
「8月になると多くなるよねぇ」などと軽く言ってしまう人がいるけれど、
私にしたら、8月と言わず一年中この話題は常にしていて欲しい。
特に昨今、戦前~戦時中~戦後の日本がどうだったか、知らないでいることに
何の疑問も持たない人が多くなってるような気がするから。
① 小説集「夏の花」 原 民喜・作
原民喜は、広島で被爆した時にその様子を野宿しながらメモをし、それをもとにこの小説を書いた。
まるでドキュメンタリーのように淡々と書かれていて、返って胸に迫るものがある。
当初はGHQの検閲に引っ掛かり発禁にされた。細部に渡ってリアリティな表現があるためだろうか。
彼は実にピュアな作家、詩人で、遠藤周作と大変親しかったそうだ。
この「夏の花」を書き上げることに全身全霊を捧げた、と思えてならない。
② 「戦下のレシピ」 斎藤美奈子・著
戦時中は、食糧も少なくなる中、家庭内でも主婦たちがいろいろ工夫して飢えを凌いでいた。
当時の婦人雑誌が紹介するレシピや食糧事情など、興味深い。
著者は『実際に作ってみて欲しい』と述べている。
例えば、里芋のおはぎ、とか、うどん入り寒天とか、ぬか入りビスケットなど、お米や小麦粉を節約するためのおやつらしい。このようなものはまだ上等な方だと私は思う。
生前、私の母も『雑草でも何でも食べたのよ』と言っていた。
飢えとの戦いでもあったのだろうけれど、実は軍の上層部の人たちはすごく贅沢をしていたと母は証言している。『戦地の兵隊さんは飢えていたのに』とも。なぜなら、母は軍の駐屯地で台所仕事(賄い?)の手伝いをさせられていたから。当時は「一億総動員」と言って、誰でも「お国」にために働かねばならなかったのだ。母も主婦であったが、戦時中は賄い係りの他に薬品会社でも働いたそうだ。
現在の「一億総活躍」という言葉は、当時を想像させてすっごくイヤな気分になる。
「一億一心火の玉だ!」というスローガンもあったと母が言っていた。
③ 「日本軍兵士ーアジア・太平洋戦争の現実」 吉田 裕・著
ドラマなどで、帰還した兵士がきれいな(汚れひとつない)軍服を着ているのを見るとすごく違和感を覚える。あんなもんじゃないぞ。時代考証はちゃんとやってるのか?
実際、ニューギニアから帰還した父が実家に帰った時「物乞い」が来たと家人は思ったらしい。それほど壮絶な体験だったのだ。
この本では、太平洋戦争で実に310万人も戦死者を出したことの原因と内容を具体的に分析して紐解いて行く。
映画やドキュメンタリー番組で観て想像はしていたが、実際のところ兵士たちがあまりにひどい扱いを受け、まるで戦争のコマ扱いであったと改めて感じた。
歯を悪くする人が続出するのに歯科医の軍医が足りないとか、お粗末な軍靴だとか、驚愕の事実が記されている。その上、兵隊たちの上下関係で事あるごとに叩かれたりいじめられたリ、まるで地獄であったと思う。そのやり方が戦後の教育現場でも続いていて特に、体育の時間はまるで軍事訓練みたいに感じたこともあった。
戦争体験者が口を閉ざすはずである。思い出したくないほど辛かったのだ。
もう一冊↓
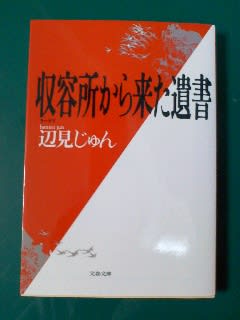
「収容所(ラーゲリ)から来た遺書」 辺見じゅん・著
戦後、シベリア抑留中に亡くなった兵士の遺書を仲間たちが、彼の遺族に伝えた方法とは。
この中で、収容所で可愛がられていた「クロ」という犬のことが出てくるのだが、数年前にこのクロの話を新聞で読んで、号泣したのを覚えている。
捕虜だった兵士たちが引き上げてくる時、港でクロが後を追って海に飛び込んだという件。
ただ、この本ではあくまでも事実が記されているので、クロのことはサラリと書いてある。
強制収容所にあっても、仲間を信じ最後まで想いを実行しようとしたことに胸が熱くなる。
人間らしい理性と知性を失わなかった彼らの強い心に、磨かれた魂を感じた。
今、戦争に反対することを言うと何やら火の粉が飛んでくるようであるが、
何も勉強しない輩が自分と違うものを排除しようとする風潮がそうさせて、オソロシイ世の中になったもんだと嘆いている。
私にしたら、8月と言わず一年中この話題は常にしていて欲しい。
特に昨今、戦前~戦時中~戦後の日本がどうだったか、知らないでいることに
何の疑問も持たない人が多くなってるような気がするから。
① 小説集「夏の花」 原 民喜・作
原民喜は、広島で被爆した時にその様子を野宿しながらメモをし、それをもとにこの小説を書いた。
まるでドキュメンタリーのように淡々と書かれていて、返って胸に迫るものがある。
当初はGHQの検閲に引っ掛かり発禁にされた。細部に渡ってリアリティな表現があるためだろうか。
彼は実にピュアな作家、詩人で、遠藤周作と大変親しかったそうだ。
この「夏の花」を書き上げることに全身全霊を捧げた、と思えてならない。
② 「戦下のレシピ」 斎藤美奈子・著
戦時中は、食糧も少なくなる中、家庭内でも主婦たちがいろいろ工夫して飢えを凌いでいた。
当時の婦人雑誌が紹介するレシピや食糧事情など、興味深い。
著者は『実際に作ってみて欲しい』と述べている。
例えば、里芋のおはぎ、とか、うどん入り寒天とか、ぬか入りビスケットなど、お米や小麦粉を節約するためのおやつらしい。このようなものはまだ上等な方だと私は思う。
生前、私の母も『雑草でも何でも食べたのよ』と言っていた。
飢えとの戦いでもあったのだろうけれど、実は軍の上層部の人たちはすごく贅沢をしていたと母は証言している。『戦地の兵隊さんは飢えていたのに』とも。なぜなら、母は軍の駐屯地で台所仕事(賄い?)の手伝いをさせられていたから。当時は「一億総動員」と言って、誰でも「お国」にために働かねばならなかったのだ。母も主婦であったが、戦時中は賄い係りの他に薬品会社でも働いたそうだ。
現在の「一億総活躍」という言葉は、当時を想像させてすっごくイヤな気分になる。
「一億一心火の玉だ!」というスローガンもあったと母が言っていた。
③ 「日本軍兵士ーアジア・太平洋戦争の現実」 吉田 裕・著
ドラマなどで、帰還した兵士がきれいな(汚れひとつない)軍服を着ているのを見るとすごく違和感を覚える。あんなもんじゃないぞ。時代考証はちゃんとやってるのか?
実際、ニューギニアから帰還した父が実家に帰った時「物乞い」が来たと家人は思ったらしい。それほど壮絶な体験だったのだ。
この本では、太平洋戦争で実に310万人も戦死者を出したことの原因と内容を具体的に分析して紐解いて行く。
映画やドキュメンタリー番組で観て想像はしていたが、実際のところ兵士たちがあまりにひどい扱いを受け、まるで戦争のコマ扱いであったと改めて感じた。
歯を悪くする人が続出するのに歯科医の軍医が足りないとか、お粗末な軍靴だとか、驚愕の事実が記されている。その上、兵隊たちの上下関係で事あるごとに叩かれたりいじめられたリ、まるで地獄であったと思う。そのやり方が戦後の教育現場でも続いていて特に、体育の時間はまるで軍事訓練みたいに感じたこともあった。
戦争体験者が口を閉ざすはずである。思い出したくないほど辛かったのだ。
もう一冊↓
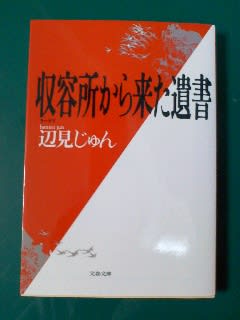
「収容所(ラーゲリ)から来た遺書」 辺見じゅん・著
戦後、シベリア抑留中に亡くなった兵士の遺書を仲間たちが、彼の遺族に伝えた方法とは。
この中で、収容所で可愛がられていた「クロ」という犬のことが出てくるのだが、数年前にこのクロの話を新聞で読んで、号泣したのを覚えている。
捕虜だった兵士たちが引き上げてくる時、港でクロが後を追って海に飛び込んだという件。
ただ、この本ではあくまでも事実が記されているので、クロのことはサラリと書いてある。
強制収容所にあっても、仲間を信じ最後まで想いを実行しようとしたことに胸が熱くなる。
人間らしい理性と知性を失わなかった彼らの強い心に、磨かれた魂を感じた。
今、戦争に反対することを言うと何やら火の粉が飛んでくるようであるが、
何も勉強しない輩が自分と違うものを排除しようとする風潮がそうさせて、オソロシイ世の中になったもんだと嘆いている。


























もう色んなことを感じる年頃なので記憶が鮮明です。
子どもの私が話を聞きたがるのでよく話してくれました。
戦争を知らない子どもたち
私たちが最後かも知れませんね。
コメントをありがとうございます。
まりちゃんのお母様も、戦争中に、そして戦後もさぞご苦労なさったことと思います。
まりちゃんがいろいろ聞きたがっていた、ということはとて貴重なことですね。
そのようなお子さんの方が少なかったと思います。
私は自分から、というよりは昔の古いアルバムを見るのが好きで、それを見ながら母に質問して行った時に
戦争の話もその中にあった、という感じですね。
まりちゃんと同じく、母の話は結構衝撃的なこともあって、忘れられません。
戦争体験者から直に話を聞けた経験は貴重ですよね。
戦争に関する本はいくつか読みましたが、読むたびに悲しくなります。
<戦争体験者が口を閉ざすはずである。思い出したくないほど辛かったのだ。>
これ、ものすごく解ります。共感です。
実は私のアメリカ人の夫、ベトナム戦争へ行きました。戦争の話はこちらが聞けば話してくれましたが自分からはあまりいいませんでした。
夜中に毎晩、うなされてたので、よほどひどい体験だったんだろうなと推測するだけです。
「戦争を良いとか悪いいう形容詞を使って語るのは無理がある。戦場には死体と人殺ししかいないんだから」と夫が言ってたのを今でもよく覚えています。
ここに紹介された本、どれも興味深い内容ですね。
読んでみたいです。
図書館で探してみますね。
ありがとうございます。
8月は結構メディアでも戦争に関するテーマで放送されますが、それ以外の月もいえ一年中取り上げてもらいたいくらいです。
そうでないと、日本人はますます平和ボケになって行きそうですから。
leelinさんのご主人はベトナム戦争に行かれたのですね。
当時、映画ではこの戦争を扱った作品が結構上映されたのをいくつが観ました。
「7月4日に生まれて」とか「ディア・ハンター」とか。
帰還後にトラウマになった方も多いとか・・・
ご主人も夜中にうなされる程、相当お辛い経験をなさったこととお察しします。
ご主人の仰る通りです。「戦争によい戦争というものなどない」と言った人がいましたが、その通りですね。
どれも深く重いテーマの本ですが、私は知りたい一心で読みました。知る前と後では気持ちも違いました。
戦争の悪をより感じるようになりました。
leelinさんも読まれて共感して頂けたら幸いですm(__)m