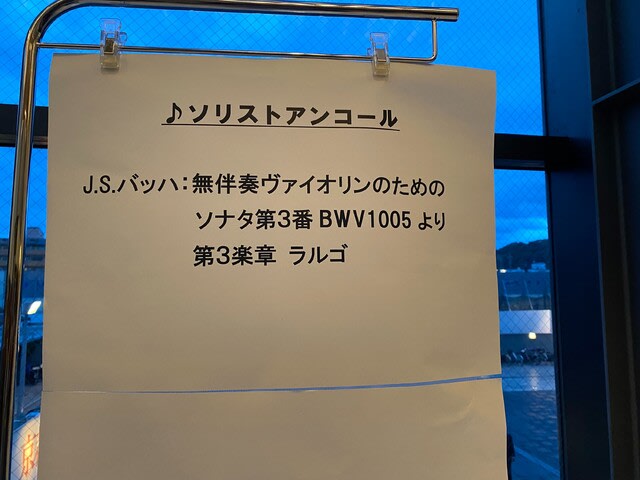現在公開中の御常御殿の部屋が、11月17日までで一旦公開を終了するので、再訪しようと思い立った。「松鶴の間」「雉子の間」「御納戸」である。20日から2025年3月16日までは「四季草花の間」「耕作の間」「萩の間」が公開され、3月19日からは、再度変更されるようだ。
「松鶴の間」は、主の居室であったそうだ。金銀の雲、大ぶりの松に鶴が描かれ、非常にきらびやかで力強い。床の間は東側に設えられているので、主は床に背を向けて座り、西側の襖を開け放って広々とした庭を眺めたに違いない。
「雉子の間」は、松鶴の間のすぐ東にある部屋で、主の寝所。前回の観覧の際は蚊帳吊り金具に気づかなかったが、四方の柱に二段に金具が取り付けられていた。二重に蚊帳を吊るしたなら、蚊に悩まされることもなくぐっすりお休みになれたことだろう。金色の雲に紅葉と雉。松鶴の間ほど豪華ではないぶん、落ち着きを感じる。
「御納戸」は雉子の間の東隣りにある部屋で、主の世話をする者が控えた部屋であったらしい。納戸という名がついているが、漆喰の白壁の下は一面、緑青地に金色の朽木雲文様の唐紙の襖で、豪華な印象。
御納戸と萩の間(今回は非公開)の間に、地図上で狭い部屋のようなものがあり、ガイドの方に質問すると、二階へ続く階段があるとのこと。御常御殿には、ほかにも、もう一か所階段があるらしい。以上が御常御殿についての個人的なまとめ。
さて、今回の本丸御殿の見学ルートは、次の通りである。
①「使者の間」→②「殿上の間」「公卿の間」→③御書院の南側三部屋(「三の間」「二の間」「一の間」)→④渡廊下→⑤御常御殿の南側三部屋(「松鶴の間」「雉子の間」「御納戸」)→⑥御湯殿→⑦渡廊下→⑧御書院の東側・北側廊下に面した四季の間(「夏の間」「冬の間」「秋の間」)→⑨御書院廊下北側にある雲鶴の間(「一の間」「二の間」「三の間」)→⑩「雁の間 東」「雁の間 西」→「取次の間」「玄関の間」
⑧「四季の間」の障壁画は、どれも地味。
⑨「雲鶴の間」の名は、雲鶴模様の唐紙が襖に使用されていることからきている。緑青地に、金で鶴と瑞雲が描かれ、華やかであった。また、⑧「冬の間」「秋の間」と⑨の三部屋は廊下を挟んでそれぞれ南と北に並んでいるが、廊下に面した襖は白地に銀砂子だか、落ち着いたきらめきのある七宝文様の唐紙が使用されていた。⑤の唐紙についてもそうだが、すべて元の文様を復元したものであるとのこと。
⑩「雁の間」は、家来たちが使用した部屋である。襖の多くに雁の絵が見られる。「雁の間 西」の西壁面に一間半ほどの棚があり、棚奥の壁に二羽の雁が描かれているのだが、上部に描かれた一羽は座らないと見えない。この棚は、元は「雁の間 東」の東壁面にあったとパンフレットに記載されている。では、二羽の雁は?移築の際、部屋の配置が変わり、障壁画も切り貼りされたというから、雁は棚奥に描かれたものではなかったのかもしれない。どれも、水墨画でありながら、全く寂しさを感じない。かっこいい障壁画である。強い生命力と力強さを感じる雁の絵は、宮家の御殿というより、武士のお屋敷にふさわしいようにも思える。
二度目の見学だが、御殿の造りが複雑で、どこを歩いているのかわからなくなった。来週以降、また別の障壁画を見に行こう。


















 書院より本堂の方を撮影。
書院より本堂の方を撮影。 書院南側に広がる苔。
書院南側に広がる苔。
 蹲踞の足元にツワブキ。
蹲踞の足元にツワブキ。 鳥居の右には鐘楼。
鳥居の右には鐘楼。 鳥居の左手に井戸。
鳥居の左手に井戸。







 北山大橋より北側を望む。
北山大橋より北側を望む。

 宝池橋より比叡山を望む。
宝池橋より比叡山を望む。