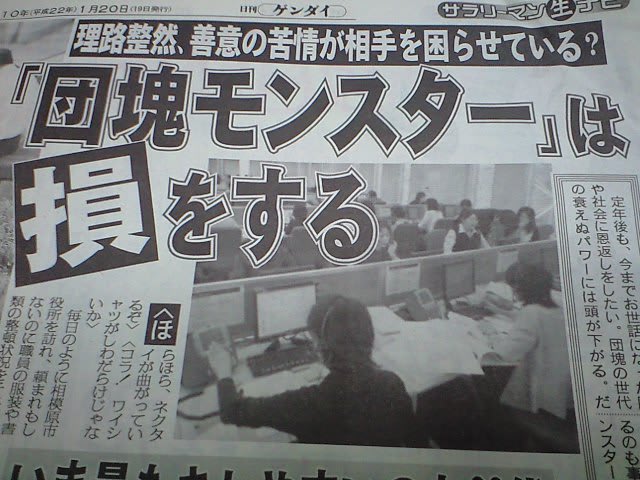
「団塊モンスター」という言葉が、しばしばメディアを賑わすようになりました。
現役から引退し目的意識を失った団塊世代の定年退職者が自分の居場所を無くす中、社会の様々な場面でモンスタークレーマー化し、別な意味で存在感を発揮しているという指摘です。
第二次大戦が終戦を迎えた1947~49年頃の第一次ベビーブームに生まれ、戦後日本の高度成長を支え、謳歌した人たちが(いわゆる)「団塊の世代」です。彼らが生まれた3年間は年間出生数がいずれも260万人を超えており、現在の日本の世代別人口構成において突出した割合を占めています。
団塊の世代が10代の後半から20歳の前半くらいまでの時期、日本の産業界は人手不足が顕著であり、若者たちは「金の卵」と呼ばれ持て囃されていました。この時代は地方出身者が集団就職などで都会へ出てくるケースも多く、核家族化が進む中、モーレツ社員や専業主婦として企業を中心とした生活にどっぷりとつかってきた世代と言えるでしょう。
団塊の世代はその人口規模の大きさにより、子供のころから学校では1クラス50人~60人のすし詰め状態であったうえ、学級数も1学年2桁のクラス編成が普通だったはずです。
そうした中、当然、彼らは(主に学校を舞台とした)競争社会を所与のものとして受け入れ、人間関係に揉まれながら成長してきました。さらに、教育的には1947年(昭和22年)に日本教職員組合が設立され、その濃厚な影響を受けた(主張する)世代であるともされています。
一方、団塊の世代では中学卒業と同時に働きに出る人もまだ多く、大学進学率は15%~20%程度で大半の高校生は卒業と同時に企業に就職していました。また、大学に進学した人の多くは1960年代後半から70年にかけての学園紛争の荒波にもまれ、安保闘争、ベトナム戦争反対の反体制運動に身を投じた者も多かったことから、「全共闘世代」などとも呼ばれているようです。
さらに、70年安保闘争が不調に終わった後、過激派として反社会的な暴力行為をエスカレートさせ、「あさま山荘事件」や「よど号乗っ取り事件」、連合赤軍による海外でのテロ行為などを企図したのも彼らの世代です。
その後、経済の高度成長期も終わり、オイルショック後の景気の低迷に続くバブル経済、そしてその崩壊、さらに「失われた20年」と呼ばれた賃金削減やリストラなどが直撃する時代を経て、彼らの多くは何とか定年を迎え現在では年金生活も板についたころかもしれません。
さて、そんな激動の時代を過ごしてきたパワーあふれる団塊の世代も、もうすぐ齢70歳を迎えようとしています。
基本的に1億総中流意識の中で育ち、学生運動を体現した後は会社人間として朝日新聞を読みながら権利意識やディベート力を磨いてきた人たちです。会社や地域社会の重しが次第に取れていき、「人生の先輩」として発言や行動が(他人を気にせず)いよいよ自由にできるようになる中で、彼らの公共の場でのマナー違反やクレーマー化が問題視される場面も増えてきているようです。
3月14日の「東洋経済on line」では、そうした団塊の世代の(あぶない)行状?について、「横暴すぎる老人のなんとも呆れ果てる実態」と題する興味深いレポートを掲載しています。
JR関係6社や日本民営鉄道協会などの調査によると、鉄道係員に暴力を振るった加害者の年齢は、2014年度まで5年連続で、何と60歳代以上がトップだったということです。実はそうした加害者の6割が飲酒をしており、時間帯としては終電時刻前後でのトラブルが多いのが特徴とされています。
記者が取材したところでは、加害者となる高齢者には自尊心が強い人が多く、「人に注意されたり何かを教えられたりするのを嫌がる傾向が強いということです。
記事によれば、駅でよく起こるのが指定席の券売機でのトラブルで、操作方法がわからないまま挑み続け、係員が助けに入ろうとしても「うるさい!」と拒否。そのうち後ろに並んでいる人ともめ事になるといったケースも多いのだそうです。
また、駅ばかりでなく、高齢者が多く集まる病院での暴力や暴言、セクハラなども多発しているとこの記事は述べています。
私立大学病院医療安全推進連絡会議が2011年に11施設の全職員に調査をした(有効回答約2.3万人)結果では、患者やその家族から暴力を受けたことがある職員は実に4割を超えていたということです。
院内暴力などをふるった人を年齢別に見ると、暴力では70歳代、セクハラでは60歳代の事例が最も多く、暴言についても60代が2番目に多いということです。病院では彼らの院内暴力や悪質なクレームによって、優秀な若い職員たちが辞めてしまうことも少なくないと記事はレポートしています。
一方、昨今では、高齢者による犯罪も深刻な問題となっているとの指摘もあります。
一般刑法犯の検挙人員数を年齢別に見ると65歳以上は約4.7万人に上っており、14~19歳に次いで高い水準になっています。検挙人数全体が約25万人と10年前から3割強も減少しているにもかかわらず、高齢者による犯罪は概ね1割増加しているということです。
因みに、高齢者の犯罪で最も多いのは「窃盗」で約3.5万人。10年前と比べて約3割増加しているとされます。しかし、増加率で言えばもっと増えている犯罪もあり、「暴行」は約3500人で10年前の約4倍、傷害は約1600人で1.5倍になっているということです。
一般に、年齢を重ねるにつれ性格は穏やかになり、好々爺然としてくるというイメージを抱きがちですが、実際は歳を取れば取るほど暴言やエキセントリックな言動など「キレやすくて自己中心的」になるのは(ある意味)必然なのかもしれないとレポートは説明しています。
人の感情をつかさどる脳は年を重ねるごとに萎縮することが明らかになっており、その中でも早い段階から萎縮が始まるのが、衝動の抑制や理性、意欲などを担う「前頭葉」だということです。そして、前頭葉が老化すると感情抑制機能の低下や判断力・意欲の低下などが起こり、さらに喫煙や飲酒などの長年の生活習慣によって脳の機能低下は時系列的に進んでいくとされています。
現在、4人に1人が65歳以上の高齢者という超高齢社会を迎えている日本ですが、45年後の2060年には、2.5人に1人というかつて人類が経験したことのない(極めて極端な)状況を迎えることが見込まれています。
当然、高齢者を巡る様々な問題がこれからさらに顕在化してくると考えられ、年老いた親を抱える現役世代にとって、これは決して「人ごと」ではないとレポートは指摘しています。
議論の方向性を間違うと深刻な世代間対立にも繋がりかねない問題ですが、(一方で)ここで肝に銘じておかなければならないのは、誰もがいずれは高齢者になるということです。
多様な高齢者を社会としてどう受け入れていくのか、その態勢作りが不可欠になっていると結ぶ今回の東洋経済のレポートを、わが身を振り返り私も大変興味深く読んだところです。





















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます