京セラ美術館で現在開催されている「京都の美術 250年の夢 第1部~第三部総集編」。
前期は10/10~11/8、後期は11/10~12/6です。


明治維新から100年前の江戸後期から現代にかけて、日本画の代表作家を中心に、同時代に活躍した工芸家や書家、明治期に登場した洋画家、彫刻家、版画家、さらには戦後の現代美術の新鋭作家を加えて、「京都の美術」の250年の歴史を彩った名品を三部構成で紹介します。
第1部 江戸から明治へ:近代への飛躍
江戸後期の京都では、異端の画家伊藤若冲や曾我蕭白をはじめ、文人画家の与謝蕪村、新登場した写生画の円山応挙、四条派の始祖・呉春、個性派である長沢芦雪らが活躍していました。この後、幕末から明治にかけて、新しい時代を迎えた京都の美術・工芸の発展を「江戸から明治へ」と連続的に回顧します。

第2部 明治から昭和へ:京都画壇の隆盛
明治後期から昭和初期、新しい日本画の創造に向けた活動が展開されました。竹内栖鳳を中心にした京都画壇では、大正期には国画創作協会が結成され、黄金期をむかえます。また明治後期には浅井忠が、京都の洋画壇を確立します。工芸界でも浅井は海外思潮をもたらし、大正期には神坂雪佳が日本的な意匠を普及させる中、芸術としての工芸の道が切り開かれました。

第3部 戦後から現代へ:未来への挑戦
戦後の激動の中、日本画、工芸、書の伝統が問い直され、1960年代以降、現代美術と呼ばれる潮流が生まれます。日本画では、新団体の結成と共に新しい日本画表現が探究されました。工芸でも、伝統の継承と新たな表現との葛藤から、使用目的を排した作品(オブジェ)が探究されます。洋画でも、社会的な主題が指向され、書には抽象美術との関係から前衛書が登場しました。
本館光の広間 天の中庭から会場に入ります。

雨樋があか(銅)で作られているものがあります。


とにかくここも出展数が多く、全部見るのに2時間かかりました。
会場を出るともう夕暮れ。
秋の日はつるべ落としですね。


京都駅までは同じく100系統のバスでもどります。
もう真っ暗。
ライトアップされた京都タワー。

駅ビルの壁に映っています。

運よく近鉄電車乗り場へ向かうと奈良行き急行に乗れて、ギリギリ座ることができました。
戻ってくると電線に多くのムクドリ。
糞の落下に気を付けながら部屋へ戻りました。

歩きも歩いた、万歩計では19000歩を超えています。
一息ついて窓の外を見ると、東の山の上にオレンジ色に輝く火星。


本当は京セラ美術館からすぐのところにある細見美術館へも行きたかったのですが、
予定外に時間がかかったので今回はパスしました。

















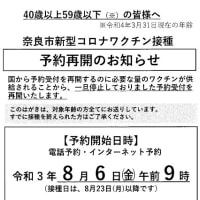

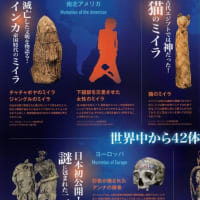

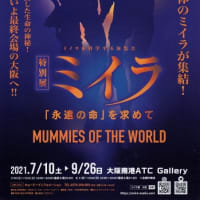
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます