
 暑い日が続く中、見学者1名を迎えて行われた7月の読書会。もう少しすれば、人類が死に絶えてしまうという重い内容ながら、なかなか好評だったと思います。
暑い日が続く中、見学者1名を迎えて行われた7月の読書会。もう少しすれば、人類が死に絶えてしまうという重い内容ながら、なかなか好評だったと思います。★静かで(波乱がなさすぎて)読むのが大変だった。物足りない。人類が滅びるというような状況にでもならなかったらやらないようなことをした人に共感。レースに参加したオズボーン氏とか。
★核戦争後の終末の物語といえば『北斗の拳』や『マッドマックス』などのバイオレンスに満ちたものを思い浮かべてしまう。それと比べると起伏がないのが物足りない。
理知的なのは好感が持てる。名作だとは思います。
★核戦争が起こった!ということでどんなにすごいことが始まるの?と思ったら、戦争の話ではなく家族の生活の話だった。自分がいかに死すべきか気になってしまう。
★みんな死んでしまう救いのない話をキャラクターをうまくつかって描いている。古臭いところはあるにせよ、その時代で考えられる核によっての人類の終末をうまく書いているのでは。
★SFとしての設定の古さは否めないが時代を超えた普遍性がある作品。
自分だけがあと何カ月しか生きられないと言われるよりは、みんなが死ぬんだよといわれるほうが冷静でいられるのでは?
★古さを感じるSF。書かれた時代に読めば感動するかも。技術の進歩を知っているので描かれた状況に陳腐さを感じてしまう。いい小説だけど。
★SFはあまり好まないが、読んでよかった。じわじわと最後が近付いてくる希望がなくてつらい話。オズボーンさんがいい味だしてた。
★今話題の『1Q84』のヒロインが映画の『渚にて』を見たという記述があった。
登場する人みんな落ち着きすぎじゃないか?もっと自暴自棄になるひとがいるのでは?
ドワイトとモイラの関係もプラトニックできれいすぎ。人間が描かれているけど今っぽくない。
★旧訳版は古い言葉づかいがあります。「てんやわんや」とか「およしになって」とか。
せっかくオーストラリアが舞台なのにコアラやカンガルーが出てこない。メアリーとピーターは嫌い。どろどろした葛藤はでてこなくて古い物語なのできれいになりがちなのでしょうか。生活している様子はよく描かれていた。
★テーマは重いけれど書き方は明るい。ディティールがきっちり描かれている。女性像が古臭い。
★気になっていた作品だが、やっと読めてよかった。すごくおもしろかった。地図を見て、あとはこれしか人がいる地域がなくなったと思うとぞっとした。文体は明るいがヒタヒタとした恐怖がおしよせる物語。あえてパニックを描かず、登場人物を絞りこむことで静かに人類がやってしまっとことを提示し、怖さを描いたのでは。
★SFに分類されているが、それは設定だけ。モイラの描き方などはキリスト教的倫理観を感じる。死が確実とわかっていて苦痛を長引かせないために自害用の薬を配るのは非常に合理的な考えだが、仏教国の日本ではそこまでしないだろう。国柄の違いもおもしろく読んだ。
★個人的には最後の迎え方にリアリティーを感じる。残された日々はいつも通りにしか生きられないのでは。故郷に帰りたいという気持ちも理解できる。
★おもしろい。淡々と逃れられない死をそれぞれのキャラクターごとに描いている。ドワイト艦長がかっこいい。著者が英国人なので死をきれいに受け入れる書き方なのか。
自分はこのように潔く死を迎えられるだろうか?
★読んでよかった。なにげない日常を描いてこの長さを最後まで読ませる力がある。直接手を下していないのに人類滅亡という事態になってしまったのに、なんでアメリカやオーストラリアの人々はもっと怒らないのか。宗教観の違い?
★ドラマティックさが足りない。強く感動しなかったが、放射能の怖さがわかった。
講師から
核戦争による人の終末はいろいろな描き方があるだろう。作者は執筆当時の最先端技術である原子力潜水艦を舞台にし、限られた人物と個人の営みに終始視点をおいて描いている。
時代を超えた人類の終末の描き方として一番怖い。この力量はたいしたもの。
時代を超えて死なない作品と言える。
私は旧訳で読んでいるはずなのですが、すっかり忘れてました。この世の終わりというのに静かな話だったなあくらいしか思っていなかったのです。終末ものの映画などはパニックが起きたり、滅亡を避けようとあがいたり非常に激しいものになりがちです。
今回また読んでみて、この静けさが非常に怖さを醸し出しているなと思いました。アメリカまで潜水艦で行って、動いている通信機は風に揺れる窓枠が触れているだけだったという記述にも、そこでドラマが起きないという期待外れより「やっぱり誰もいない」という恐怖を強く感じました。
古い作品ですが、読んでみると非常に考えさせられることが多い。生きること死ぬこと。核兵器の怖さ。エネルギーが限られている状況になったら。などなど
やはり名作と言われるだけの理由があるのですね。
同じ作者の『パイド・パイパー』もたいへんおもしろい作品ですのでお薦めします。
また、人類の静かな終末を描いた作品として、伊坂幸太郎の『終末のフール』があります。
読み比べてみるのも一興では。
『渚にて』は映画化されて有名になりました。つい最近テレビで放映されたそうです。
ご覧になった方いかがでしたか?
読書会に出席できなかった方。映画を見て感想のある方。コメントよろしくお願いします。
 舞浜嵐子
舞浜嵐子



















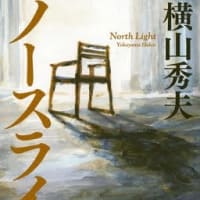






原作が、明るく淡々とした日常に迫る静かな恐怖を描いたのに対し、映画の方は、終末までのわずかな時間を精一杯生きる、残された人々の美しい哀しみが主旋律となっているようでした。
安定感抜群の好男子グレゴリー・ペック、"官能女優"の名に恥じないエヴァ・ガードナーの見事な女っぷり、「サイコ」以前のアンソニー・パーキンスのうっとりするようなハンサム。
昔のハリウッド映画には、このようにいつも美男美女があふれていましたよね。
しかしこの映画の核心は、フレッド・アステア演じる科学者オズボーンだと思います。
原作で20代だったオズボーンを、なぜすでに老境にさしかかったアステアが演じたのかと考えてみました。
彼は、美しいモイラに言い寄って振られた過去を持ちながら、「若い頃からの夢だったのさ」とレースに熱中したり、
武力で平和を守れるなんて考えは間違っていた!と皆の前で吐き捨てるセリフがあったように、
実現できなかったこと、やり残した多くの夢など、生きることのやるせなさを体現し、また人類を破滅に至らしめたその思いあがりを糾弾するなど、
この映画独自のメッセージを観客に伝える重要な役どころを担っていたように思います。
若い俳優が演じるのは難しいかもしれません。
テーマ曲の"Waltzing Matilda"がさまざまなアレンジで繰り返し全編に流れますが、その陽気なメロディラインにもかかわらず、特殊な環境下でのメロドラマが醸し出す哀しみを、その都度美しく盛り上げていました。
映画化されたこの作品においては、もはや「およしになって」というせりふがあったとしても何の違和感もないでしょう。
最後に。
例会で不評だったホームズの妻メアリーですが、本を読んで別段嫌いじゃないけどと思った人はこの映画で彼女のことを嫌いに、本で嫌いだった人はますます嫌いになるに違いありません。
夫に薬を渡されて、「将校になると知っててあなたと結婚したのよ」なんてせりふ、美人で可憐な品のある女優さんなのに、ほとんど悪役ですがな。
かわいそうに・・・。
さて、当時、がちがちのSF少年だった私は、『渚にて』をはじめ、人類破滅テーマの作品を好んで読んでいました。そうした中から忘れられない破滅テーマSFのいくつかをご紹介させていただきたいと思います(なお、今回は、70年代に発表された日本ものに限らせていただきます)。
まずはじめに、いわゆる「人類破滅テーマ」といわれる作品について。このテーマのSF作品は、古今東西、多くの名作がありますが、それらは、①本当に人類(あるいは生命すべて)が死に絶えてしまうもの、②多くの人類は被害を受けるものの、最終的な破滅の危機を未然に回避するもの、③破滅を暗示させるものの、結末を保留とするもの、に大きく分かれると思います。
また、破滅の原因としては、大きく、a人類に原因があるもの、b自然災害によるもの、c異種生命体(宇宙人など)の侵略によりもの、などに分かれています。bはパニックもの、cは侵略テーマ、などと呼ばれることもあります。
小松左京『復活の日』。日本を代表する破滅テーマの傑作中の傑作。上記の分類で言えば、②パターンに該当します。「たかが風邪」で、一部の南極越冬隊を除き死に絶えてしまう人類。その過程を、時に文明論をまじえてワールド・ワイズの視点から描く前半の力技。そして、人類「復活の日」を予感させる後半で描かれた、人類とその未来に対する圧倒的な希望。ちなみに、プロローグで、ノーマンズ・ランドと化した東京に向う潜水艦のシーンは、明らかに『渚にて』へのオマージュでしょう。
小松左京『見知らぬ明日』。③-c型。文革中の国を閉ざした中国奥地に飛来し、人類殲滅の殺戮を続ける異性人。圧倒的技術力といっさいのコミュニケーションをこばむ異性人の前に、なすすべもない人類の姿を、当時の世界情勢がらみでシリアスに描きます。唯一の対抗策、水爆ミサイルを、異性人の基地のひとつ、富士山頂向けて打ち込むという国連決定に同意せざるを得ない日本政府の姿を描いたラストは、被爆国日本への痛烈な皮肉ともとらえることが出来ます。
筒井康隆『霊長類南へ』。東西冷戦下の時代にあって、aパターン、特に核戦争による破滅SFは多く書かれました。筒井みずからが「早すぎたライフワーク」と位置づけるこの作品は、核戦争がおこった世界で繰り広げられる人類の愚行を、彼独特のブラックな筆致でときにドタバタ仕立てで、ときにシリアスに活写します。南極点で死ぬ(これは『復活の日』へのパロディか?)人類最後の男が漏らす最後の言葉、「ナンセンス」が、決まっています。
松本清張『神と野獣の日』。SFを毛嫌いしていた清張唯一のSF。③-cパターン。ある日、東京に向けて発射された「2発」の核ミサイル。パニックにおちいる東京都民の姿を、筒井とは異なる社会派作家の視点でリアルに描きます。後楽園球場に落下した「不発弾」ミサイルに、生き残ったことを喜ぶ都民。間もなく落下してくるもう1発のミサイルの存在も忘れて……。
新井素子『ひとめあなたに…』。隕石の衝突で数日後に、世界が破滅してしまう。東京練馬に住む女子大生は、鎌倉に住む彼にひと目会いたいと、西へ向けて歩き始めます。その道筋で彼女が出会った何人かの女性たちと、その人生模様……。今読むと、壁に投げつけたくなるような出来の作品ですが、当時は素直に感動していたのです。
半村良『収穫』。ある日、世界各地に出現した巨大な宇宙船に向って、整然と隊列を組んで歩き始めた人びと。全人類を飲み込んだ宇宙船は地上を離れ、あとにはごく一部の生存者が残されます。なぜ彼らには宇宙人のメッセージが伝わらなかったのか、人類を連れ去った宇宙人の意図は何か、コミューンを作り真実が知らされるときを待つ彼らの運命は……。人類家畜テーマとも言える、著者デビュー作の名短編。
光瀬龍『たそがれに還る』。永劫の時間と刹那に生きる人類の姿を描いた、日本ハードSFの最高傑作。西暦3785年の未来、太陽系全域に進出した人類は、宇宙のかなたから近づいてくる破滅招来体の存在を知ります。英知と技術力のすべてを傾けて破滅回避にまい進する人類の姿を、さらなる未来の歴史家の視点から描きます。破滅は回避されるのでしょうか? 分類は③パターンです。
星新一『午後の恐竜』。ショート・ショートでありながら、私に生涯忘れられない感動を与えてくれた作品です。生命の発生から人類の誕生までのドラマが、映画の映像のように世界中で繰り広げられたある日。死の直前に人はその一生を走馬灯のように垣間見るといいますが、これは人類規模のパノラマ視現象だったのです。のどかな日曜日に起こった珍事をめぐる一家族の姿と、緊迫した水爆ミサイル盗難事件を絶妙なカットバックで描きます。地球規模、人類規模のパノラマ視現象が、一個人のそれに収斂されるオチの切れのよさ。
以上、長々と失礼しました。