

坂東 眞砂子 『傀儡(くぐつ)』
集英社 2008年 (左)
集英社文庫 2012年 (右)
信仰とは、生きることとは、死ぬこととは──
鎌倉時代、四人の男女の運命が交錯する。著者渾身の歴史長編!
鎌倉中期、執権・北条時頼が権力を振るう頃。仲間たちと唄や踊りの芸を売って自由に生きる傀儡女・叉香は、復讐のために鎌倉を目指す武士や、武士に家族を殺された瀕死の女、信仰の本質を追い求める西域から来た僧らと出会う。全く異なる境遇で生きる四人の男女の運命が、鎌倉で交錯する。仏教と武士道が権力と結びつき、大きな流れを形成していった歴史の分岐点を舞台に描かれる渾身の歴史長篇
<例会レポート>
レポートとは、時間が経つにつれ、記憶が薄れることはもちろん、やらねばと思えば思うほど書きたくない気持ちがどんどん大きくなっていくものだ・・・。と毎月の推薦者のお気持ちが少しわかりました。いえいえ、嬉々としてやっている方もいらっしゃいますよね。失礼。
今月の課題本は、坂東 眞砂子の「傀儡」 すでに題名と筆者名の時点で、旧漢字やら難しい漢字が出てきて、気が遠くなりそう・・・。たまたまなのか、私とおなじお気持ちの方がいらしたのか、男性8名、女性10名と少な目の人数。でもでも、鎌倉在住の会員が鎌倉の地図をを作ってくださったり、見学の方が来てくださったりとほのぼのムードで開催されました。
【皆さんの感想】(順不同&一部抜粋&略)
・登場人物のそれぞれのエピソードが上手くからまっていない。
・叉香の名前はお釈迦様からきたのでは・・
・派手さやダイナミックさが足りない。投げ出すほどつまらなくはないが、期待はずれ。
・叉香の自由でたくましい生き方に感銘を受けた。
・おも本に入会してからの菊池先生の推薦本の中では一番面白かった。
・網野史観を生かし、民の生活を生き生きと描いている。
・時代考証が十分にできている。ラストに救いがある。
・農民の妻が武士に復讐するという設定が面白い。権力者の後ろに誰かがいるという設定を傀儡とかけているのでは・・
・作者は、現代の言葉で鎌倉時代の人達の内面を描くということに挑戦している。
【菊池講師のお話】
群像劇としたのは、作者の意図があった。冒頭のシーンは、時頼の政権を固める前から始まっている。時頼の死を1つの時代ととらえ、物語を光と影、傀儡さながらに二重に描いている。 宗教の話はちらばりすぎてわかりにくいが、網野史観のテキストとして読むのは悪くない。最後の叉香の子供をあげるというエピソードは作者が加えた話であり、影に対する光のエピソードの役割を果たしている。
日本の歴史では、節目節目で天皇制が話題になる。会員のコメントにもあったように、乳児の生存率が低かった昔は6歳までは社会全体で子供を育てるという共通認識があったように思う。ラストシーンは、その意識の表れ。
【報告者の感想】
時代ものと聞いて、とっつきにくいかなと思いきや、読むほどにお話に引き込まれました。今とは異なる価値観の時代を舞台にした話なのに、どこか共感や納得する部分もあり、8百年以上も以前に生きる人達に思いを馳せました。お持ちいただいた鎌倉の地図もわかりやすく、秋の鎌倉を歩いてみたくなりました。また、今回は、新人さんの長く印象的な感想があったり、菊池講師の熱の入った解説もあったのですが、他の連絡事項があり時間が足りない感が否めなかったのが少々残念でした。



















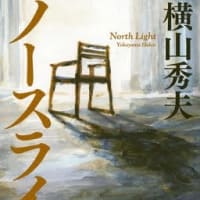






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます