
河出文庫 ¥799
謎の男・麦に出会いたちまち恋に落ちた朝子。だが彼はほどなく姿を消す。三年後、東京に引っ越した朝子は、麦に生き写しの男と出会う…そっくりだから好きになったのか?好きになったから、そっくりに見えるのか?めくるめく十年の恋を描き野間文芸新人賞を受賞した話題の長篇小説!
ちなみに写真は映画に合わせて発売された増補版ですが、単行本、増補版ではない文庫でもOKです。
なお、増補版は「森泉岳土のマンガとコラボした魅惑の書き下ろし小説を収録」だそうです。
(映画情報)
濱口竜介監督 東出昌大主演
第71回カンヌ国際映画祭コンペティション部門正式出品
2018年9月1日全国公開
例会は 10月25日 木曜日 19:00に開催しました。
以下はそのレポートです。
映画を観て、読んでみたいと思ったこの作品。今回の読書会は出席者が少なかったのですが、賛否両論、話が盛り上がっていました。こんな女の子は嫌だとか、こんな人っているよね~とか、こんなの恋愛じゃないのではないかとか。楽しい時間を過ごせました。
出席者も女性が多かったし(講師を除けば男性は一人)、柴崎友香さんの作品は初めてだという人は多く、感情移入できないという意見も多かったのですが、実はとても繊細に情景を描写することによって、人を描いているのだということがわかりました。
否定的な意見としては
・彼女の何が良くて、好きになったのかわからない。ひとりよがりなのでは?
・何も起こらないうちに終わってしまった。良さがわからないけど、印象に残る。
・最初と最後の描写はとても良いが、小説には現実を超えた世界を描いて欲しいのでどっちの男性が好きでもどうでもよい。
・情景は描けているけど、登場人物の心がわからない。最後にやっと朝子の気持ちが出たのか。私には合わない。
・恋愛小説なの?あまり感情移入できない。
・タイトルが内容とあわないのでは?
・共感できることがなかった。
肯定的な意見としては
・とてもおもしろかった。
柴崎友香の作品はもともと好き。
文章が視覚的なので、映画にしたくなる気持ちもよくわかる。
登場人物のキャラクターの輪郭があいまいで、何を考えているかわからないけれど、実際の人生でも、きっぱりせずとも曖昧に流れていくことはあるのでは。
柴崎作品にはカメラを持った女性が出てくることがあるが、主観と客観の違いを表しているのではないか。麦のことは写真に撮れなかったので、朝子は麦のことを客観視できない。自分のことも写真に撮れないので、客観視はできない。亮平のことは撮影できたので、現実のものとして、彼の元にもどることができた。
麦は突然消えたので、10年たっても彼とのことに決着がついていなかった。そのためまた現れた麦について行ってしまった朝子は、決着をつけて亮平のところに戻って来られたのでしょう。良かったね。新鮮な恋愛小説と感じた。
道具立ても作りこまれているけれど、押しつけがましいとは感じない。
恋愛そのものではなく恋愛感情が書きたかった?
講師からは
仕掛けにあふれた小説。登場人物の内面を直接描くことなく、街を描写してすべてを描いている。作者は描写の力が成熟し、うまくなってきている。
街、歌、カメラの使い方がうまい。朝子はカメラを使うことによって物事を切り取っている。しかし麦は写真を取らせない=手に入らない(帰ってくるといいながら、去ってしまった執着の対象)。
なぜ、似た男性を2人出すのか。朝子にとって2人は似ていなくてはならない。それだけ麦を失った喪失感が大きいということを表しているのでは。朝子は目に見えるものにとてもこだわりがある。相手のことは書かず、朝子のことしか書いていない。
あまりはっきり書かないし、いらいらするところもあるかもしれないが、それは作者の小説作法。相手のことは考えない。とにかく朝子がどう感じたかを描いている。文章がものすごく良い。情景描写によって朝子の心理をよく表せている。
近年、女性作家は文章がうまい人がかなりいる。読者は作品に感情移入したほうがいいし、作家に惚れるのはいいこと。その作者のつくった世界に入り込んでいけるのは、読書の幸せでしょう。
映画は、小説とは違っている部分もあり、小説も読めて良かったです。会話がいいですね。大阪のことば。
あまり起伏がない話でも、雰囲気に浸れる感じがしました。(最後はちょっとドラマチック)
映画はひたすら朝子が何考えているかわからない。顔はかわいいのだけど。お友達の女性たちは、みなしっかりした人たちのようだった。
出会い方に写真展など使っており、印象的でした。カラーの映画だと思ったけど、今は白黒の映画だったみたいに記憶に残っています。猫も出ていました。最後に流れる曲も声に人工的な加工したような歌なのですが、映画の雰囲気には合っていました。(レポーター:AIさん)



















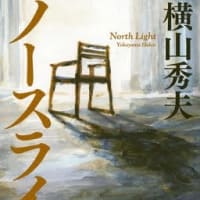






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます