リュドミラ・ウリツカヤ/著 前田和泉/訳
『通訳ダニエル・シュタイン』(上)(下)
新潮・クレストブックス 2009年![]()
「必要なのは論争じゃなくて、理解なんだ」20世紀の過酷な戦場に刻まれた奇跡の足跡。![]()
ポーランドのユダヤ人一家に生まれ、奇跡的にホロコーストを逃れてゲシュタポでナチの通訳をしながらユダヤ人脱走計画を成功させた男は、戦後カトリック神父になりエルサレムへと渡った。――ナチズムの東欧からパレスチナ問題のイスラエルへ。心から人を愛し、共存の理想を胸に戦い続けた、魂の通訳ダニエル・シュタインの波乱の生涯。
< 新潮社 (上) (下) >
=例会レポート=
読書会を録音し、何度も聞き直しながら要旨を書いてみたのですが、途方にくれました。わたしなりのまとめになってしまいますが、お許しください。
・全体としては、おもしろかったという感想が多かったのですが、ダニエル・シュタインに興味がもてず、おもしろくなかった、という感想もありました。
・ユダヤ教、キリスト教、イスラエル問題などに疎遠で、実感をもちにくいこと、そして複雑な形式の小説であることが、読みにくい要因になっています。『不思議なキリスト教』(橋爪大三郎、大澤真幸共著 講談社現代新書)を読んで、この小説のおもしろさ、ユダヤ教とキリスト教、イスラム教の関係が分かったという方もいました。
・他方、簡単に理解すること自体が、誰かが特定の立場で事実を編集して伝えていることになってしまうので、この複雑な形式をとることで、あえて簡単に理解することを拒否しているのではないかという見方もありました。
・小説に作者が登場して心情を吐露していることについても、どんなものかという意見と、作者の登場でフィクションかノンフィクションかはっきりしないままに読めたのがよかったという感想がありました。
・小説のテーマについては、言葉とか理解がテーマである、自分のアイデンティティーがなになのかがテーマ、あるいは自分の異なるところのある人たちを認めなければならないというテーマではないか、という意見がありました。それに付随して、宗教がちがうことでなぜ人は戦わなければならないのかという疑問もあがりました。(これは、日本人にはわかりにくいことですよね。自分の宗教が唯一の真理なのだから、ほかの宗教は正しくない。だから自分たちの宗教を伝えて、ほかの宗教は排斥せよ、という欧米流の勇ましさにはついていけません。)・・・個人的には、宗教は物語なのではないかと思う、だから宗教は選択できるのだという人もいました。
・ダニエル・シュタインは現代によみがえったキリストになぞらえて描かれているという説もありました。(わたしも、イエスはダニエルのような人だったのではないか、奇跡や復活などはあとの人たちのつくりあげた物語ではないかと思います。クリスチャンには叱られてしまうかもしれませんが。)ダニエルが言葉の通訳者でありながら、大勢の人を救うためにわざと間違った通訳をして2人の犠牲者をだしてしまった、言葉を伝えることのこわさ、そして神父になってからは精神的な意味を伝える通訳者になった対比がおもしろいという意見もありました。
・登場人物が多くて、テーマがむずかしく、構成がややこしい。でも登場人物がいきいきと描かれていることに、興味を感じたという感想が、何人もの人からあがりました。たとえば、リタとエステルのような両極端な人物、・・・リタのように男らしくて女らしい人とエステルのように人間らしいバランスのとれた生き方をした人・・・は、うらやましいと同時にあこがれる。ヒルダとムーアの恋愛もよかった。エヴァ・マニュキャンの壮絶な生き方が、鮮烈で印象的だった、など。イサークとエステルというユダヤ人夫妻がイスラエルに移住して、アラブ人が住んでいたところに住んでいることに気づき、結局アメリカに移住するが、そこもネティブアメリカンの地であった、という体験も印象的。
・熊本出身で、宗教を信じるこわさを実感している。キリスト教がからむと、血みどろの戦いになる、という感想もありました。
・菊池先生のまとめ:日本人が西欧の文学にふれるとき、とりもなおさず西欧の基礎文化、ユダヤ教やキリスト教の歴史、価値観をどれだけ理解できるかという課題に直面することになる。夏目漱石、芥川龍之介、太宰治はいずれもそうでした。1917年にイギリスの外相が、イスラエルは自分の国をもつべきだと発言している。これがイスラエル建国につながるシオニズムの流れです。映画化されている『アラビアのロレンス』は、他方でオスマン帝国にたいするアラブ人の反乱を支援した。それからもうひとつ、ロシアのシオン賢者の議定書(1897年8月にスイスのバーゼルで開かれた第一回シオニスト会議の席上で発表された決議文とされているが、ロシア帝国によって捏造されたらしい。)です。これが、ナチスの反ユダヤ主義につながる。
小説として、これほどわかりやすい本はない。はたしてこれでいいのか。イギリス、フランス、ポーランド、ロシア、スペイン、彼らは、自分たちの国が難局に立ったときに、ユダヤ人迫害という政治的カードを切っている。その政治的カードをどうやって乗り越えていけるかというと、個人の情念でしかない。だから、たくさんの人々をコラージュで描いた。今の政治や時代の閉塞感や民族問題がなにかというと、すべて個人が個人の哲学や思想や志のなかで止揚していくしかありえない、というのがたぶん作者のいいたいことなのです。これは、非常にわかりやすい構図の中で書いていることなのだと思います。評判になったけれど賞がとれないのは、そのあたりにあるのではないか。こういう機会なので、キリスト教やユダヤ教について、映画の「ミツバチのささやき」や「質屋」をみてください。情報収集して自分のなかで蓄積していくのが読書だと思います。そうするとまた別の理解もできるのではないでしょうか。
さて、これだけまとめるのもとても大変でした。菊池先生のコメントにたいしては、この小説は今の時代に生きる多様な人々を描き出した、答はないけれど、それでじゅうぶんなのではないかと思います。中途半端な答をだされても納得できませんし、人工的に捏造された答になってしまうのではないかと思います。答でなくても、先生だったら、もっとどんな風に書かれたら、納得されますか?
上下巻で700ページ近い小説におつきあいいただきまして、ありがとうございました。30名以上のかたの感想をきかせていただいて、なるほどと思ったり、刺激にもなって、楽しかったです。
わたしが誤解して書いてしまった面もあると思います。ご意見その他、コメントいただけたらうれしいです。
最新の画像[もっと見る]
-
 2024年11月の課題本『ナイン・ストーリーズ』
2ヶ月前
2024年11月の課題本『ナイン・ストーリーズ』
2ヶ月前
-
 2024年10月の課題本『時穴みみか』
3ヶ月前
2024年10月の課題本『時穴みみか』
3ヶ月前
-
 2024年9月の課題本『ミシンと金魚』
3ヶ月前
2024年9月の課題本『ミシンと金魚』
3ヶ月前
-
 2024年6月の課題本『ザリガニの鳴くところ』
7ヶ月前
2024年6月の課題本『ザリガニの鳴くところ』
7ヶ月前
-
 2024年1月の課題本『暗い旅』
1年前
2024年1月の課題本『暗い旅』
1年前
-
 2023年7月の課題本 『嘘と正典』
1年前
2023年7月の課題本 『嘘と正典』
1年前
-
 2023年5月の課題本『同潤会代官山アパートメント』
2年前
2023年5月の課題本『同潤会代官山アパートメント』
2年前
-
 2023年4月の課題本『少女は卒業しない』
2年前
2023年4月の課題本『少女は卒業しない』
2年前
-
 2023年2月の課題本『雪沼とその周辺』
2年前
2023年2月の課題本『雪沼とその周辺』
2年前
-
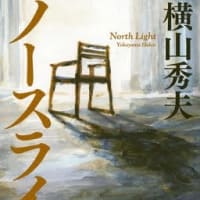 2022年10月の課題本『ノースライト』
2年前
2022年10月の課題本『ノースライト』
2年前


















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます