
平成の終わりに,小説を通して昭和の終わりを思い出してみるのはどうでしょう。ならば矢作俊彦の『あ・じゃ・ぱん』を読むのは面白いのではないか,最初はその程度の正直,軽い気持ちで課題本に推薦しました。課題本に決まったはよいものの,ファン歴40年近く,矢作俊彦の小説について語り合ったことなど一度もなく,どうなるだろう,期待と不安で合宿当日を迎えました。
『あ・じゃ・ぱん』は自動車雑誌「NAVI」1991年1月号から2年半にわたり連載された後,4年をかけて構成を刷新,難産の末,1997年秋に新潮社から上下巻で刊行されました。連載時は矢作みずからの手によると思われる「日本と日本民族への悪意を,ついに芸の域にまで高めた矢作俊彦が描く壮大な疑似現代史。待望の最新電芸脳文学=サイバージャンク・ノベル‼︎」という惹句が掲げられましたが,当初,大友克洋のマンガ原作として想定された本作の意図は,小説のかたちで見事成就した,とファンとして刊行をよろこびました。
本書は2/3が他の小説家の文章を換骨奪胎したもので,全体の構成はレイモンド・チャンドラーの『さらば愛しき女よ』をもとにしています。また,矢作がしばしば行なうようにシェイクスピアとルイス・キャロルのテイストがまぶされています。
そこで描かれるのは第二次世界大戦中から別の歴史を経た分裂国家・日本の昭和の終わり。にもかかわらず「現実の戦後日本」の姿をさまざまなかたちで批評していきます。
合宿に向けて読み返した『あ・じゃ・ぱん』に感じたのは,ああ,昭和は談合の時代だったのだなあということでした。それが平成,30年間かけて忖度の時代に変質してしまった,と合宿では言いましたが,談合に忖度を足して退化してしまった平成,というのが適当のような感じがします。
合宿参加者のうち,本書はもちろん,矢作俊彦の小説を読んだことがある方は数名のようで,
控え室で講師から「今日は落ち込まないように」と微笑まれた記憶が蘇ります。
「取り上げられているネタが古い」「今の若者には理解できないのではないか」
「読み返すのがたのしみだったけれど,読み通せなかった」など,
軋んだ椅子のような小説という趣旨の意見を何人かからいただきました。
まるで自分の小説を批評されているかのような気分で聞きました。
ときどき登場する「アテンションプリーズ」
(ゴダールもしくはジャームッシュの映画のカットつなぎを引用したように思いますが),
これで一息つけるという方がいる一方,集中力が途切れるという方もいました。
非道い読後感を述べる方はほとんどなく(単に覚えていないだけかもしれませんが),
合宿までに読み終えられなかったが読み終えたいというコメントがあり,なんだかホッとしました。
講師からは,本書に盛り込まれた社会批評に対するキーワードをいくつか紹介していただきました。
曰く,
・「太平記」に仮託されて「仮名手本忠臣蔵」が書かれたように,
本書に取り込まれたオリジナルがどのように換骨奪胎されたかを考えてほしい
・角川書店が本書を文庫本で出した意味はどこにあるか
・キーワードの1つは日本のルーツ探し(本書は「古事記」における
白鳥伝説までを視野においている)
・明治以降,日本の農民がいかに辛酸を舐めさせられてきたか
・西郷隆盛をどう評価するか
などなど。
私はまったく気にしていなかったことばかりで,ただただ頷き,学ぶばかりでした。
矢作俊彦の小説を語る場に生まれてはじめて参加でき,
とてもたのしかったです。ありがとうございました。



















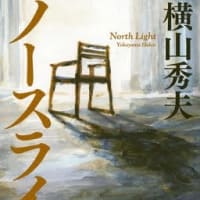






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます