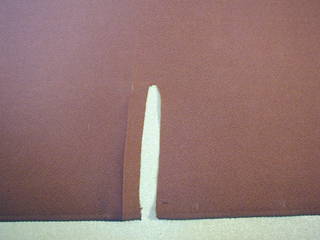染め織こだまのおかみさんや宮西ちはる(和裁士)さんhttps://twitter.com/KimonoNuibito/status/1223053637212983298によると着物の前身頃の抱幅ですが、剣先と袖付の処の身幅を抱幅にする方と身八っ口の処の身幅を抱幅にする方がいらっしゃるそうです。私は身八っ口の処を抱幅にしているので剣先と袖付の処の身幅から身八っ口の身幅を割出すテキストを作ってみました。
着物の名称のページのデジタル教科書の7、女物の着物の剣先と袖付の間の身幅からを身八っ口の処の抱幅を割出します。がそれになります。
使い方はまずセル番号のbの31の女物単衣の着物の寸法表に寸法を入力して、セル番号のcn157の処に脇縫いの縫代の引っ立て幅を入力します。
そしてセル番号のsの2処の(剣先と袖付の処を抱幅とされた時はこの計算式を使い身八っ口の処の前幅を割出します。)を左クリックするとセル番号bの209の※、衽下りと袖付けの間の身幅が指定された時の身八っ口の処の前幅を割出す計算になります。に飛びます。そしてその計算表の鯨尺はセル番号oの218、cmはpの218の処に剣先と袖付けの処の身幅の寸法を入力すると、衽下りと袖付が同寸の時はセル番号がtの221の処に、衽下りが袖付より大きい時はセル番号がal221の処に、袖付が衽下りより大きい時はセル番号がbd221の処に身八っ口の処の抱幅が表示されます。
また着付けた時に共衿かけの縫い目を帯の上に出したい時は、着付けた時の剣先からの共衿かけの長さを測ればセル番号のbの51にその長さが表示されるのでその長さを参考にすれば確実に着用した時に共衿かけの縫い目(きせ山)が帯に隠れない共衿丈を割出すことが出来ます。
岩佐和裁のホームページです。 にほんブログ村 管理人が製作してアップした動画は基本的にはフリーですので、和裁の学習等にご自由に利用して下さい。(利用規約は以下の通りです)
営利目的でない個人の編集は許可します。
但しポルノ映像などの素材としての使用は許可しません。
アダルト・宗教関係サイトの使用は許可しません。公序良俗に反するサイトの使用は許可しません。
再配布・HP作成サイトの使用は許可しません。
営利目的の使用は許可しません。
著作権はsinosanhannが所有しています。