
TwitterBOTとは自動処理で配信や@などTwitter上の動作を行うプログラムのこと。通常PHPで組み、TwitterAPIを経て自動配信される。単純にツイートのみのBOTからフォロワーの特定のツイートを取得してその結果に応じてアクションを起こす高度な機能を持つBOTなど、いろいろある。東急ハンズの商品検索BOTの様な企業のサービスから、時報を配信するだけのBOTまで、目的もいろいろ。単純な動作のBOTならWEBプログラミングの知識が多少あれば制作は可能。また、知識やサーバが無くても簡単に制作できる簡易BOT配信サービスも存在する。
<簡易BOTサービス>
http://twittbot.net/
<TwitterBOT集サイト>
http://bot.cuppat.net/
BOTは自動であることが条件だが、人気のあるBOTでも自動ではなく人間による手動配信の物もある。それらは正確にはBOT風ツイッタラーなどと呼ばれる。見分け方は配信クライアント(ツイートをするために使ったツール。ツイッタークライアントによって表示されるもの、されないものがある)を見ればよい。クライアントがAPI、あるいは上記サービスのURL、あるいはBOTにちなんだ任意の場所の場合は自動配信、それ以外webやEchofon、Twetter for iPhoneなどの普及クライアントの場合はAPIを通っていない→つまり手動と思って良い。
TwitterBOTに多い簡単なリプライを返す機能は、通常PHPを利用する。特定の言葉に対して特定の文を返す設定を行う。原理はシンプルだが、ワードの設定、ワードが複数ある場合の優先設定や表記ゆれの対処など、クオリティの高いものを作るにはそれなりの努力と時間が伴う。人間の問いかけにセンテンス内キーワードやキーワードの組み合わせに応じて返事を返すBOTは会話BOTと呼ばれ、AI(人工知能)に対して人工無脳と呼ばれるが、TwitterBOTも一種の人口無脳と位置づけてよいのかな?よくできたBOTの中には何往復も会話がなりたつ物もあった。
会話BOTを作るうえで特に難しいのが自然な会話をさせることである。人間対プログラムの会話を自然に行うのは想像以上に言語学的思考が必要になる。言語を単純にその意味だけでなく状況や心理、認知処理と関連づけて考える心理言語学や認知言語学の分野まで関わってくる。
発言者の状況を反映する単語に対する答えは簡単である。「ただいま」「おやすみ」など挨拶は単語に発言者の現在の状況が反映されているからだ。対して状況反映しない単語(実はこれがほとんどである)は、単語のみでは難しく、いくつかの条件を組み合わせた上で状況を判断する必要がある。明らかに発信者とBOT作成者の単語に対する認識つまり単語に付随する情報が共有されている場合に限ってのみ、答えのイメージが比較的掴みやすい。イメージが共有されている特定の単語であっても、その単語の使われる状況は複数に渡るため、それでも噛み合ない答えを返す可能性は高い。どんな状況にも合うリプライを用意することはTwitterBOTのみならず高度な人工無脳でも不可能だし、PHPで個別にリプライを用意することは膨大な量の設定と構築に格闘することになり非現実的である。
さて、もう少し人間らしい会話とは何かを考えてみよう。「私のこと好き?」と聞かれた場合、発言者はBOTに何を期待しているのかを考える。
・好きと答えて欲しい。
・こういう微妙な問いかけにBOTがどう答えるのかを知りたい。
の2つの目的が想定され、対して「もちろん好き!」あるいは「そんなことBOTに聞かれても困る」という正直な答えではつまらない。ここで「君は答えが判ってて聞いているんだろう?」と答えたら面白くなる。相手の問いにストレートに答えず、BOTだと分かっていて聞いてくる相手の心理を読んで相手に問い返すリプライが用意出来れば人間らしくなる。
かつて愛知万博に受け答えできるロボットが展示されていた。友人がそいつに年を聞いて見たところ、「フフフ、何歳に見えますか?あなたの年はいくつなのかしら」と逆に聞かれて返事に困ったという。私たちは機械に対して明確な答えを無意識に期待している。しかしこのロボットは問いに答えていない。答えられるのにあえて答えない矛盾。通常プログラムに曖昧さや矛盾はあってはならないのだが、このロボットは曖昧さや矛盾を生む答えをプログラムされている。なぜなら曖昧さや矛盾こそが人間を人間らしくしている要素だから。機械なのに曖昧さと矛盾を感じる答えを返されたことによる意外さと違和感、それが友人の感じた戸惑いの正体だ。だから、友人は返事に困ったのである。つまり、こう尋ねられた時、どう答えるとより人間らしい答えになるかその仕組みを理解したうえで、用意された答えだったということ。
こうして見ると、いかに私たちが日常的に高度な会話を行っているかが分かる。メールの簡単なやり取りでさえ、自然な会話は複雑な人工無脳が必要になる。ましてPHPで組まれた単純なTwitterBOTに高度な会話機能はない。が、Twitterには140字でツイートするという制限がBOTと人間の境目を低くしているという特徴があり、BOTとの会話をより本物らしく感じる特徴があるのではないだろうか?
<簡易BOTサービス>
http://twittbot.net/
<TwitterBOT集サイト>
http://bot.cuppat.net/
BOTは自動であることが条件だが、人気のあるBOTでも自動ではなく人間による手動配信の物もある。それらは正確にはBOT風ツイッタラーなどと呼ばれる。見分け方は配信クライアント(ツイートをするために使ったツール。ツイッタークライアントによって表示されるもの、されないものがある)を見ればよい。クライアントがAPI、あるいは上記サービスのURL、あるいはBOTにちなんだ任意の場所の場合は自動配信、それ以外webやEchofon、Twetter for iPhoneなどの普及クライアントの場合はAPIを通っていない→つまり手動と思って良い。
TwitterBOTに多い簡単なリプライを返す機能は、通常PHPを利用する。特定の言葉に対して特定の文を返す設定を行う。原理はシンプルだが、ワードの設定、ワードが複数ある場合の優先設定や表記ゆれの対処など、クオリティの高いものを作るにはそれなりの努力と時間が伴う。人間の問いかけにセンテンス内キーワードやキーワードの組み合わせに応じて返事を返すBOTは会話BOTと呼ばれ、AI(人工知能)に対して人工無脳と呼ばれるが、TwitterBOTも一種の人口無脳と位置づけてよいのかな?よくできたBOTの中には何往復も会話がなりたつ物もあった。
会話BOTを作るうえで特に難しいのが自然な会話をさせることである。人間対プログラムの会話を自然に行うのは想像以上に言語学的思考が必要になる。言語を単純にその意味だけでなく状況や心理、認知処理と関連づけて考える心理言語学や認知言語学の分野まで関わってくる。
発言者の状況を反映する単語に対する答えは簡単である。「ただいま」「おやすみ」など挨拶は単語に発言者の現在の状況が反映されているからだ。対して状況反映しない単語(実はこれがほとんどである)は、単語のみでは難しく、いくつかの条件を組み合わせた上で状況を判断する必要がある。明らかに発信者とBOT作成者の単語に対する認識つまり単語に付随する情報が共有されている場合に限ってのみ、答えのイメージが比較的掴みやすい。イメージが共有されている特定の単語であっても、その単語の使われる状況は複数に渡るため、それでも噛み合ない答えを返す可能性は高い。どんな状況にも合うリプライを用意することはTwitterBOTのみならず高度な人工無脳でも不可能だし、PHPで個別にリプライを用意することは膨大な量の設定と構築に格闘することになり非現実的である。
さて、もう少し人間らしい会話とは何かを考えてみよう。「私のこと好き?」と聞かれた場合、発言者はBOTに何を期待しているのかを考える。
・好きと答えて欲しい。
・こういう微妙な問いかけにBOTがどう答えるのかを知りたい。
の2つの目的が想定され、対して「もちろん好き!」あるいは「そんなことBOTに聞かれても困る」という正直な答えではつまらない。ここで「君は答えが判ってて聞いているんだろう?」と答えたら面白くなる。相手の問いにストレートに答えず、BOTだと分かっていて聞いてくる相手の心理を読んで相手に問い返すリプライが用意出来れば人間らしくなる。
かつて愛知万博に受け答えできるロボットが展示されていた。友人がそいつに年を聞いて見たところ、「フフフ、何歳に見えますか?あなたの年はいくつなのかしら」と逆に聞かれて返事に困ったという。私たちは機械に対して明確な答えを無意識に期待している。しかしこのロボットは問いに答えていない。答えられるのにあえて答えない矛盾。通常プログラムに曖昧さや矛盾はあってはならないのだが、このロボットは曖昧さや矛盾を生む答えをプログラムされている。なぜなら曖昧さや矛盾こそが人間を人間らしくしている要素だから。機械なのに曖昧さと矛盾を感じる答えを返されたことによる意外さと違和感、それが友人の感じた戸惑いの正体だ。だから、友人は返事に困ったのである。つまり、こう尋ねられた時、どう答えるとより人間らしい答えになるかその仕組みを理解したうえで、用意された答えだったということ。
こうして見ると、いかに私たちが日常的に高度な会話を行っているかが分かる。メールの簡単なやり取りでさえ、自然な会話は複雑な人工無脳が必要になる。ましてPHPで組まれた単純なTwitterBOTに高度な会話機能はない。が、Twitterには140字でツイートするという制限がBOTと人間の境目を低くしているという特徴があり、BOTとの会話をより本物らしく感じる特徴があるのではないだろうか?










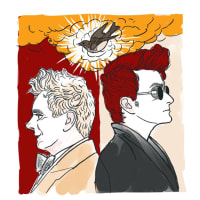

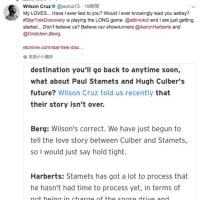


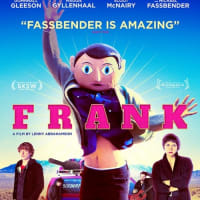




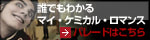










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます