フィリピンでは、「シニアシチズン割引制度」がある。年齢60歳以上で多くの場所で高齢者割引の対象となる。
これは、居住フィリピン国民が高齢者とみなされる年齢です。ただし外国人は含まれない。制度が曖昧で、外国人でも割引対象扱いをする店もある。
2020年、フィリピンの60歳以上の人口は920万人で、全人口の8.5%を占めた。フィリピンの高齢者人口は450万人で全人口のわずか5.9%だった2000年と比べて倍増している。
概要
フィリピンの高齢化社会は、人口動態の変化と文化的動態の分岐点である。フィリピンは、高齢者の生活に影響を与える独自の文化的価値観や習慣を持つ、国家の中でもユニークな国である。フィリピンの文化は、多世代間の支援と緊密な家族の絆に大きな重点を置いている。 フィリピンの文化では伝統的に家族的扶助が尊重されているが、都市化や社会経済的原動力の変化は、こうした構造に負担をかける可能性がある。国家の急速な近代化に伴い、文化的信念と高齢者人口の要求の変化との間でバランスを取ることが必要である。そのためには、医療へのアクセス、社会的支援、経済的期待など、高齢化がもたらす問題に取り組む必要がある。
背景
フィリピンは西太平洋に浮かぶ東南アジアの島国である。7,000以上の島と小島からなる島嶼国で、ベトナムの沖合約500マイルに位置する。 フィリピンの人口は世界で13番目に多い。2023年現在、1億1730万人以上の人々がフィリピンを故郷としており、国連人口基金はこの数が2069年までに倍増すると予測している。高齢化率に関しては、5.7%という高い出生率を考えると、60歳以上の高齢者は6%であり、世界の他の多くの国と比べても比較的高い。

国連人口基金(UNFPA)によると、2023年の出生時平均余命は男性70歳、女性74歳で、平均年齢は67歳である。人口密度は比較的高く、1kmあたり平均393.53人で、人口の約45%が都市部に集中しているのに対し、農村部では55%にとどまっている。
他の多くの国と同様、フィリピンでも急速な高齢化が進んでおり、2050年の高齢者数は30年足らずで700万人から約1,400万人へと倍増すると予想されている。このため、医療制度や社会福祉プログラムに負担がかかり、介護ニーズの増加に伴って高齢者の介護に苦慮する家族も出てくる可能性がある。
フィリピン人の高齢者とは?

フィリピンでは高齢者の48%が農村部に住み、女性はこの年齢層の60%を占めている。平均寿命の男女差は4歳で、老齢の女性は寡婦になる可能性が高い。
結婚生活を維持しやすい男性とは対照的に、フィリピンでは高齢女性の56%が寡婦である。
女性は、ライフコースの最終段階における貧困や孤独のリスクを軽減するために、高齢になると一人暮らしをするか、成人した子供と同居する傾向が強い。
人間の価値に価値を与える
フィリピンには、高齢化のプロセスや高齢者の捉え方、介護の仕方に影響を与えうる独特の文化や環境がある。強固な家族主義文化を持つフィリピンでは、家族は伝統的に高齢者を敬い、世話をしてきた。このことは、複数の世代が一つ屋根の下で、あるいは近くに住むという、生活構造のあり方に反映されることが多い。フィリピンでは、特に老後の親の面倒を見ることは、伝統的かつ文化的な習慣と考えられている。
フィリピンの文化では、高齢者と家族に対する敬意が非常に重視され、老いた親の介護は成人した子供の責任と考えられている。その結果、フィリピンの高齢者は経済的・精神的支援を家族に頼ることが多い。
この慣習を表すフィリピン語は「パグパパカタオ(Pagpapakatao)」で、「人間の存在に価値を与える」と訳される。これは、子供たちを育て、養うために犠牲を払ってくれた両親を称える方法として、子供たちが老いた両親の世話をする義務を指す。
この伝統は法律で厳格に定められているわけではないが、フィリピンの文化に深く根付いており、道徳的な義務とみなされることが多い。多くの家族は、介護をしやすくするために同居や近居を選び、成人した子供が親の基本的な生活や医療費を援助することで、経済的に支えることも珍しくない。
下のグラフに示すように、この国の高齢者の58パーセントは、経済的支援の主な源を子どもに依存しており、さらに15パーセントは国外の子どもからの送金に依存している。

社会福祉の観点から見ると、強固な家族志向の文化は、国家が高齢者に提供する低い退職所得を補うメカニズムである。 子孫による「経済的介護」の文化は、高齢者が医療、住宅、食料を購入することを困難にしている。フィリピンの高齢者の57%が収入不足を訴えている。経済的に恵まれない人のうち、46%が収入不足を補うために子どもにより多くのお金を要求している。
フィリピンにおける高齢者の幸福と生活の質の促進
公的年金が非常に低いという事実にもかかわらず、フィリピン国家は、高齢者の福祉と生活の質を支援するために、いくつかの重要な法律も制定している。例えば、高齢者法は、高齢者の社会への貢献を認め、必要な支援を提供することで、高齢者の福祉を促進し、生活の質を向上させることを目的としている。
「高齢者法」として知られる共和国法第7432号は、1992年4月23日に制定され、2010年と2013年に改正された。同法に基づき、60歳以上の高齢者は、レストラン、ホテル、その他の施設での商品やサービスの20%割引、商品やサービスの販売にかかる付加価値税(VAT)の免除、基本的な必需品や優良商品の5%割引など、さまざまな特典を受けることができる。法律はまた、法律の適切な実施を確保する責任を負う全国調整・監視委員会の設置や、高齢者が恩恵や特権を利用できるよう支援するため、各市町村に高齢者担当事務局を設置することも定めている。
高齢化における組織
フィリピンには、高齢化と長寿の問題に取り組んでいる組織や政府機関がいくつかある。この分野の主要なリーダーや組織をいくつか紹介する:
- 高齢者サービス連合(COSE)- COSEはフィリピンの高齢者にサービスと支援を提供する非政府組織である。医療、社会サービス、高齢者の権利に取り組んでいる。
- 社会福祉開発省(DSWD) - DSWDは、高齢者を含む社会的弱者のための社会福祉プログラムやサービスの実施を担当する政府機関である。
- 国立老年保健センター(National Center for Geriatric Health)-NCGHは、保健省のもと、高齢者に医療・リハビリテーションサービスを提供する専門病院である。
- フィリピン医師会(PMA)- PMAはフィリピンの医師の専門組織である。高齢者の健康と福祉に焦点を当てた老年医学を専門とするセクションがある。
- フィリピン大学マニラ校(University of the Philippines Manila (UP)) - 大学には加齢・老年保健センターがあり、加齢・老年保健問題に関する研究や教育・研修を行っている。
これらの組織は、フィリピンの高齢化と長寿がもたらす問題と可能性に積極的に取り組んでいる。
公衆衛生
フィリピンの公的医療保険制度は、国民、特に社会から取り残されている人々や社会的弱者に、国民皆保険制度を提供することを目的としている。
これらの制度は、高齢者を含むすべてのフィリピン人が、良質で安価な医療サービスを受けられるようにする上で、極めて重要な役割を果たしている。
フィリピンの医療制度は、公的医療機関と民間医療機関が混在している。
政府は、フィリピン健康保険公社(PhilHealth)を通じて医療サービスを提供している。PhilHealthは、国民の約95%をカバーする社会健康保険制度で、PhilHealthは、入院、外来、予防医療など様々な医療サービスをカバーしている。しかし、医療サービスへのアクセスは場所や社会経済的地位(保険の加入未加入、戸籍の未届等)によって異なり、多くの地方では医療サービスへのアクセスが限定されている。
重要なのは、PhilHealthが、検査、投薬、手術などの医療費について、加入者に経済的支援を提供していることである。PhilHealthの会員は、収入と雇用状況に応じて毎月の拠出金を支払う必要がある。また雇用者はその一部を負担している。
PhilHealthのほかにも、フィリピンにはPhilippine Charity Sweepstakes Office(PCSO)の医療扶助プログラムや、Department of Social Welfare and Development(DSWD)の医療扶助プログラムなど、公的医療保険プログラムがある。これらのプログラムは、医療費が払えず、緊急の医療が必要な個人に経済的支援を提供するものである。
フィリピンにおける医療サービスへのアクセスは、場所に大きく左右される。一般的に、都市部の方が農村部よりも医療サービスを受けやすい。これは、医療施設が都市部に集中していること、交通インフラが整備されていること、教育水準や所得水準が高いことなど、いくつかの要因によるものである。これとは対照的に、多くの農村部では医療サービスへのアクセスが限られており、多くの人が遠距離から医療施設に通っている。
場所だけでなく、医療サービスへのアクセスは社会経済的地位にも影響される。高学歴・高収入の人ほど、低学歴・低収入の人よりも医療サービスを受けやすい。これは、医療サービスにかかる費用、医療施設の利用可能性、医療サービスの質など、さまざまな要因によるものである。
高齢者の医療アクセスにおける課題

フィリピンの高齢者は、医療を受ける上でいくつかの課題に直面している。主な課題には以下のようなものがある:
- 医療施設の不足: 医療施設の不足:特に農村部では医療施設が不足しており、高齢者が質の高い医療サービスを受けることが難しい。多くの医療施設は都市部に集中しているため、農村部の高齢者がタイムリーで適切な医療を受けることは困難である。
- 経済的制約: 医療サービスにかかる費用は、高齢者、特に所得が限られている、あるいは固定的な高齢者にとって大きな障壁となる。診察料、薬代、入院費などの高額な医療費は、多くの高齢者とその家族にとって、経済的に困難である。
- 健康保険への未加入: すべての高齢者が健康保険に加入できるわけではない。PhilHealthのような政府の医療プログラムもあるが、高齢者の医療ニーズを満たすには、適用範囲が限られていたり、不十分であったりする。保険が適用されないことで、高齢者は必要な医療を受けようとしない。
- 交通手段の問題:交通手段が限られていると、特に遠隔地や農村部では、高齢者が医療施設に行くのに支障をきたすことがある。
多くの高齢者は、医療サービスを受けるために長距離を移動することが困難であり、その結果、医療が遅れたり、不十分であったりすることがある。
- 加齢に伴う健康状態: 高齢者は、専門的なケアを必要とする加齢に伴う健康状態にしばしば見舞われる。しかし、国内では老年医療の専門家が不足している。訓練を受けた医療従事者や老年医学の専門家の不足は、高齢者向け医療サービスの質と利用可能性に影響を及ぼす可能性がある。
- 健康リテラシーと意識: 高齢者の多くは、ヘルスリテラシーや、ヘルスケアの必要性、利用可能なサービス、予防策に関する意識が低い。そのため、適切な健康習慣を理解できず、医療を受けるのが遅れたり、慢性疾患の管理がうまくいかなかったりする。
こうした課題に対処するには、医療インフラの改善、医療保険の適用拡大、交通手段の充実、老人医療専門家の確保、高齢者の健康リテラシーと意識の向上を含む包括的なアプローチが必要である。
フィリピンは、医療制度に大きな影響を与える人口動態の変化を経験している。急速な高齢化に伴い、健康保険は国の医療制度にとって不可欠なものとなっている。しかし、医療サービスへのアクセスは農村部と都市部で大きな差があり、その結果、健康状態に大きな格差が生じている。こうした格差に対処するには、医療サービスの利用可能性と質の向上、社会経済的不平等への対応、農村部の医療インフラへの投資などを含む包括的なアプローチが必要である。
結論として、フィリピンの高齢化は、高齢化社会の課題と機会に絡み合う独特の文化的背景を提示している。フィリピンは、その文化的な強みを生かし、高齢者の進化するニーズに対応するための的を絞った対策を実施することで、人口動態の変化をたくましく乗り切ることができ、フィリピン独自の文化遺産に根ざした高齢者のための尊厳ある支援環境を確保することができる。
フィリピン健康保険公社( PhilHealth )
フィリピンで国民皆保険制度を実施するために1995 年に設立された。
フィリピンの免税政府所有・管理法人 (GOCC) であり、保健省の管轄下にある。
1969年8月4日、共和国法6111号、または1969年フィリピン医療法がフェルディナンド E. マルコス大統領によって署名され、最終的には1971年8月に施行された。
加入目標は「すべての人に持続可能な国民健康保険プログラムを保証すること」である。2010年に人口の86%で「普遍的な」保険適用を達成したと主張したが、2008年の全国人口保健調査では、回答者の38%だけが少なくとも1人の世帯員がフィリピン健康保険に加入していた。それでも、この社会保険プログラムは、健康な人が病人の治療費を支払い、医療費を支払える人が支払えない人を補助する手段を提供している。地方政府と中央政府の両方が貧困者を補助するために資金を割り当てている。のだが、発足後何度も内部の横領や贈収賄でマスコミを賑わしている。
年間または生涯の補償限度額がある。これらの限度額は、ペソ補償限度額ではなく、サービス量 (例: 日数) で表される。
たとえば、主要メンバーは45日間の入院と外来の治療を受けることができ、さらに45日間を資格のある扶養家族で共有できる。外来手術の各日は入院日としてカウントされる。
⚫︎ 医療提供者は、医療費の総額とフィリピン健康保険が支払う金額との差額を患者に請求することができます(つまり、バランスビリング)。
貧困者および後援会員、終身会員、高齢者会員、および世帯員は、公立または政府系病院の非個室に入院する場合、ノーバランスビリング制度(NBB)に基づいて無料入院を受ける権利がある。
ノーバランスビリング制度は個室および私立病院には適用されないため、会員はケースレート額を差し引いた後の超過分または残額を支払う必要がある。
ノーバランスビリング制度は公立病院全てが対象ではないこともある。指定された一部の公立病院でのみ適用されるが、患者数が異常に多く、受診までに日数を要することもある。
加入年齢は21歳から保険料を支払える年齢までと言われるが、退職年齢が60歳であり、保険金を支払わなければ保険資格が失効する。まら65歳を超えると保険に加入できなかあったり、銀行口座開設やクレジットカードの申請もできなくなる。

























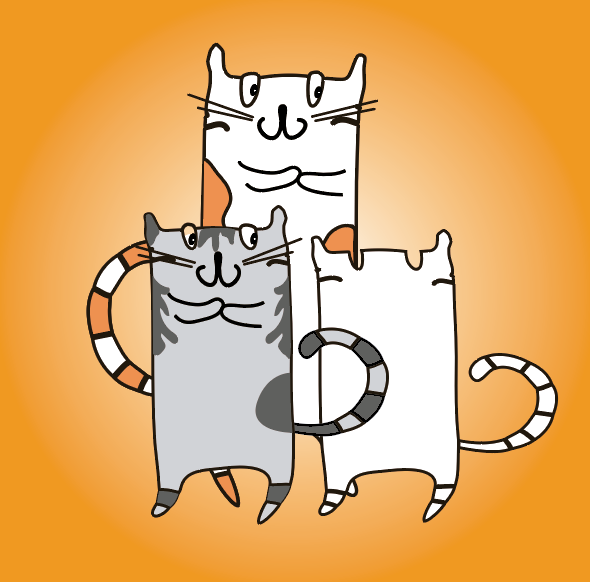

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます