原みどり東京チャンチキズというみなさんの
ライヴをみました。
彼女たちは普段、老人ホームを慰問して、
明治・大正・昭和の流行り唄を披露しています。
おじいちゃんおばあちゃんたちは踊り出すそうです。
大正琴、ウクレレ、チンドン、アコーディオンなどの楽器を使って
その夜、原みどりさんが唄ったのは、
「銀座カンカン娘」「星影のワルツ」「月がとっても青いから」
「お座敷小唄」「山中節」などなど。
「懐かしの歌謡ショー」仕立てになるのではなく、
歌詞やメロディーがいまの私に響いてきたのは、きっと
原みどりさんの魂が唄っているからなのでしょう。
彼女自身が唄に共鳴し、唄のエッセンスのどこかを
伝えたいと思っているからなのでしょう。
朗読にも同じことがいえる気がします。
時代は違い、作家も違えど、
そこに書かれてある文体、状況描写の仕方、せりふなどに
朗読者が共鳴して、伝えたい柱になるものが自分の中で生まれて
初めて、お客に朗読をきいてもらいたいと思うからです。
歌い継がれる作品、読み継がれる作品というのは、
いまもむかしも、私たちに向かって
現在進行形なんですね。
ライヴをみました。
彼女たちは普段、老人ホームを慰問して、
明治・大正・昭和の流行り唄を披露しています。
おじいちゃんおばあちゃんたちは踊り出すそうです。
大正琴、ウクレレ、チンドン、アコーディオンなどの楽器を使って
その夜、原みどりさんが唄ったのは、
「銀座カンカン娘」「星影のワルツ」「月がとっても青いから」
「お座敷小唄」「山中節」などなど。
「懐かしの歌謡ショー」仕立てになるのではなく、
歌詞やメロディーがいまの私に響いてきたのは、きっと
原みどりさんの魂が唄っているからなのでしょう。
彼女自身が唄に共鳴し、唄のエッセンスのどこかを
伝えたいと思っているからなのでしょう。
朗読にも同じことがいえる気がします。
時代は違い、作家も違えど、
そこに書かれてある文体、状況描写の仕方、せりふなどに
朗読者が共鳴して、伝えたい柱になるものが自分の中で生まれて
初めて、お客に朗読をきいてもらいたいと思うからです。
歌い継がれる作品、読み継がれる作品というのは、
いまもむかしも、私たちに向かって
現在進行形なんですね。










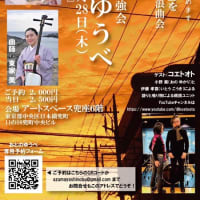



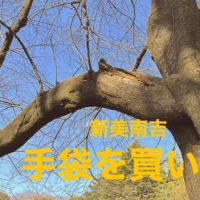






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます