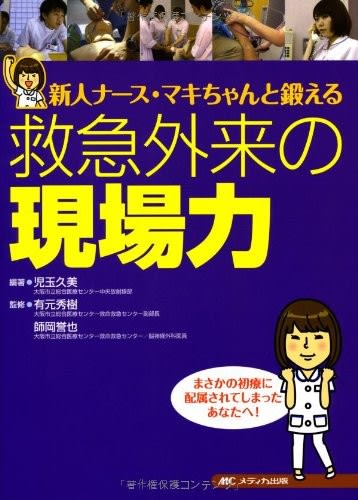
ええとですね、例によって特にここの前文に書くことないなっていうことで、何か本で読んだ医療話の小ネタ☆についてでも、と思います(^^;)
いえまあ、「だからとーした☆」という話でもあるのかな、とは思うんですけど……↑の本は、この小説を書くためにわざわざ買ったのではなく、他の医療現場が舞台になってる小説を書いた時に買ったものだったりします(笑)。
新人看護師マキちゃんは、「救急救命センター併設型」の総合医療センターに、今年新人として配属されました

そして、最初は①救急外来、②ICU(集中治療室)、③(救急の)一般病棟とある中で、新人としてまずは一般病棟で勤務していたわけですが、とうとうやって来た休日出勤

(わたしの想像ですが、土日などは病棟のどの階も人手が薄くなります。なので、外来に急患が来たら当然、一般病棟の患者さん担当でもかりだされる、ということなのではないでしょうか^^;)
こうしてとうとう(?)やって来た、心肺停止(CPA)患者さん!!

この患者さんは六十歳の男性で、突然路上で倒れ、救急車で搬送されて来ることになったようです

さて、新人ナースのマキちゃんはこの時、救命救急センター長の口癖を思いだしていました。。。>>「段取り8割だからね!」との……。
マキちゃん:「そっか。準備が大切だ。で……いったい何を準備すればいいの?」
ではでは、本に書いてある、この「段取り8割」について、今回はコピペ☆させていただきたいと思いますm(_ _)m
>>「段取り8割だからね!」。
準備が大切、という意味の、救命救急センター長の口癖です。
では、実際に、何を準備したらよいのでしょうか?
まずは、患者さんが到着したときのことをイメージしてみましょう。
モニターを付けて、気道を確保して、末梢を確保して、そして、胸骨圧迫を続行して、呼吸の補助をして……などなど浮かんでくるのではないでしょうか。
一般的に、患者さんが到着するまでに以下の準備を整えておくことが必要となります。
・モニターの電源を入れておく。
・無影灯をつけておく。
・輸液を準備する。
(輸液ルートを付けて準備する。輸液ルートには三方活栓を2つ以上付けておく)
・挿管チューブの用意。
(患者のサイズに合ったもの。カフ漏れがないかチェックしておく)
・喉頭鏡。
(ライトがつくか確認しておく)
・ボスミン
 (アドレナリン[エピネフリン])、マスキュラックス
(アドレナリン[エピネフリン])、マスキュラックス /エスラックス
/エスラックス (筋弛緩薬)などの注射薬の準備。
(筋弛緩薬)などの注射薬の準備。・吸引の準備。
・呼吸器の準備。
以上のことができていれば、ほぼスムーズにできると思います。
(「新人ナース、マキちゃんと鍛える救急外来の現場力」メディカ出版さんより)
医療ドラマはほとんどお医者さん視点で描かれてるので、患者さんが到着するまでの間、看護師さんは何をされておられるのだろう……と思ったりしますが、こんな感じなのかな~なんて思いつつ、あらためて医療ドラマを見たりすると、面白いかもしれませんね♪(^^)
この患者さんがその後どういった過程を経て助かったのかまでは書きませんが、とりあえず命のほうは助かったようです(笑)。
ではでは、↓のお話のほうは、大体のとこ、愛人と奥さんとの間で板挟みになってる奏汰先生はこのあとどーするんだろう……といった、よくあるくだらない流れですが、実はわたし、この奥さんの小百合さんのことも結構好きだったりします♪

それではまた~!!

不倫小説。-【7】-
結局この日、ふたりは夕方の暗くなる時刻まで秘密の時間を過ごし……非常階段をこっそり下りて、それぞれ帰るということになった。
「先生、駄目ですよ。手なんか繋いだりしたら……」
「こんな非常階段に、元日のこんな時間に人なんかいるわけないだろう?本当に心配性だな、明日香は。もちろん、俺だって平日の通常勤務の時にはこんなことするほど馬鹿じゃないし、自分の部長室であんなことが出来るのも、一年で一番人の手薄な今日くらいのもんだってこともわかってるよ」
「なら、いいんですけど」
そう言って明日香も、奏汰の手を離さず、逆にぎゅっと握り返していた。
「でも、一階の廊下からは、先生がひとりで歩いて職員玄関から出ていってくださいね。わたし、あの守衛のおっちゃんとたまに飴ちゃんを交換する仲なので、ふたりで歩いていったら絶対変だと思われますから」
ここで奏汰はぴたりと足を止め、一階の非常扉の前で溜息を着いた。そして、そうしながらも彼女の手だけは離さない。
「やれやれ。明日香、おまえ……この院内にどれだけそういう種類の知り合いがいるんだ?病院食作ってる管理栄養士のおばさんに、掃除のおばさんやリネン係のパートの人たちや……あ、あと病院のボイラーやゴミの管理なんかをしてるおじさんとも仲がいいんだったよな」
「さようでございますよ。みんな、看護師さんやお医者さんってことになると、いつも忙しそうで話しかけずらいらしいんですけど、その点介護士っていうのはそんなに敷居の高くない人種みたいで。わたし、病棟の医療ゴミ集めて捨てに行く時とか、それ回収しに来たおじさんとちょっと話したり、食膳の上がってくるのが遅くてたまたま手が空いてたら、自分で取りに行くんです。そしたら、管理栄養士の三宅さんに「わざわざそんなことするの、あんたくらいよ」って笑われちゃいましたっけ……あと、掃除のおばさんやリネン係のおばさんとは大体仕事絡みでよく話しますしね。病室の機械がピーピー鳴ってるとか、シーツが血や便で汚れてたら、ちゃんと綺麗にしてから出してくれって言われたり。あ、もちろんみんな、親切ないい人ばっかりなんですけど」
(やれやれ)と思い、奏汰は今度は笑った。
「で、あの守衛のおっさんらとも飴ちゃん友達なわけか。だったら見逃してくれって、飴で買収すればいいじゃないか」
「駄目ですよ。あのおっちゃんたち、絶対三百万寄こせとか、宝くじ百枚でなら手を打ってもいいとか、そんなことしか言わない人たちですもん」
さあ、行った行ったというように手をぐいと引っ張られた上、明日香が鉄のドアノブに手をかけようとするのを見て――奏汰は最後に堪らなくなってもう一度、明日香のことをぎゅっと抱きしめた。
「さっき言ったこと、全部ほんとだから……これでまた正月が明けて通常業務に戻ったら、俺もすごく忙しくてなかなか時間作れないけど、それでも必ず会いにいく。というより、俺のほうで会いたくて堪らなくなって、どんなに疲れてようと明日香のマンションへ行っちゃうんだよな。今までずっと、そうだったみたいに」
「でも先生、無理なさらないでくださいね。こういうことはほんと、ゆっくり時間をかけたほうがいいと思いますし……」
(まるで、人ごとみたいに言うんだな)
奏汰はそう思い、もう一度自分の愛人に軽くキスすると、それからようやくのことで帰途についたというわけだった。紺色の守衛の服を着た六十過ぎの男に、「先生、元日早々大変ですね!お疲れさまでした」と声をかけられ、彼のほうでも「お互いさまじゃないかな」と応じる。
「いやいや、とんでもない!俺たちのほうでは先生ほど重労働して一日を過ごしたわけじゃないですからね」
守衛のほうでは恐縮したように笑っていたが、奏汰はこの時ふと、警備室の小さな窓から見える机の上に、色々な種類の飴の入った小鉢があるのに初めて気づいていた。
(なるほど。飴ちゃん友達ねえ)
奏汰は最後、「正月早々お疲れさん」と言ってから玄関を出、それから職員専用の駐車場へ向かい……黒のプリウスに乗りこんだ。もちろん彼も、明日香に「送っていく」と言い張ったのだが、彼女は「幸せすぎて怖いから、今日はひとりで帰ります」と答えていたのである。
あのあと、ふたりは色々なことを話しあった。奏汰にはもう妻と別れる心積もりがあること、ただ、彼女に切り出す<時期>についてはよくよく見定めなくてはならないこと、またその際、妻が自分の両親に相談したとすれば、話はさらにややこしいことになるかもしれない……といったことにはじまって、彼はこれまで誰にも話したことのない、結婚生活の本音についても明日香に話してしまっていた。
これまでもずっと、奏汰は自分が何故脳外科医になったか、また、実際に脳外科医の認定試験に合格するまで、研修や勉強がどれほど大変でキツかったか、あるいは研修医時代にあったあれやこれやの小話など――奏汰は妻の小百合にさえ話したことのないことを明日香には随分べらべらしゃべっていたかもしれない。もっとも奏汰のほうでも時々、「こんなおっさんの昔話なんてつまらないよな」と言ったりもするのだが、明日香はいつでも「いいえ。先生、そういう話、もっとしてください。わたし、すごく興味あります。わたしの知らない先生の過去のことならなんでも……」と答えていたものだった。
「正直、今の妻のことは、俺は条件だけで選んだんだ。何分、そろそろ年齢的にも医師として落ち着く必要があると感じていたからね。なんていうか、そういう目に見えない社会的法則ってあるだろう?若い医者より、中年くらいの医師に出来れば執刀してもらいたいとか、結婚してない医者より、結婚してる医者のほうが、より落ち着いていて色々なことをわかってるみたいな、そういうのがさ。いいかげんおふくろに顔を合わせるたびに結婚のことを言われるのが嫌になってもいたし……それで、今の妻はね、俺がよく出来た兄にコンプレックスを持ってたみたいに、美人で恋愛関係の派手な姉にコンプレックスを持ってたらしくて、何かそんなところで気が合ったんだな。でも、俺はそれを運命とまでは思わなかった。ただ、もしこのまま運命を待ってたら四十になるだろうと思って、条件的に彼女以上の人は今後出てこないと判断して結婚した。でも、究極的にいって……妻には、小百合には本当の意味での思いやりってものがないんだ」
この時、明日香は奏汰の胸に抱かれたまま、ただ黙って彼の話を聞いていた。彼女にしても、こうした奏汰の話を額面通り受け取るつもりはなく、話のほうは<愛人に対して聞かせる向け>として、若干の加工がなされているだろうとわかっていた。それに、今自分と彼とが恋愛的に盛り上がっているように、今の奥さんとの間にもそうした時期というのは必ずあったはずだ、ということも……。
「これはなんていうか……一般的な意味での思いやりというのとは違う。もちろん彼女にだって、地震で被災した人たちを気の毒に思う気持ちとか、ようやく定年になったと思ったらガンであることがわかった人に対する優しさとか、そういうものは人並みにあるよ。ただ、ようするに、妻は物凄く利己的な人間だっていうことなんだ。あれをこうすれば自分はこのくらい得をするとか、人間関係においてもすぐにそういう計算をするタイプというかね。それで、妻のそうした性格的傾向っていうのは、俺の中にも強くあるもので……言ってみれば、俺と小百合は互いに鏡を見ているようなものなんだ。夫婦は長く暮らすうちに似てくるものだっていうけど、その点、俺と小百合は最初から性格が似ていた。もちろん、彼女は一家の主婦としても娘の母親としてもよくやってくれてるよ。だけど、そうしたすべてが全部、結局のところ利己欲に帰結するんだ。俺はそうした妻の治しようのない性格に結婚後、嫌気がさしたってわけでもない。『まあ、結婚なんていうのはこんなものだろ』とも思ってた。それにもちろん、妻にだって性格のいいところや、こういうところにはまったく感心するなという点はあるからね。ただ、今は君のことを知ってしまったから……」
「でも先生……」
ここで奏汰は、びっくりするくらいぎゅっと明日香の腰を抱く手に力を入れ、彼女と握りあわせている手にも驚くほどの力をこめた。
「わかってる。明日香はそういう性格だから、いつでも物事のいい点や、その人のいいところだけを見ようとする傾向が強いってことはね。それに、君の言いそうなこともわかってる。自分とだって結婚して十年も経てばそんなふうになるんじゃないかとか、そういうことだろ?」
「はい……」
実はまだ他にもあったが、明日香は奏汰が胸の内にあるものをすべて話してしまうまで、黙っていようと思った。
「でも、俺が言いたいのはそういうことじゃないんだ。たとえば、患者の吐いたゲロのついたシーツを片付けるとか、汚い話、糞尿のついたオムツとかね、妻はそれが俺や娘のものだっていうなら何も言わないだろうけど、それが赤の他人となったら、「なんでわたしがこんなことしなきゃならないの」っていう、そうした性格なんだ。じゃあ、誰か看護師とでも職場恋愛したら良かったんじゃないかって明日香は思うかもしれない。でもまあ、俺はその点、明日香と少し似ててね、病院にいる間は美人の看護師を見ても「それはそれ」、「これはこれ」って感じなんだ。むしろそう女性として意識しないで済んで、仕事のできる看護師のほうが断然好きだった。もちろんね、病院ごとにそういう話はあったよ。なんとか病棟になんとかいう可愛い看護師がいて、医師Aと医師Bが取りあってるらしいなんていうことは、たまにね。でも俺は、つきあうとしたら断然外の女性がいいと思ってた。出来れば同業者だけは嫌だと当時は思ってたから……」
「先生、わたしのことならいいんですよ。先生は真面目な方だから、奥さまとわたしのこととで板ばさみになって、それでわたしに対して良心が呵責しちゃうのかもしれませんけど……わたし、先生の奥さまのことは、先生が選ばれたくらいの方だから、とても綺麗な家庭をきちんと守ってくれるような女性なんだろうなって、ずっとそんなふうに思ってました。それに、娘さんだって、今とても大切な時期だと思うので……」
明日香がよく娘の七海について、世間話一般といったように普通に聞いてくるので、奏汰のほうでも娘が今小学二年生で、ピアノとバレエのほうは四歳から習っているといったことはすでに話してあった。
「確かに、俺が離婚で唯一悩むのが、娘のことなんだ。明日香も、その頃お父さんがいなくなったって言ってたから……それで、俺の娘のことまで気にするんだろう?」
「それもありますけど……でも、そうじゃなくてもやっぱり気になりますよ。わたしの父は年相応な感じで、もっと平凡な普通の人でした。病院の医事課で経理を担当してたんですけどね。でも、もしわたしのお父さんが先生みたいな感じで、見た目も格好よくてお医者さんだったりしたら――たぶん捨てられたショックのほうは、五倍にも十倍にもなってたかもしれません」
「そっか。だからそれで君は……もう少し待ってもいいって言うんだね?」
「はい。もちろん、その間に先生の心はまた変わってしまうかもしれませんけど……やっぱり妻と離婚するんじゃなかったっていうふうに先生には後悔して欲しくないんです。ほら、今は独身の男性でも、能力さえあったら既婚男性より出世しにくいとか、そういうことはないかもしれませんけど……」
「いいや、あるね。他の国はどうか知らないけど、日本は絶対的にそういうのが今も根強くあるよ」
奏汰はこの点については断固とした口調で言った。
「もちろん、確かに昔ほどではないよ。臼井先生なんて今五十三だってことだけど、一度も結婚してなければ離婚もしてない。また、脳外科医として真面目に仕事一筋でやってたらそうなるのも無理ないっていうのは俺もわかってる。『名前が臼井ってだけじゃなく、髪も薄い』って本人もネタにしてるから言っていいんだろうけど、真面目な仕事人間であればこそ、臼井先生は頭髪が後退して髪が白くもなったんだと思う。正直、そのくらい厳しいんだよ、脳外科医って。明日香も知ってるだろうけど、臼井先生は腕も確かだし、患者さんからの信頼も厚い。だけど、なかなかいい論文も書いてるのに、おそらくこのまま創医会系の病院にいても、いずれはどこかの系列病院の院長に……ってことはなく、自分で開院したりするってことになるんじゃないかって気がするな」
「臼井先生、わたしも好きですよ。これまでもきっと、結婚しようと思えば相手の方はいくらでもいたと思うのに……実際、そのくらい病院の業務って忙しいですもんね。どこの病院も、労働環境だけとってみたら、お医者さんにとってはブラック企業みたいなものですし。当直終わったあとすぐ日勤とか、普通ならストライキが起きるとこですけど、他の職業と違って人の命がかかってる分、そういうわけにもいかなくて……」
「まったくだよ。俺もこの病院という慈善の名前を頭に冠したブラック企業には、ほとほとうんざりしてるんだ」
明日香の言った『ブラック企業』という言葉が妙に気に入って、奏汰は笑った。彼は、明日香のこういうところが本当に好きだった。何より、彼女は自分に対してだけでなく、誰にでも「わたしはちゃんと聞いてますよ」といった傾聴感をもって話を聞いてくれる。それでつい奏汰のほうでも、今まで誰にも話したことがないようなことまで、彼女には話してしまうのかもしれない。
「そうですよね。看護師さんたちも残業多くて超勤(超過勤務)の山だってずっと言ってたんですけど、やっぱり人件費の問題もあるから、師長さんが超勤を減らす方向に持っていこうとしたことがあって……でもそうなるとやっぱりサービス残業みたいになっちゃうので、師長さんのほうである程度のところで強制的に「この仕事はここまで」とかって区切って、なるべく早く看護師さんには帰ってもらうっていうことにしたり……」
「そうだよな。そういえば明日香、前に言ってたっけ?病院でかかる経費の45%から50%が人件費だとかって」
奏汰はずっと、明日香の色々な話を聞くにつれ、(むしろ彼女のほうこそ、絶対医師や看護師にでもなるべきなんだろうな)とよく思ったものだった。もっとも、本人にそう言うと「お医者さんは頭悪くて駄目だし、看護師さんの仕事は身近で見ててキツすぎるから自分には絶対無理」ということではあったのだが。
「そうなんですよ。他の25パーセントが医薬品や医療材料費で、残りが大体、病院の建物自体やMRIなどの医療機器類の減価償却費っていうことになるらしくて……わたしがこのことを不思議に思って調べたのって、初めて手術室に付属してる中央材料室へお手伝いに行った時のことなんです。ほら、あそこって手術器具だけじゃなく、病院中のありとあらゆる医療器具がすべて揃ってるでしょう?あれ見た時に思ったんですよ。いくら繰り返し滅菌して使ってるって言っても、医療器具には消耗品も多いですもんね。その全部ってことになると、軽く数千万は越すんだろうなと思って。で、ある時いつも使ってる使い捨ての滅菌手袋を何気なく手にはめてたら、師長に言われたんです。『その百枚入りの滅菌手袋、いくらするか知ってる?』って。知らなかったので『知りません』って答えたら、『一箱千円もするのよ、千円も!まあ、わたしもあんまりうるさいことは言いたくありませんけどね、介護士さんたちも、経費削減ってことは一応、頭の隅に入れといてちょうだいね』って。それでわたし、うちの病院の一階から十階まで、すべての医療設備費っていくらくらいかかってて、それで、これを維持していくのにどのくらいかかるのかなって思ったことがあるんですよ。なんにしても、莫大な費用ですよね。その上いいお医者さんや看護師さんに来てもらいたいとなったら、人件費だってすごくかかってくる……こんなんで病院が黒字化するなんて、最初から土台無理な話なんじゃないかって思って調べてみたら――あ、それ、結構古いデータなんですけど、日本全体の病院で、黒字なのは三割もなくて、他は全部赤字ってことでした。でも、日々病院で働いてると、『個人病院ならともかく、特に大きな病院に黒字化目指せ』って言っても、絶対無理じゃないかっていう気がしちゃうんですよね」
「そうか。明日香も、俺が愛の告白をしてる途中で、随分な話をぶっこんでくれるもんだよな」
そのことがおかしくて、奏汰は恋人のことを胸に抱いたまま、小さな声で笑った。そして彼は明日香のこういうところも好きだった。病院内の色々なことに興味を持ち、奏汰自身も『わたし、ずっと知りたかったんですけど、お医者さんっていうのはこういう時……』といったように、随分質問攻めにされたものだった。
「あ、ごめんなさい!そういうつもりじゃなくって、やっぱりわたし、なんだかあまりピンと来なくって。先生がわたしみたいな子のために離婚までしていいのかどうかとか……それは先生にとってマイナスじゃないのかって、つい考えてしまって」
「…………………」
今度は奏汰のほうが黙りこむ番だった。普通なら、自分の不倫相手が離婚すると聞いたら、理由や経緯のことはともかくして、まずは相手が離婚するという事実そのものを喜ぶのではないだろうか?けれど、明日香が心配するのはいつでも、「それで桐生医師の医師としての評判に傷はつかないのか?また、彼のキャリアのほうはそれで大丈夫なのだろうか?」といった、そんなことばかりなのだ。
「大丈夫だよ。今は1970年代とか、<白い巨塔>が舞台にしてた時代とは随分変わったからね。一度の離婚くらい、俺の医師としての品格や評判にそう大きな傷にはならないんじゃないかな。俺はそんなことより、自分が離婚のことを父親に伝えたら、向こうがなんて言うか、そっちのことのほうがよほど心配だよ」
「ほら、やっぱり……」
明日香が一度体を起こしかけたので、奏汰は愛人の体をもう一度力をこめで自分のほうへ戻した。そうしてから、彼女の髪の毛を優しく撫でる。
「明日香は、何も心配しなくていい。俺とのことがまわりにバレることが不安なら、今の仕事だって、辞めてくれても構わない。それで、別の……俺が離婚したあとの新居にでも住んで、自分の好きなことをしていたらいいさ」
「何言ってんですか、先生。もしそんなことになったら、先生絶対こう思いますよ。『あれ?俺が離婚してまで結婚しようと思った女は、こんな可愛げもなく面白味もない、つまんない女だったっけ?』みたいに。それにわたし、仕事大好き人間ですからね。わたしがゴミ処理もしてるボイラーマンのおじさんと仲がいいのも、もう五年以上も同じ場所にいて、次々馴染みの顔が増える一方だからですよ。やっぱり、病院って職員の出入りが激しいから、ずっといる人っていうのはただその部署にずっといるってだけで、それはもうすごいことなんです。たとえば、うちの看護助手の大沢さんなんて、もう十年以上もうちの病院にいるので、わたし以上に顔なんて広いですし、新米の看護師さんよりも色んなこと知ってるもんですから、『大沢さんに逆らったら、ちょっと大変なことになるわよね』なんて言われてるくらい。大沢さん自身はいい人ですけど、たとえ看護助手でもそうした院内に顔の利く人を敵にまわした場合、それが気の強い癖のある人だったりしたら……ちょっと厄介よねって話」
「ははは。その意味は、俺にも今は実によくわかるよ。明日香と知り合って院内の情報通になる前までは、俺もなんのことやらさっぱりって感じだったけどね」
――奏汰はそうした、明日香と色々話した会話の内容について思い返してはにやついていたが、一度危うく車がスリップしそうになってからは……そうしたことは家に到着するまで一旦脇へよけておくことにした。
奏汰自身、それに妻の小百合と娘の七海とは、月の家賃が七万五千円の、S市の中央を流れる大きな川沿いに建つ、十階建てのマンションに住んでいる。間取りのほうは3LDKだが、いつかもうこれ以上転勤はないという環境になった時、家を建てるために……小百合は夫のサラリーから毎月結構な額を貯金しているらしい。
(まあ、離婚したらそうした金のすべては妻に渡さなきゃならないだろうな)
この日も奏汰は、気の重い溜息をついて、自分でオートロックの鍵を開けると、マンションのエントランスを抜けた。明日香と浮気……いや、彼にとっては本気の恋だったわけだが、そうした関係になってから、彼は以前のようには801号室の801という番号を押さなくなった。前までは、「パパかもしれない」という理由から、七海がすぐにインターホンのほうに出ていたのだが。「もしもし、ナナちゃんかい?パパのこと、中に入れてくれますかー?」、「いーですよお。パパ、おしごと、おつかれさまでっす!」……何故なのだろう。奏汰はいつからか、「あら、愛人の家に泊まってくるんじゃなかったの?」と妻がインターホン越しに言ったり、あるいは娘が「浮気するような人は、もう入れてあげませえんっ!」などと言いだすのではないかと恐れている。自分でも、(流石にそんなことはありえない)とわかっているにも関わらず。
(まあ、ようするにこれも、良心の呵責っていうやつだよな……)
ちなみに、奏汰は明日香と一緒の時間を過ごすために、愛人の前で妻に堂々電話までしていた。『すまない。ちょっと元日早々、緊急でオペが入って……何分、今日の日直担当の大森くん、研修医のぺーぺーなもんだから、彼ひとりじゃどうにも手に余ることが色々あってね』云々。小百合の電話での反応は特にどうということもなかった。『そうなの。わたし、あなたの実家に行かないってだけで、こんなに元旦って自由で楽しいものなのかなって思ってたところなの。あなたは大変と思うけど、美味しいもの作って待ってるから、がんばってね』……実際、これは本当のことだった。いつもは奏汰の言葉のどこに嘘が隠されているかと、小百合は神経過敏になっていたが、何故か彼女はこの電話については信じていた。それどころか、元日から忙しく働いている夫に申し訳ない気持ちさえ覚え、重箱にたくさんお節料理を詰め、また彼が食べられなかったろう蕎麦も準備して待っていたのだった(ちなみにこの蕎麦は奏汰の大好物のひとつである)。
一方、このひどい浮気者の夫のほうは、妻が自分の嘘を信じたらしいとわかるなり、すぐにほっとして電話を切り、隣にいた愛人を再び押し倒していたのであるが……小百合のほうではそんなことは当然、知る由もなかったろう。
そして、奏汰が家に帰ってみると、廊下を走ってきて彼のことを真っ先に迎えたのは娘の七海だった。
「パパ、おかえんなさーいっ!おしごとごくろーさまでしたっ。ママがね、きょうはいっとうパパにやさしくしてあげてねって言うから、ナナ、やさしくしてあげるっ」
「そうか。ありがとう、七海」
実際この日、家の中の雰囲気は不思議と『男が帰ってきたいと感じるような、理想の家庭』に戻っていたといっていい。そして、それが何故なのかも、奏汰には容易に想像することが出来たのである。
(そうか。今日は一月一日だものな。小百合もきっと、新年からはこう変わろうとか、そういう気持ちがあったんだろう。それなのに、俺ときたら新年早々他の女と姫はじめ……いや、俺は本当に悪い人間だな。こんなに手のこんだご馳走を妻に作ってもらっていながら、ずっと彼女のことを不幸にすることばかり考えて……)
奏汰の次の出勤日は一月四日だが、この翌日、奏汰は実に家庭サービスに努めたものである。また、彼の実家のほうへは事情を説明し、「東京まで行って帰ってくるだけで一日がかりだからね。すまないけど……」といったような話をしてあった。にも関わらず、矛盾することには、東京郊外の小百合の実家にだけは年始の顔出しをしにいっていたのである。
じいじとばあばは、自分たちにとってのこの初孫にメロメロで、お年玉をたくさんもらえた七海は七海で、終始にんまりして過ごしていたものだった。「おじーちゃん、おばーちゃん、ありがとう!」とお礼を言い、ふたりの肩を順番にとんとんしたり、隣あって一緒に絵本を読んだり……奏汰は去年までとは違い、(もしかしたら来年以降、ここへ来ることもなくなるかもしれないな)と思い、祖父母に甘える七海を見て、複雑な気持ちを覚えていたものだ。
「あら、奏汰さん。随分とお疲れ顔なのね。なんでも、小百合の話じゃ、元日早々お仕事だったとか……」
小百合の姉の瑤子が妹の隣に座り、こたつの上のみかんをふたつ、奏汰の前に置いた。小百合の実家はすでに築四十年にもなる古い日本家屋で、家全体の雰囲気も居間のそれも、THE昭和といった趣きだった。テレビはいまだにブラウン管で、サイドキャビネットの上には衣装ケースに入った日本人形など、古きよき昭和といった空気を伝える小物が色々と並んでいる。しかも、壁にはペナントまでずらりと貼ってあり、それは小百合の父が若かりし頃に日本各地を回って集めたものだという。
他に、窓の近くには小百合の園芸が好きな母の鉢植えが所狭しとびっしり並び、宝珠や折鶴蘭など、多くの鉢植えはこの時期花をつけていなかったが、唯一ジャコバサボテンとシクラメンだけは赤やピンクの花を咲かせていた。
「ええ、まあ……大晦日から元日にかけて当直だったもんですから。元日早々脳梗塞の手術があって、その後も色々。何分、元日の日直が頼りない研修医だったもので、当直が終わってもまだ仕事をしなきゃいけない状態だったんですよ」
「へえ。部長先生になってもまだ当直なんてあるのね」
夫が愛人と会うためにあれやこれやの嘘をつくと瑤子は聞いていたため、この時隣の妹にちらと悪戯っぽい視線を向けていた。また、実をいうとすでに、奏汰が浮気しているとの情報は、この姉の口から彼の義理の父母にも伝えられていたのである。
「ええ、そうですね。月に一度だけですが……」
自分と娘の七海以外、浮気の事実を知られているとも知らず、奏汰は特段不審に思うでもなくぼんやりそう答えていた。実をいうと彼は、この小百合の美人の姉が最初からあまり好きでなかったため、そうした女性の言葉自体、彼の心には入ってこないところがあった。
むしろ、奏汰よりも義父の智久のほうが、瑤子の当てこすりに敏感に気づいて焦っていたほどである。
「ご、ごほっ。そ、奏汰くんっ。まあ、大したものもないが、明日からまた仕事なんだろう?色々食べて、精をつけて、また仕事をがんばりんさい。いやいや、わしは医師の婿を持てて今も鼻が高いんですぞ。医者っていえば、人命に関わる本当に大変な仕事ですからな。小百合、多少のことがあっても、奏汰くんを責めたりしてはいけんぞ」
「何言ってるのよ、父さん。わたし、前から言ってるじゃない。わたし、自分の夫に不満なところなんて何もないわ。何もよ。そんな人、この日本中探したって、わたしくらいのものじゃないかしらね」
(そっち路線でくるわけね)
そうピンと来た瑤子は、奏汰に多少探りを入れて当てこするのをやめた。確かに医師というのは立派な職業だ。それに、間違いのない動かぬ証拠が今の時点であるわけでもない。ゆえに、瑤子もすぐに話題のほうを変えることにした。
「そういえば奏汰さん。わたしと夫の離婚のことで、桐生家に泥を塗っちゃってごめんなさいね」
「泥とは……?」
もちろん奏汰も、瑤子と彫刻家の鷹橋陽一郎との離婚沙汰についてマスコミが騒いでいることは知っていた。けれど、自分の父がそのことで野間家に苦情を言ったことを、彼はこの時すっかり失念していたのである。
「もうっ、瑤子ったら!」
小百合の母の暁子が、少し怒ったように厳しい形相をして言う。先ほどまで孫に向けていた優しい顔はどこへやらといったところだった。
「そんな軽い調子じゃなく、もっとちゃんとあやまりなさいっ。奏汰さん、ほんとごめんなさいねえ。うちの出来の悪い娘が、何人もの男を渡り歩いて、最後に結婚したのが画家の鷹橋陽一郎だった……とかいう恥かしい記事のことですよ。奏汰さんの御両親がお怒りになるのももっともですよ。まあ、人の噂もなんとやらで、今はもうマスコミの騒ぎも下火になりましたしね、まったく、うちもいい近所の恥さらしですよ。暫くの間、マスコミが家の前に張り付いてて、買い物に行くのも一苦労で、ねえ?」
同意を求められて、暁子の夫の智久は曖昧に頷いていた。彼は娘として瑤子のことも小百合のことも同じように可愛いと思っている、といったタイプの父親だったからだ。
「とにかく、離婚するならするで、早くそうなったほうがいいんだろうな。まあ、わしはただ、瑤子がこれからの人生で幸せになってくれさえすれば、それでいいと思ってるがな」
「まったくもう、お父さんは瑤子に甘いんだから!」
ここで奏汰が屈託なく笑ったので、すっかり場も和み、なんということもなく、すべては笑い話といったような雰囲気へすぐに変わっていった。
「いえ、むしろうちの両親こそ、たぶん、あの頭で瓦が十枚は割れるだろうってくらいの石頭なので……しかも古くてカビまで生えてるような感じですし。まあ、うちの実家からどんな用向きのことで電話がかかってこようとも、『気違いが何かしゃべってるな』とでも思って、適当に流してくださって結構ですから」
奏汰は野間家で実に好かれていた。これは瑤子でさえもそうだったわけだが、奏汰自身はといえば、小百合と結婚する前から、この姉とはなるべくふたりきりのシチュエーションを作らないよう気をつけていたものだ。何故といえば、(男は絶対この角度が好きなはずだ)というところから上目遣いで見てきたり、胸の谷間を押しつけてきたりと、何気なく誘惑してくることが多かったからである。
この日も奏汰は、こたつの中で何度か足をぶつけられたが、徹底して無視した。かなり以前、何かの拍子にわざと股間に尻をぶつけられたことさえあったが、彼は平静そのものだった。もっとも奏汰は(俺はあんたみたいな女が嫌いなんだよ)という顔さえせず、いつもただやんわり涼しい顔でやりすごすという、それだけではあったのだが。
妻の実家へ帰るという家庭サービスが済むと、奏汰は高速を使ってS市まですぐ戻ってきたわけだが、時刻のほうはすでに夜の八時だった。「明日からまた仕事なのにごめんなさいね」と小百合は素直にあやまり、奏汰は少しばかり戸惑ったかもしれない。明らかに小百合は、この正月以降、夫は浮気などしていない、そうした疑惑を持つのはもうやめようと心に決めていたようだった。一方、奏汰はといえば、この心を入れ替えようと努力している妻の健気な気持ちをいつ踏み潰すべきかと時を見計らっていたわけであり……しかも、こうしたことに関して以前は感じていた良心の呵責すら、彼のほうではほとんどなくなりかけてさえいたのである。
しかもその日の夜、「もうひとりくらい、子供を持つ気はない?」とまでベッドに入ってから言われ、奏汰はあれほど眠かったというのに、突然冷水でも浴びせられたようにシャキッ!と目覚めていたのものである。
「な、なんでだ!?というより、急にどうしたんだ?君は、七海を生んだ時つわりもつらかった上、物凄い難産だったから、もう一度同じ思いをするくらいなら、子供はもういいって……」
「それはそうなんだけど。わたし、姉さんが結婚した時、きっと姉さんにも子供が出来て、父さんや母さんを喜ばせてくれるだろうと思ってたのよ。でも姉さん、子供なんか全然欲しいと思えないっていう人で、旦那さんの鷹橋さんのほうでもそのことに同意してて……まあ、向こうはすでにもう四回も離婚してて、全部で子供が十人ばかりもいるから、そりゃそうでしょうねって感じではあるわよね。でも、今日の父さんや母さんの七海を見るあの目つき……もちろんわたしだって、この先七海に何かあるだなんて思ってないわ。だけど、たとえば大学からは留学したいとか、何かそんなことになったらわたしも寂しいし、父さんと母さんも打ちのめされると思うのよ。ほら、たとえば手術さえすれば必ず治る病気で入院したってだけでも、相当な打撃だと思うのね」
「まあな。もちろん、ふたり目が出来たからって、そういう人生上のリスクは回避できないにしても、小百合の言いたいことはもちろん俺にもわかる。だけど、おまえももう四十二だし……高齢出産はやっぱり危険だよ。それに子供だって、障害のある子が生まれる可能性が二十代や三十代で子供を生むよりずっと高まるわけだから」
奏汰はこの時内心で冷や汗をかいていた。もし彼に清宮明日香という愛人がおらず、今小百合がこうした申し出をしていたとしたら……おそらく賛成していたに違いない。それに彼の妻はこうしたある種の<正しい申し出>をすることにより、夫の心を繋ぎ留めようとしていることも明白だった。
(そうよ。七海を妊娠した時、あなたがわたしに対してどれほど優しかったか……つわりがあんまりひどくて妻として家庭の務めを十分果たせなくても、「そんなことは気にしなくていいから」って、わたしに食事を作ってくれたことさえあった。今日、わたしが実家で言ったことは本当よ。わたしは夫に対して不満なんてない。そしてそれは、彼が浮気さえやめてくれたら、本当にもう一度そうなるってことなのよ)
「でもあなた、新婚だった頃、よく言ってたじゃない。子供は最低でもふたりは欲しいよなって。わたし、七海の相手をしてるあなたのことを見てると、こんなに優しくていいパパはいないっていつも思うのよ。ほんと、馬鹿だったわ。今のこの年になって自分でもふたり目が欲しいって気づくより、もっと早くにそうしてたら良かったんだけど……」
実際、夫が浮気をしないためであったら、小百合は子供を三人でも四人でも生んでおけば良かったと、近ごろつくづく後悔している。そうしたら、心のちょっとした隙を相手の女に突かれるということもなかっただろうにと(小百合は病院の看護師に夫が誘惑されて屈したのだろうという自分の推理をほぼ確信していた)。
「だ、だけど……俺はもう七海ひとりで十分とも思ってるんだ。何より、おまえにも危険な思いをして欲しくないし……」
「そう?わたし最近時々、意味もなく死にたいって思ったりするのよ。もちろん、具体的に自殺のことを考えるっていうんじゃなくね。そんな時、ふっと思ったの。もうひとりくらい子供がいたら、そんなことをなんとなくでも感じなくなるんじゃないかしらって」
「…………………」
――この時奏汰は瞬時にして思考停止状態になり、ベッドの中へもぐりこむと、妻に背を向けて眠った。小百合から「ねえ、あなた……」と肩に手をかけられても、彼は何度か咳き込んでこう言った。
「ごめん。もう今日は疲れてるんだ。それに、明日から仕事もぎっしりだ。今は色々なことを考える思考能力自体がない。そのことはまた明日以降ふたりで話しあおう」
奏汰のほうからは見えなかったが、この時小百合はある種の満足を覚えてにんまり微笑んだ。自分は今この瞬間、夫の心に楔を打ちこむことに成功した――その確信が彼女にはあったからである。
(大丈夫よ。結局この人、優しいもの。それで、その優しさがあればこそ、一度体の関係を持った女ともずるずる続いてるっていうそれだけなのよ。ああ、良かった。この人はまだわたしに対して脈がある。これなら、ここ数か月……ううん、もう半年かそれ以上になるんだったかしら。関係を持ってる女と、もう結婚して十年にもなるわたしと七海とのほうが絆のほうは深い。絶対この人はわたしと娘の元に必ず戻ってくるわ)
小百合はそう思うと心底からほっとした。子供のことは、もし夫が「ふたり目を作ろう」と言ったら、それはもう完全に愛人とは手を切るということだし、母体が危険云々といったことを理由に説得してくるのだとしても、夫は彼らしく妻に誠意を見せてその説明をするだろう。そう思うと小百合は十分満足だった。夫に愛人が出来たように感じて以降、彼が自分の体に一度も触れていなかったとしても……。
>>続く。

























