組合の教育研究集会で保護者負担軽減と就学援助受給者を増やす取り組みの両面から行い、子どもの貧困を克服するための第一歩としたいというレポートをした。そしたら同じ年齢くらいの学校事務職員から、「それは保護者の二重取りになるのではないか」という質問を受けた。オレは就学援助費で支給される費目以上に学校で集めているお金があること、就学援助費で支給されるのはほんの一部で、学校で集めるお金がなくなったとしても家庭でかかる教育費や衣服・靴などを買うための経費と考えれば二重取りなどにはならないと主張した。
それで参議院選挙が近くなってテレビや新聞で各政党の政策を比較する中で、共産党以外の政党が政党助成金をもらいながら企業・団体献金をもらっていることを考えると、それこそ二重取りだと思った。それで教育研究集会でのことを思い出した次第である。
国会議員の給与に当たる歳費や手当の他に、世襲政治家や財界出の政治家は親から譲り受けた資産があって、パーティー券で資金を集め、企業や団体からの献金をもらい、いったいどれほどお金を集めれば気が済むのかと思ってしまう。そういう意味で企業・団体献金も、税金の山分けである政党助成金も受け取らない共産党は筋が通っていると思う。国会議員の比例定数削減や公務員の削減をいう前に毎年約320億の税金を山分けしてる政党助成金こそやめるべきで、昨年話題になった事業仕分けでも真っ先に切って欲しかったがまったく手を付けないあたりが茶番である。
みんなの党の代表が昨年の衆議院選挙で企業・団体献金(政治資金パーティーを含む)の全面禁止を公約しておきながら、6年間で5億円もの企業・団体献金を受け取っていたそうである。一方で6年間に受け取った政党助成金は9900万円にのぼるとか。まさにこれこそ二重取りではないか。そう言えばつい先日まで消費税増税を主張していたのに、最近になって消費税増税反対を主張しているという一貫性のなさにも表れているように全く信用できない政治家だと思った。
そして強欲な政治家がため込んだ資産も、日産CEOカルロス・ゴーンが8.9億円というオレなんかには想像もつかない金額の役員報酬をもらったそうであるが、その他の大企業の役員や株主配当をもらっている資産家が手にしたお金は消費になど回らず、そのほとんどは権力を維持するためだったり、投棄マネー(バブル)に変わるだけで内需を拡大して景気を良くすることには繋がらないオレに言わせれば死に金(バブルだからアブク銭か?)だと思う。
論点がかなりそれてしまったけれど、言いたいのは教育研究集会で「二重取りだ」と言った同世代の青年の発言に見られるように、上には無関心で下には厳しい態度をとるという習性がオレも含めて庶民に根付いてしまっているのではないかということ。権力と富を持つ者にとって見れば、それらを持たない者同士がいがみ合って足の引っ張り合いをしてくれている方が都合がよいのだから、もっと大きな視点で世の中を見なければならないのではないだろうか。
そういう意味で消費税増税論議も消費税増税分がこれまでも福祉に回ってこなかったように福祉などには回らず、財政再建にも繋がらず、権力と富を持つ者のために法人税や所得税や相続税などの減税分の穴埋めにされると見るべきであろう。
このエントリーにあたって政党助成金について調べてみたらWikipediaに詳しく載っていたのでリンクしておきます。政党交付金
なおかつ一部引用しておきます。
問題点 [編集]
税金から出るので支持していない政党へも資金を提供することになる
参政権はないが納税している日本在住外国人や未成年者も政党の資金を負担することになる
要件に当てはまらない政治団体には支給されない
一定の得票を得ていたり地方議会で数多くの議席を得ていたり首長を出していたりしてももらえない
助成金支給日直前の政党の離合集散が起きているという指摘がある
助成金は年末・年始(4月、7月、10月、12月に25%ずつ)に支給される
1996年12月26日に結党した太陽党は一部メディアから批判された
自由民主党非公認の保守系無所属当選組5人による院内会派「グループ改革」が、自民党移籍前に政党化して交付金を受け取ろうと試みたが断念
使途について制限がない
政党の政治活動の自由を尊重する観点から、政党交付金の使途について制限してはならないと定められているため、その使い道は貸し植木代、タクシー代、高級料亭などでの飲み食い、党大会の会場費、自動車税の支払い、テレビCM放映料などにも及んでいる。
税金依存体質につながる
政党交付金に依存する体質ができると政党は世論より税金の動きを気にするようになり、支持者の意見を聞いたり、自ら政策の理解を訴えて支援を呼びかけたりすることをやめてしまう。逆に、政府与党が他党の資金をも握ることとなり、統制・介入につながる危険性もある。
解党時の使途が定められていない
解党時の党首の政治団体に入金されるなど、不透明なカネの流れを疑問視する人もいる。
「政党交付金は国会の議席数に基づいて配分されるため、大型国政選挙で大勝すると交付金が大幅に増やされ、大敗すると交付金が大幅に減らされることになる。一度政党交付金に依存する体質ができてしまうと、その政党には経済的窮乏と混乱が生じることになる。これも政党の離合集散の原因になる」という意見もある。2007年分の政党交付金は、大敗した自民党は年初の見込み額から5億1600万円減の165億9500万円、一方、躍進した民主党は5億7000万円増の110億6300万円となった。
政党の対応 [編集]
日本共産党は「思想良心の自由に反し、憲法違反である」(東京地裁は合憲の判決を出している。学説では違憲説が多数だが、「政党は準国家機関であり、公費助成は正当」とする少数説もある[誰?])「税金の無駄遣いである」「企業団体献金禁止を名目に助成制度を作ったにもかかわらず、現在も企業団体献金を残しているのは有権者への裏切り」として政党助成制度の廃止を主張しており、助成金受け取り団体に登録していない(その分は他の政党に配分されている)。
第二院クラブは当初、登録しておいて受け取りを拒否し、自党が受け取るはずの助成金を国庫に戻させていたが、佐藤道夫の代表就任以降、財政難を理由に受け取るようになった。
社会民主党は阿部知子が「NPOや市民活動と同じく、お金のない一般市民が政党を作り政治に参加するための財政保障制度として必要不可欠」と増額を主張しており、辻元清美は受け取り拒否を「ポピュリズム」と批判している(但し、土井たか子は2003年総選挙で廃止を主張したことがある)。
新党護憲リベラルは「議席に応じて受け取り額が異なるのは不公平」と公平性を理由に反対した。
また、政党交付金の導入は、ミニ政党への締め付けの強化と同時に行われている。具体的には、選挙費用(ポスター、ビラ、広告代など)は公費負担が原則だが、公費負担の足切りを強化し、選挙区では供託金没収、比例代表区では一定の得票率(参議院では1%、衆議院ではブロックごとに2%)未満の候補者は公費負担の多くを受けられなくしたことなどである。このため、従来はこうした「泡沫候補」に使われていた費用を、既成政党で分け取りしたに過ぎないという批判もある。
2005年までの10年間に各党が受け取った政党交付金 [編集]
自由民主党 1470億2,100万円
民主党 619億5,000万円
社会民主党 266億5,400万円
公明党 211億1,800万円
その他政党(二院クラブ、新社会党、新党護憲リベラル、自由連合、無所属の会など) 558億5,400万円
※日本共産党は政党要件を満たしているが、上記の理由により政党交付金(政党助成金)の受け取りを制度の創設時から、一貫して拒否し続けている。
(引用ここまで)
それで参議院選挙が近くなってテレビや新聞で各政党の政策を比較する中で、共産党以外の政党が政党助成金をもらいながら企業・団体献金をもらっていることを考えると、それこそ二重取りだと思った。それで教育研究集会でのことを思い出した次第である。
国会議員の給与に当たる歳費や手当の他に、世襲政治家や財界出の政治家は親から譲り受けた資産があって、パーティー券で資金を集め、企業や団体からの献金をもらい、いったいどれほどお金を集めれば気が済むのかと思ってしまう。そういう意味で企業・団体献金も、税金の山分けである政党助成金も受け取らない共産党は筋が通っていると思う。国会議員の比例定数削減や公務員の削減をいう前に毎年約320億の税金を山分けしてる政党助成金こそやめるべきで、昨年話題になった事業仕分けでも真っ先に切って欲しかったがまったく手を付けないあたりが茶番である。
みんなの党の代表が昨年の衆議院選挙で企業・団体献金(政治資金パーティーを含む)の全面禁止を公約しておきながら、6年間で5億円もの企業・団体献金を受け取っていたそうである。一方で6年間に受け取った政党助成金は9900万円にのぼるとか。まさにこれこそ二重取りではないか。そう言えばつい先日まで消費税増税を主張していたのに、最近になって消費税増税反対を主張しているという一貫性のなさにも表れているように全く信用できない政治家だと思った。
そして強欲な政治家がため込んだ資産も、日産CEOカルロス・ゴーンが8.9億円というオレなんかには想像もつかない金額の役員報酬をもらったそうであるが、その他の大企業の役員や株主配当をもらっている資産家が手にしたお金は消費になど回らず、そのほとんどは権力を維持するためだったり、投棄マネー(バブル)に変わるだけで内需を拡大して景気を良くすることには繋がらないオレに言わせれば死に金(バブルだからアブク銭か?)だと思う。
論点がかなりそれてしまったけれど、言いたいのは教育研究集会で「二重取りだ」と言った同世代の青年の発言に見られるように、上には無関心で下には厳しい態度をとるという習性がオレも含めて庶民に根付いてしまっているのではないかということ。権力と富を持つ者にとって見れば、それらを持たない者同士がいがみ合って足の引っ張り合いをしてくれている方が都合がよいのだから、もっと大きな視点で世の中を見なければならないのではないだろうか。
そういう意味で消費税増税論議も消費税増税分がこれまでも福祉に回ってこなかったように福祉などには回らず、財政再建にも繋がらず、権力と富を持つ者のために法人税や所得税や相続税などの減税分の穴埋めにされると見るべきであろう。
このエントリーにあたって政党助成金について調べてみたらWikipediaに詳しく載っていたのでリンクしておきます。政党交付金
なおかつ一部引用しておきます。
問題点 [編集]
税金から出るので支持していない政党へも資金を提供することになる
参政権はないが納税している日本在住外国人や未成年者も政党の資金を負担することになる
要件に当てはまらない政治団体には支給されない
一定の得票を得ていたり地方議会で数多くの議席を得ていたり首長を出していたりしてももらえない
助成金支給日直前の政党の離合集散が起きているという指摘がある
助成金は年末・年始(4月、7月、10月、12月に25%ずつ)に支給される
1996年12月26日に結党した太陽党は一部メディアから批判された
自由民主党非公認の保守系無所属当選組5人による院内会派「グループ改革」が、自民党移籍前に政党化して交付金を受け取ろうと試みたが断念
使途について制限がない
政党の政治活動の自由を尊重する観点から、政党交付金の使途について制限してはならないと定められているため、その使い道は貸し植木代、タクシー代、高級料亭などでの飲み食い、党大会の会場費、自動車税の支払い、テレビCM放映料などにも及んでいる。
税金依存体質につながる
政党交付金に依存する体質ができると政党は世論より税金の動きを気にするようになり、支持者の意見を聞いたり、自ら政策の理解を訴えて支援を呼びかけたりすることをやめてしまう。逆に、政府与党が他党の資金をも握ることとなり、統制・介入につながる危険性もある。
解党時の使途が定められていない
解党時の党首の政治団体に入金されるなど、不透明なカネの流れを疑問視する人もいる。
「政党交付金は国会の議席数に基づいて配分されるため、大型国政選挙で大勝すると交付金が大幅に増やされ、大敗すると交付金が大幅に減らされることになる。一度政党交付金に依存する体質ができてしまうと、その政党には経済的窮乏と混乱が生じることになる。これも政党の離合集散の原因になる」という意見もある。2007年分の政党交付金は、大敗した自民党は年初の見込み額から5億1600万円減の165億9500万円、一方、躍進した民主党は5億7000万円増の110億6300万円となった。
政党の対応 [編集]
日本共産党は「思想良心の自由に反し、憲法違反である」(東京地裁は合憲の判決を出している。学説では違憲説が多数だが、「政党は準国家機関であり、公費助成は正当」とする少数説もある[誰?])「税金の無駄遣いである」「企業団体献金禁止を名目に助成制度を作ったにもかかわらず、現在も企業団体献金を残しているのは有権者への裏切り」として政党助成制度の廃止を主張しており、助成金受け取り団体に登録していない(その分は他の政党に配分されている)。
第二院クラブは当初、登録しておいて受け取りを拒否し、自党が受け取るはずの助成金を国庫に戻させていたが、佐藤道夫の代表就任以降、財政難を理由に受け取るようになった。
社会民主党は阿部知子が「NPOや市民活動と同じく、お金のない一般市民が政党を作り政治に参加するための財政保障制度として必要不可欠」と増額を主張しており、辻元清美は受け取り拒否を「ポピュリズム」と批判している(但し、土井たか子は2003年総選挙で廃止を主張したことがある)。
新党護憲リベラルは「議席に応じて受け取り額が異なるのは不公平」と公平性を理由に反対した。
また、政党交付金の導入は、ミニ政党への締め付けの強化と同時に行われている。具体的には、選挙費用(ポスター、ビラ、広告代など)は公費負担が原則だが、公費負担の足切りを強化し、選挙区では供託金没収、比例代表区では一定の得票率(参議院では1%、衆議院ではブロックごとに2%)未満の候補者は公費負担の多くを受けられなくしたことなどである。このため、従来はこうした「泡沫候補」に使われていた費用を、既成政党で分け取りしたに過ぎないという批判もある。
2005年までの10年間に各党が受け取った政党交付金 [編集]
自由民主党 1470億2,100万円
民主党 619億5,000万円
社会民主党 266億5,400万円
公明党 211億1,800万円
その他政党(二院クラブ、新社会党、新党護憲リベラル、自由連合、無所属の会など) 558億5,400万円
※日本共産党は政党要件を満たしているが、上記の理由により政党交付金(政党助成金)の受け取りを制度の創設時から、一貫して拒否し続けている。
(引用ここまで)















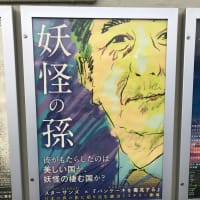










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます