
昨日は福島県学校事務職員制度研究会(通称:福島制度研)の秋の学習会と、午後は福島制度研も主催者に名を連ねる「シンポジウム 学校の安全を考える」に参加してきた。
午前の福島制度研秋の学習会は短い時間ではあったが中身の濃い例会だった。予算委員会を機能させて学校集金の集め方や使い方におけるルールづくりの取り組みや、学校の施設や備品などについて子どもの声を聞く子どもアンケートの実践を交流した。子どもアンケートの結果(子どもの生の声)を予算要求書に添付して教育委員会に届けようとしたら教頭に止められたという実態もだされた。ありのままをさらけ出して教育委員会や保護者と解決策や改善策を探ろうとする度量は持ち合わせていないのだろう。
午後は「学校の安全を考える」と題して学校災害・事故についてのシンポジウムに参加した。「子どもの命と人権を守る福島の会」とならんで福島制度研も主催者に名を連ねている。福島制度研は以前から学校事務職員の立場で学校内で起こる災害や事故を未然に防ぐ対策や、起きてしまった場合の補償制度のあり方を検討してきた。前述した子どもアンケートもその取り組みの一つだ。
パネラーはマスコミでも話題になっている須賀川一中柔道部事故(リンチ事件だな)によって意識不明になっているKさんの両親、須賀川市議、学校事務職員、フロアからは県立石川高校の水泳の授業中に溺死したIさんの両親の発言もあった。
須賀川一中柔道部の事件は現在裁判中で、新聞・全国放送のテレビ番組・テレビユー福島のニュースなどのほか、2ちゃんねるで話題になって折り鶴を送るなどの支援活動も広がっている。(詳細は須賀川一中・柔道部で検索してみて下さい。)この事件でも教育行政が官僚化していることがよく分かる。校長が柔道部保護者会や事故報告書で虚偽の報告をした可能性が高いとか、隠蔽しようとしたとか、県や市の教育委員会も真摯に対応してくれないとか。午前の子どもの生の声を教育委員会に伝えたくないという事例や、今話題になっているいじめの調査にいじめはなかったと報告される実態と根っこは一緒で、「開かれた学校」とか簡単に口にするわりには肝心なことは隠蔽してしまう学校の体質がうかがえる。これらの学校の体質は学校で働く者の責任として変えていかなければならない課題だが、教育基本法の改正などでますます「物言わぬ教師」が作られようとしているから外からしか改革できなくなるか?。
それで須賀川一中の校長がどんな人だか知りたくて職員録を開いてみて驚いた。なんと須賀川一中に来る前は県中教育事務所の次長兼生涯学習課長でその下には8月にセクハラでクビになったN校長もいた。県中教育事務所の生涯学習課っていったいどういうところなんじゃ。それから1年生部員がいじめだったという証言をしたら恫喝したとか、虚偽の事故報告書を作成したとされる当時の教頭は今は県の体協事務局にとばされたようだが、以前常葉町教育委員会に派遣で来てたこともある人だった。どの人も教育行政の官僚機構にどっぷりつかって、気合いを入れることが大好きな体育会系の人たちのようだ。
しかし教育行政のセオリーから考えるといくら大物校長でもこのくらいの事件の場合は教育長の指示を仰いでいたのではないだろうかと考えるのが普通だ。そして教育委員会のところを見てみたら当時県内でも有名なワンマン教育長の名前がでていた。この教育長は校長を退職してすぐに教育長になり4期12年の間須賀川市の教育長を務めた人でこの事件のあった翌年の9月に任期満了で退任していた。校長で退職してがっぽりもらって、教育長になって市長レベルの給料を12年間もらったことだろうからかなり稼いだな。おそらくこの教育長が指示をだして校長を操っておきながら、後は後任の教育長にまかせ自分は知らんぷりというのが容易に想像できるな。そして校長も来年の3月で定年を迎えるからこのままずるずる引っ張ってがっぽりもらっておさらばと考えているのかもしれない。そうやって当事者がいなくなって誰も責任をとらないというのが官僚機構のセオリーだ。
石川高校で溺死したIさんのお父さんが、学校のすぐに救急車を呼ばない体質がいけないと発言していたが、須賀川一中も同様でお母さんが学校に呼ばれて到着してから救急車を呼んだそうだ。官僚機構にどっぷり浸かっている管理職は体裁を気にして救急車を呼びたがらないのかもしれない。それから物言わぬ教師たちも管理職の許可がなければ救急車を呼べないと思っている。実際に学校事故が起こって養護教諭が救急車を呼ばなければならないと判断したのに校長が会議中だったために会議が終わるまで待っていたという嘘のような事例もある。これでもし子どもが命を落としていたら養護教諭の責任だな。
この問題も学校で働く者にとって重要な課題だ。管理職がいて管理職が呼ばないと判断すればその管理職の責任だが、管理職が不在だったり近くにいなくて探しに行ったりしている間に手遅れになったらその人の責任になる。最悪のことを想定して救急車を呼んでおいた方が間違いがないと思う。そしてそういう認識を共有しておかなければならないな。
とても重いシンポジウムで自分自身の学校での取り組みや課題を考えさせられた1日だった。真相究明と、仕事なのか趣味なのかボランティアなのか分からない部活動のあり方を見直してこういう事故が二度と起きないようにすること。それから裁判などではなく学校が自ら真摯に対応して説明責任を果たす開かれた学校にすること。学校をそんなふうにさせている教育行政も変わらなければならないな。
午前の福島制度研秋の学習会は短い時間ではあったが中身の濃い例会だった。予算委員会を機能させて学校集金の集め方や使い方におけるルールづくりの取り組みや、学校の施設や備品などについて子どもの声を聞く子どもアンケートの実践を交流した。子どもアンケートの結果(子どもの生の声)を予算要求書に添付して教育委員会に届けようとしたら教頭に止められたという実態もだされた。ありのままをさらけ出して教育委員会や保護者と解決策や改善策を探ろうとする度量は持ち合わせていないのだろう。
午後は「学校の安全を考える」と題して学校災害・事故についてのシンポジウムに参加した。「子どもの命と人権を守る福島の会」とならんで福島制度研も主催者に名を連ねている。福島制度研は以前から学校事務職員の立場で学校内で起こる災害や事故を未然に防ぐ対策や、起きてしまった場合の補償制度のあり方を検討してきた。前述した子どもアンケートもその取り組みの一つだ。
パネラーはマスコミでも話題になっている須賀川一中柔道部事故(リンチ事件だな)によって意識不明になっているKさんの両親、須賀川市議、学校事務職員、フロアからは県立石川高校の水泳の授業中に溺死したIさんの両親の発言もあった。
須賀川一中柔道部の事件は現在裁判中で、新聞・全国放送のテレビ番組・テレビユー福島のニュースなどのほか、2ちゃんねるで話題になって折り鶴を送るなどの支援活動も広がっている。(詳細は須賀川一中・柔道部で検索してみて下さい。)この事件でも教育行政が官僚化していることがよく分かる。校長が柔道部保護者会や事故報告書で虚偽の報告をした可能性が高いとか、隠蔽しようとしたとか、県や市の教育委員会も真摯に対応してくれないとか。午前の子どもの生の声を教育委員会に伝えたくないという事例や、今話題になっているいじめの調査にいじめはなかったと報告される実態と根っこは一緒で、「開かれた学校」とか簡単に口にするわりには肝心なことは隠蔽してしまう学校の体質がうかがえる。これらの学校の体質は学校で働く者の責任として変えていかなければならない課題だが、教育基本法の改正などでますます「物言わぬ教師」が作られようとしているから外からしか改革できなくなるか?。
それで須賀川一中の校長がどんな人だか知りたくて職員録を開いてみて驚いた。なんと須賀川一中に来る前は県中教育事務所の次長兼生涯学習課長でその下には8月にセクハラでクビになったN校長もいた。県中教育事務所の生涯学習課っていったいどういうところなんじゃ。それから1年生部員がいじめだったという証言をしたら恫喝したとか、虚偽の事故報告書を作成したとされる当時の教頭は今は県の体協事務局にとばされたようだが、以前常葉町教育委員会に派遣で来てたこともある人だった。どの人も教育行政の官僚機構にどっぷりつかって、気合いを入れることが大好きな体育会系の人たちのようだ。
しかし教育行政のセオリーから考えるといくら大物校長でもこのくらいの事件の場合は教育長の指示を仰いでいたのではないだろうかと考えるのが普通だ。そして教育委員会のところを見てみたら当時県内でも有名なワンマン教育長の名前がでていた。この教育長は校長を退職してすぐに教育長になり4期12年の間須賀川市の教育長を務めた人でこの事件のあった翌年の9月に任期満了で退任していた。校長で退職してがっぽりもらって、教育長になって市長レベルの給料を12年間もらったことだろうからかなり稼いだな。おそらくこの教育長が指示をだして校長を操っておきながら、後は後任の教育長にまかせ自分は知らんぷりというのが容易に想像できるな。そして校長も来年の3月で定年を迎えるからこのままずるずる引っ張ってがっぽりもらっておさらばと考えているのかもしれない。そうやって当事者がいなくなって誰も責任をとらないというのが官僚機構のセオリーだ。
石川高校で溺死したIさんのお父さんが、学校のすぐに救急車を呼ばない体質がいけないと発言していたが、須賀川一中も同様でお母さんが学校に呼ばれて到着してから救急車を呼んだそうだ。官僚機構にどっぷり浸かっている管理職は体裁を気にして救急車を呼びたがらないのかもしれない。それから物言わぬ教師たちも管理職の許可がなければ救急車を呼べないと思っている。実際に学校事故が起こって養護教諭が救急車を呼ばなければならないと判断したのに校長が会議中だったために会議が終わるまで待っていたという嘘のような事例もある。これでもし子どもが命を落としていたら養護教諭の責任だな。
この問題も学校で働く者にとって重要な課題だ。管理職がいて管理職が呼ばないと判断すればその管理職の責任だが、管理職が不在だったり近くにいなくて探しに行ったりしている間に手遅れになったらその人の責任になる。最悪のことを想定して救急車を呼んでおいた方が間違いがないと思う。そしてそういう認識を共有しておかなければならないな。
とても重いシンポジウムで自分自身の学校での取り組みや課題を考えさせられた1日だった。真相究明と、仕事なのか趣味なのかボランティアなのか分からない部活動のあり方を見直してこういう事故が二度と起きないようにすること。それから裁判などではなく学校が自ら真摯に対応して説明責任を果たす開かれた学校にすること。学校をそんなふうにさせている教育行政も変わらなければならないな。















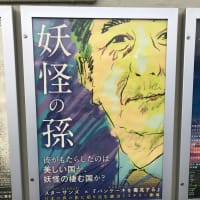










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます