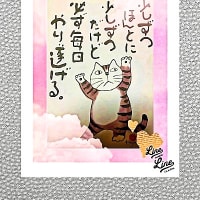山本夏彦は、この評伝『無想庵物語』で、平成2年に讀賣文学賞を受賞している。私は、四十数年来、この人の文章のファンだが、本性は奇人・変人と見ていたので、文学賞など辞退すると思って当てが外れた。念のため、フリー百科事典『ウィキペディア』で年譜を確認すると、受賞三回、記念パーティ六回、励ます会一回、とあり、合点がいった。
山本夏彦は、この評伝『無想庵物語』で、平成2年に讀賣文学賞を受賞している。私は、四十数年来、この人の文章のファンだが、本性は奇人・変人と見ていたので、文学賞など辞退すると思って当てが外れた。念のため、フリー百科事典『ウィキペディア』で年譜を確認すると、受賞三回、記念パーティ六回、励ます会一回、とあり、合点がいった。
文学(文化)賞受賞は、菊池寛賞(昭和59年)、讀賣文学賞(平成2年)、市川市民文化賞(平成10年)。平成9年の東京都文化賞は、前年のいきさつから辞退。記念パーティは、月刊雑誌『諸君!』・週刊誌『週刊新潮』に掲載のコラムの掲載回数の節目を記念して版元が開催している。「いかさまの人・ダメの人」と自称するくらいだから、くれるものはもらう、祝ってくれれば喜んで出席するというのも、当然といえば当然であった。
無想庵武林盛一のことを知るものは今はいないだろう。『無想庵物語』の帯には「芸術家として新機軸を出したい──そう希いつつ無軌道な愛欲と放浪に身をゆだね、ついに失敗したダダイスト・武林無想庵。その破天荒な生涯を、彼の親友の子としてパリで起居を共にした著者が、哀惜の念をこめて描く」とあるが、帯の文章など、売らんがための版元の宣伝文句である。もの書き(作家)や出版業者は、もともと堅気の人間とはみなされなかった。それがいつから社会的名士となったのか、私は知らないが、山本夏彦も、武林盛一と「一つ穴の狢」である。
書かれた物と書いた者は別ものである。武林がいくら希代の物知りであっても、才がなければ、人の心を引きつける物を書くことはできない。共に無頼の徒でありながら、武林には才がなく、夏彦には才があったのだろう。私は、著者の経歴には何の興味もない。ただ、『無想庵物語』に滲み出る、芸術家を志し失敗した者に対する著者の惻隠の情に心動かされるのである。
最近の「学芸文化」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事
![人生残り10年の読書記録 (7) 『[詳解] 独ソ戦全史』](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/20/fe/251517596a253652d298f2f3c577b6d9.jpg)