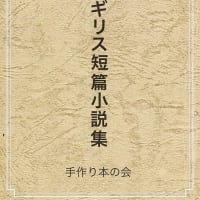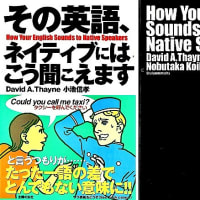吉川英治の『三國志』については既に書いた。今回この本を再び取り上げたのは、内容ではなく、印刷に用いられた活字の書体について、私の好みをいささか開陳したいと思ったからである。
活字に興味を持ったのは、就職後半年くらいに、職場にあった日本タイプライター株式会社の和文タイプライターを用いて、文書作成の練習を始めたのがきっかけだった。ほどなく、ひととおりの技術を身につけると、付属の5号活字では飽きたらず、9ポイントと12ポイントの活字盤を予備庫・貯蔵庫・記号庫付きセットで買い求めて、文書の〈見栄え〉に変化をつけることに熱中した。当然ながら、書体は明朝のみである。
しかし、昭和50年代になって、小型で高性能、数種類のフォントを備えたワードプロセッサーが普及すると、和文タイプライターはたちまち駆逐され姿を消した。平成に入ると、今度は、パーソナルコンピュータのワープロソフトとプリンタの機能が飛躍的に向上、ワードプロセッサーに取って代わった。総合的に判断して、フォントの種類もワードプロセッサーの比ではなく、勝敗の帰趨は明らかだった。これらの文書作成機器の主役交代が、わずか十数年の間の出来事だったことを思うと驚かざるを得ない。
 吉川英治の『三國志』の目次には、宋朝体という珍しい書体が用いられていて、圧倒的に量の多い明朝体の本文に引けを取らない存在感がある。私はこの書体が好きで、平成9年に新しく購入した<パワーマック5500>に、ダイナ・フォントの新宋体をインストールして使ってみた。宋朝体の独特な装飾性はかなり弱められているが、それなりに雰囲気は出ているので、今も用いている。かなり癖の強い字体なので、人によっては拒否反応を示すかも知れない。
吉川英治の『三國志』の目次には、宋朝体という珍しい書体が用いられていて、圧倒的に量の多い明朝体の本文に引けを取らない存在感がある。私はこの書体が好きで、平成9年に新しく購入した<パワーマック5500>に、ダイナ・フォントの新宋体をインストールして使ってみた。宋朝体の独特な装飾性はかなり弱められているが、それなりに雰囲気は出ているので、今も用いている。かなり癖の強い字体なので、人によっては拒否反応を示すかも知れない。
最近の「学芸文化」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事