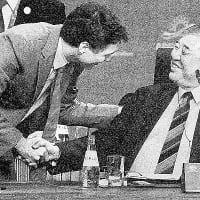五月の北海道財務局のまとめによると、道内金融機関の貸出金残高(貸出金残高推移グラフ=写真上段は、7月16日付『北海道新聞』第11面から転写)が平成二十年二月以来、二年三か月ぶりに前年を下回り、「12兆6085億円で、前年同月比0.1%」(同新聞)となり、その後の基調にも大きな変化は見られない。銀行が貸し出しをわずかに増やしたものの、信金や信組は苦戦を強いられ、道内企業の設備投資意欲が減退する中で、金融機関どおしの競争が激しくなっている。
五月の北海道財務局のまとめによると、道内金融機関の貸出金残高(貸出金残高推移グラフ=写真上段は、7月16日付『北海道新聞』第11面から転写)が平成二十年二月以来、二年三か月ぶりに前年を下回り、「12兆6085億円で、前年同月比0.1%」(同新聞)となり、その後の基調にも大きな変化は見られない。銀行が貸し出しをわずかに増やしたものの、信金や信組は苦戦を強いられ、道内企業の設備投資意欲が減退する中で、金融機関どおしの競争が激しくなっている。
 道内企業の資金需要低迷と信金・信組の苦戦は、北海道新聞社の調査による2010年3月期預貸率(3月期預貸率表=写真中段は、3月7日付・同新聞・第13面から転写)にも表れている。上位の北洋銀行(76.7%)北海道銀行(74.9%)十勝信組(72.6%)の70%台に比べて、下位の稚内信金(24.3%)北星信金(38.5%)網走信金(39.4%)の30%台の差は大きい。
道内企業の資金需要低迷と信金・信組の苦戦は、北海道新聞社の調査による2010年3月期預貸率(3月期預貸率表=写真中段は、3月7日付・同新聞・第13面から転写)にも表れている。上位の北洋銀行(76.7%)北海道銀行(74.9%)十勝信組(72.6%)の70%台に比べて、下位の稚内信金(24.3%)北星信金(38.5%)網走信金(39.4%)の30%台の差は大きい。
最下位の稚内信金では、「人口減や過疎化で地域経済が疲弊し、貸すところがない」(同新聞)のが実情で、40%台の地域も資金需要の乏しさは変わりない。 日本経済は部分的に回復基調にあるとはいえ、全体としては2008年のリーマンショックによる世界経済危機がもたらしたデフレ(消費者物価指数の動き=写真下段は、7月9日付・同新聞・第8面から転写)を脱却できずにいる。国内需要が見込めないため、企業は、対アジア戦略を強化し輸出に活路を求めてきたが、米国経済の先行き不安に端を発した円高で、積極的な設備投資に不安を抱き始めた。カネ余り金融機関は、必然的に、リスクを避け国債買いを加速させている。金融機関は預貸金利ざやで収益を上げるのが本来の営業の在り方であり、有価証券の運用は、国債といえどもリスクを抱える要因となることを忘れてはならない。政府は、デフレにも円高にも実効のある手を何も打てない本当の空き缶か。
日本経済は部分的に回復基調にあるとはいえ、全体としては2008年のリーマンショックによる世界経済危機がもたらしたデフレ(消費者物価指数の動き=写真下段は、7月9日付・同新聞・第8面から転写)を脱却できずにいる。国内需要が見込めないため、企業は、対アジア戦略を強化し輸出に活路を求めてきたが、米国経済の先行き不安に端を発した円高で、積極的な設備投資に不安を抱き始めた。カネ余り金融機関は、必然的に、リスクを避け国債買いを加速させている。金融機関は預貸金利ざやで収益を上げるのが本来の営業の在り方であり、有価証券の運用は、国債といえどもリスクを抱える要因となることを忘れてはならない。政府は、デフレにも円高にも実効のある手を何も打てない本当の空き缶か。
最近の「政治経済」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事