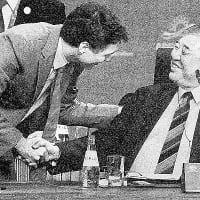左は、自然実生樹齢五年のトドマツの幼木(釧路町深山)、右は、樹齢五十年・直径九寸五分のトドマツの切り株(白糠町上庶路)。北海道の針葉樹が製材用原木として利用可能な大きさまで育つには、カラマツが三十年から五十年、トドマツが五十年から八十年、アカエゾマツが八十年から百年の年月を要する。しかし、原木の価格は、本州のヒノキやスギと比べて、はるかに安いため、北海道で原木生産を生業とすることは極めて困難である。手入れの行き届かない民有林が多いのは、このため。
林野庁による国有林育成を目的とした「緑のオーナー制度」が、木材価格の下落で、元本割れの状態となり、オーナーから不満が出ているという。しかし、10月26日付『北海道新聞』第1面に掲載された、「元本割れ補てんせず」という大見出しの記事によると、林野庁は、「損失補てんは行わない対応方針を固めた」ようだ。
緑のオーナー制度は、国有林のヒノキやスギ育成資金を募り、十五年から三十年の契約満了時の立木の販売収入を、出資額に応じて分配する仕組みである。国内の人工林の立木価格は、安価な外材の輸入により、昭和五十年代後半から下落を続けている。オーナーは、契約内容の説明不足を指摘するが、そもそも何十年も先の木材相場を予測することは不可能であり、契約内容に損失補填が含まれていないことは、出資者がリスクを負うということで、債権を購入するのと同じと考えられる。
北海道の場合は、ヒノキやスギの生育が道南に限られ、契約者数が少ないため、一部が満期を迎え、元本割れで落札販売されても、大きなトピックにはなっていない。私なら、リスクは覚悟の上で、山林の育成に奉仕した、と考えたい。
最近の「政治経済」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事