
水生生物を調べる--川の生き物から川を知る--
川の上流・中流・下流域で確認される水生昆虫や貝・カニなどの武生(ていせい)動物には、たくさんの種類があります。
川にすむ生物は、水に溶けている酸素の量(溶存酸素)と深く関係しています。酸素は水温が低いほどよく溶け、高いほど溶ける量は少なくなります。また、酸素は光合成の際、植物によってもつくられますが、汚れている川では細菌等によってたくさん使用されるので酸素の量は少なくなっています。
酸素の量が少なくなるときれいな水にすむ生物はすめなくなり、汚れたところの生物が多く見られるようになります。それぞれの生物は、溶けている酸素の量との関係で自分にあった「環境の幅」をもっています。そこにすむ生物を調べることで、水質などの川の環境が分かり、そのことを教えてくれる生物を「指標生物(しひょうせいぶつ)」といいます。このようにして水質を調べる方法を生物学的水質判定法といいます。
水のきれいさの程度は、きれいな水(水質階級Ⅰ)少しきたない水(水質階級Ⅱ)きたない水(水質階級Ⅲ、大変きたない水(水質階級Ⅳ)の4階級に分け、30種類の指標生物を用いて調べることができます。
調査結果のまとめ方と留意点
1 採収場所:流れの中心、左岸、右岸と書く
*右岸(左岸)とは、川の上流からら下流を見て、
右側(左側)の川岸のことです。
2.流れの速さ:3段階で記入します。
段階 流れの速さの目安
おそい 30cm/秒以下
ふつう 30~60cm/秒
はやい 60cm/秒以 :
*流れの速さを正しく測りたい場介は、3ないし5mの浮きのついたひもを足元から落として、ピンとはった時点までの時間を計り、その時間で割ると1秒あたりの速さが計算できます。
(例)3mのひもで6秒かかった場合
300cm÷6秒-50cm/秒
3 水質階級の判定
1)調査結果を左の表のように記録します。
①見つかった指標生物をそれぞれの欄に○印を記入します。
②数が多かった上位2種類には●印をつけます。
2)調査場所ごとに水賢階級を判定します。
①○印と●印の数の合計を「水質階級の判定]
1の欄に記入します。
②●印だけの合計を各水質階級ごとに2の欄に
記入します。
③3の欄に1・2欄の合計を記入します。
④3の欄の最も人きい数字がその場所の水質階級と判定、一番下の欄にⅠⅡⅢⅣの数字で記入します、
3)水質階級が同じ数字になった場介は、数字の小さい方をその地点の水質階級とします。
****************
どんな生き物で調べるかはこんど
まとめ
調査結果を一覧できる図にまとめ、村落・住宅・団地・市街地・工場などの位置を比べたり、同じ場所での調査結果を毎年比べると、身近な川の状況が分かり、汚れの原因や川づくりのヒントが見つかります














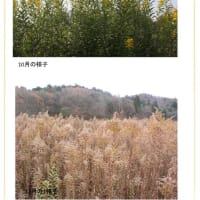
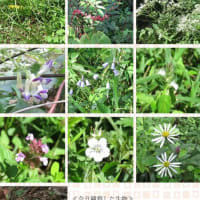
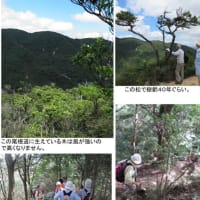
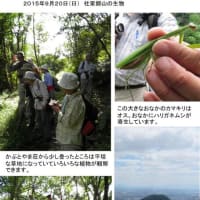



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます