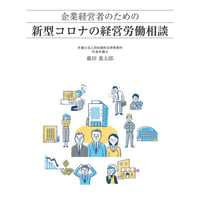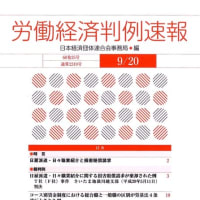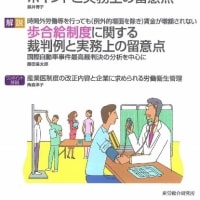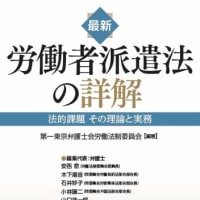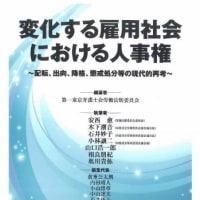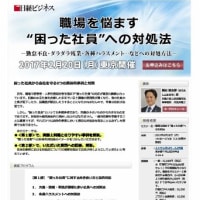業務上のミスを繰り返して会社に損害を与える。
(1) 募集採用活動の重要性
業務上のミスを繰り返す社員を減らす一番の方法は,採用活動を慎重に行い,応募者の適性・能力等を十分に審査して基準を満たした者のみを採用することです。
採用活動の段階で手抜きをして,十分な審査をせずに採用していったのでは,担当業務が単純な内容でマニュアルや教育制度がよほど整備されているような会社でない限り,業務上のミスを減らすことはできないでしょう。
(2) 採用後の対応
採用後の社員による業務上のミスの対策としては,社員の適性に合った配置,人事異動,注意指導,教育,人事考課,保険加入によるリスク管理等が中心となります。
事業主は労働者を使用することにより得られる利益を享受する以上,損失についても事業主が負担すべきとの考え(報償責任)が一般的ですから,過失によるうっかりミスについては,損害賠償請求はなかなか認められませんし,認められたとしても損害額の一部にとどまり,実際の回収可能性も低いことが多いというのが実情です。
基本的には,業務上のミスによる損害を,当該社員に対する損害賠償請求で填補できるものとは考えるべきではありません。
(3) 証拠の確保
懲戒処分,解雇,損害賠償請求をするためには,どのようなミスを繰り返し,会社がどのような損害を被ったのかを具体的に説明できるようにしておく必要があります。
その都度記録を残し,始末書を取るなどして,証拠を残しておいて下さい。
(4) 損害賠償請求
社員の故意又は重過失により会社が損害を被った場合には,社員に対して損害賠償請求をすることができます。
社員に軽過失しかない場合に損害賠償請求できるかどうかは事案次第ですが,軽過失は免責される事例が多いところです。
就業規則に故意又は重過失により会社に損害を与えた場合には社員が損害賠償義務を負う旨の規定がある場合は,通常は軽過失は免責される趣旨と解釈されるため,故意又は重過失の有無が問題となり,軽過失の有無は問題となりません。
社員に損害賠償義務が認められる場合であっても,賠償義務を負う損害額は損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度にとどまるため,故意によるものでない限り,社員に対し請求できる損害額は全体の一部にとどまることが多いというのが実情です。
労働契約の不履行について違約金を定め,損害賠償額を予定する契約をすることは禁止されているため(労基法16条),社員がミスした場合に賠償すべき損害額を予め定めても無効となります。
損害賠償金負担の合意が成立した場合は,「書面」で支払を約束させ,会社名義の預金口座に振り込ませるか現金で現実に支払わせて下さい。
賃金から天引きすると,賃金全額払いの原則(労基法24条1項)に違反するものとして,天引き額の支払いを余儀なくされることがあります。
賃金減額により実質的に損害賠償金を回収する方法は,賃金減額の有効性に問題が生じることがありますし,退職されてしまった場合には回収が困難となるといった問題もあり,正攻法とはいえません。
損害額が軽微な場合は,賞与額の抑制,昇給の停止等で対処すれば足りる場合もあります。
(5) 身元保証人に対する損害賠償請求
社員に対し損害賠償請求できる場合であっても,身元保証人に対し同額の損害賠償請求できるとは限りません。
裁判所は,身元保証人の損害賠償の責任及びその金額を定めるにつき社員の監督に関する会社の過失の有無,身元保証人が身元保証をなすに至った事由及びこれをなすに当たり用いた注意の程度,社員の任務又は身上の変化その他一切の事情を斟酌するものとされており(身元保証に関する法律5条),賠償額がさらに減額される可能性があります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
弁護士 藤田 進太郎
(1) 募集採用活動の重要性
業務上のミスを繰り返す社員を減らす一番の方法は,採用活動を慎重に行い,応募者の適性・能力等を十分に審査して基準を満たした者のみを採用することです。
採用活動の段階で手抜きをして,十分な審査をせずに採用していったのでは,担当業務が単純な内容でマニュアルや教育制度がよほど整備されているような会社でない限り,業務上のミスを減らすことはできないでしょう。
(2) 採用後の対応
採用後の社員による業務上のミスの対策としては,社員の適性に合った配置,人事異動,注意指導,教育,人事考課,保険加入によるリスク管理等が中心となります。
事業主は労働者を使用することにより得られる利益を享受する以上,損失についても事業主が負担すべきとの考え(報償責任)が一般的ですから,過失によるうっかりミスについては,損害賠償請求はなかなか認められませんし,認められたとしても損害額の一部にとどまり,実際の回収可能性も低いことが多いというのが実情です。
基本的には,業務上のミスによる損害を,当該社員に対する損害賠償請求で填補できるものとは考えるべきではありません。
(3) 証拠の確保
懲戒処分,解雇,損害賠償請求をするためには,どのようなミスを繰り返し,会社がどのような損害を被ったのかを具体的に説明できるようにしておく必要があります。
その都度記録を残し,始末書を取るなどして,証拠を残しておいて下さい。
(4) 損害賠償請求
社員の故意又は重過失により会社が損害を被った場合には,社員に対して損害賠償請求をすることができます。
社員に軽過失しかない場合に損害賠償請求できるかどうかは事案次第ですが,軽過失は免責される事例が多いところです。
就業規則に故意又は重過失により会社に損害を与えた場合には社員が損害賠償義務を負う旨の規定がある場合は,通常は軽過失は免責される趣旨と解釈されるため,故意又は重過失の有無が問題となり,軽過失の有無は問題となりません。
社員に損害賠償義務が認められる場合であっても,賠償義務を負う損害額は損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度にとどまるため,故意によるものでない限り,社員に対し請求できる損害額は全体の一部にとどまることが多いというのが実情です。
労働契約の不履行について違約金を定め,損害賠償額を予定する契約をすることは禁止されているため(労基法16条),社員がミスした場合に賠償すべき損害額を予め定めても無効となります。
損害賠償金負担の合意が成立した場合は,「書面」で支払を約束させ,会社名義の預金口座に振り込ませるか現金で現実に支払わせて下さい。
賃金から天引きすると,賃金全額払いの原則(労基法24条1項)に違反するものとして,天引き額の支払いを余儀なくされることがあります。
賃金減額により実質的に損害賠償金を回収する方法は,賃金減額の有効性に問題が生じることがありますし,退職されてしまった場合には回収が困難となるといった問題もあり,正攻法とはいえません。
損害額が軽微な場合は,賞与額の抑制,昇給の停止等で対処すれば足りる場合もあります。
(5) 身元保証人に対する損害賠償請求
社員に対し損害賠償請求できる場合であっても,身元保証人に対し同額の損害賠償請求できるとは限りません。
裁判所は,身元保証人の損害賠償の責任及びその金額を定めるにつき社員の監督に関する会社の過失の有無,身元保証人が身元保証をなすに至った事由及びこれをなすに当たり用いた注意の程度,社員の任務又は身上の変化その他一切の事情を斟酌するものとされており(身元保証に関する法律5条),賠償額がさらに減額される可能性があります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
弁護士 藤田 進太郎