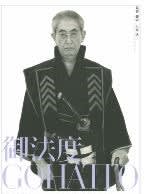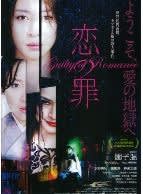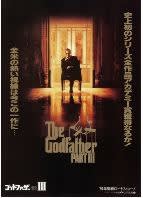大阪もそろそろ梅雨入りしそうな雰囲気。
「こ」が終わって「さ」の段に入っていきます。
「13デイズ」 2000年 アメリカ

監督 ロジャー・ドナルドソン
出演 ケヴィン・コスナー ブルース・グリーンウッド
スティーヴン・カルプ ディラン・ベイカー
ルシンダ・ジェニー ビル・スミトロヴィッチ
ケイトリン・ワックス ピーター・ホワイト
レン・キャリオー エリヤ・バスキン
ジョン・フォスター マイケル・フェアマン
ケリー・コネル ヘンリー・ストロジャー
ストーリー
1962年10月16日、ソ連がキューバに核兵器を持ち込んだという知らせがケネディ大統領のもとへ届く。
彼は直ちに緊急の危機管理チーム、国家安全保障会議緊急執行委員会、通称エクスコムを招集。
会議では空爆が推薦されたが、第三次世界大戦の勃発につながる危険があり、大統領はそれを避けたかった。
彼は本音を打ち明けられる弟の司法長官ロバート、親友の大統領特別補佐官ケネス・オドネルと共に、最善の手を探る。
空爆を迫る軍部を退けた大統領は、国連総会のため訪米したソ連外相と会談するが、外相はミサイルの存在を否定する従来の主張を繰り返すのみ。
大統領の疲労と緊張は限界に達しはじめるが、腹をくくった大統領は海上封鎖実施を発表。
しかしキューバのミサイルは発射準備を整えつつあり、大統領は止むなく29日に空爆の準備を指示。
さらに、爆撃目標の最終確認に飛び立った偵察機が撃墜されるという事件が起こる。
軍部は即時報復を進言し、事態は一触即発の状態に。
寸評
ケネディはこの翌年、ダラスにおいて疑惑の凶弾に倒れ、フルシチョフはこの危機処理が一つの伏線となってクレムリンを追われることになるのを我々は歴史を通じて知っている。
しかし、この時の当の当事者達はそんな歴史を知らず、国家の威信と世界平和を背負って、ぎりぎりの決断を行っていた事がドラマティックに描かれていて、歴史の裏側を見るような気分にさせてくれた。
オープニングはいい。タイトルと共にミサイル発射や原爆実験の映像が映し出され緊張感を醸し出す。
そして大統領特別補佐官オドネル家の朝食風景で始まるのだが、そこには子供の通知表を見せられ成績の悪さに文句を言いながら出かける主人公がいる。
ごく普通の家庭人であることの象徴的シーンで、その普通人が世界を震撼させ米国及び世界の命運を決定する瞬間に立ち会うことになるという宿命を上手く表していた。
大統領の権限があるように、それぞれの担当者にも権限があって、思惑によってその個人の権限を行使しようとする所などに偶然がもたらすことへの恐怖を感じる。
えてして歴史はそんなところから動くのかもしれないからだ。
軍部は悪人で、シビリアンは善人と言うのはいささか単純な区分けだとは思うが、それでも軍部のワナの様なものが描かれていて、職業軍人の思考は怖いものがある。
米国人にはチェコスロバキアの領土問題でドイツに譲歩し、ヒトラーの思い通りにされてしまったというミュンヘン協定のことが何回か語られる。
彼等にはその時の外交の失敗がトラウマになっているのだろうけど、その根深さは日本人の僕は実感として感じられない。
同様にピッグス湾事件でのキューバ侵攻失敗もトラウマになっているようで、どちらもこれからの決定に心理的影響を与えていそうなことがサラリと描かれていて興味深かった。
でもホワイトハウスの連中の家族だけが身分証と共にヘリポートから安全地帯に逃れる手はずが整えられていたとなれば、米国の一般国民は不満に思わないのだろうか?変な所に気をもんだ。
ジョン・F・ケネディ45歳、ロバート・ケネディ36歳、ケネス・オドネル38歳、この若い男達がアメリカのリーダーとして、世界的危機を回避したことにあらためて関心する次第だ。
ケネディ大統領のもとで、弟のロバートがあんなに重要な役割を果たしていたことに驚いた(僕の無知が招いた驚きなのだが)。
彼等のリーダーとしての指導力に、軍部が押さえ込まれていく所は、昨今のわが国の政治的指導力の無さを見るにつけ、まことにうらやましい限りと感ぜずにはおれない。
その大統領の権限とその権威に対する自負や、若きケネディが年配の幹部達を叱責するシーンを見ていると、自分達や子供の命を託すに足る人物を大統領選で選んでいる事が理解できる。
やはり日本も首相公選制をとるべきだろうと思ってしまうし、シビリアンコントロールは何があっても効かせなければならないなと感じてしまう内容だ。
時折モノクロ画面に変わるシーンがあるが、ドキュメンタリー効果を狙ったものだったのだろうか。
最高幹部の招集シーンやソ連外相グロムイコの登場シーンなど、重要人物の登場シーンだけかと思っていたが、そうでもなさそうでイマイチ意図が読み取れなかった。
しかしこのキューバ危機のことが、翌年の暗殺事件につながったのではないかとの疑念は残ったままで、同じくケビン・コスナーで以前作られた「JFK」がつながってくる。
ケネディの暗殺事件はやはりミステリーだ。
最後のナレーションは心打つし、全くもってその通りだと思わされる。
「こ」が終わって「さ」の段に入っていきます。
「13デイズ」 2000年 アメリカ

監督 ロジャー・ドナルドソン
出演 ケヴィン・コスナー ブルース・グリーンウッド
スティーヴン・カルプ ディラン・ベイカー
ルシンダ・ジェニー ビル・スミトロヴィッチ
ケイトリン・ワックス ピーター・ホワイト
レン・キャリオー エリヤ・バスキン
ジョン・フォスター マイケル・フェアマン
ケリー・コネル ヘンリー・ストロジャー
ストーリー
1962年10月16日、ソ連がキューバに核兵器を持ち込んだという知らせがケネディ大統領のもとへ届く。
彼は直ちに緊急の危機管理チーム、国家安全保障会議緊急執行委員会、通称エクスコムを招集。
会議では空爆が推薦されたが、第三次世界大戦の勃発につながる危険があり、大統領はそれを避けたかった。
彼は本音を打ち明けられる弟の司法長官ロバート、親友の大統領特別補佐官ケネス・オドネルと共に、最善の手を探る。
空爆を迫る軍部を退けた大統領は、国連総会のため訪米したソ連外相と会談するが、外相はミサイルの存在を否定する従来の主張を繰り返すのみ。
大統領の疲労と緊張は限界に達しはじめるが、腹をくくった大統領は海上封鎖実施を発表。
しかしキューバのミサイルは発射準備を整えつつあり、大統領は止むなく29日に空爆の準備を指示。
さらに、爆撃目標の最終確認に飛び立った偵察機が撃墜されるという事件が起こる。
軍部は即時報復を進言し、事態は一触即発の状態に。
寸評
ケネディはこの翌年、ダラスにおいて疑惑の凶弾に倒れ、フルシチョフはこの危機処理が一つの伏線となってクレムリンを追われることになるのを我々は歴史を通じて知っている。
しかし、この時の当の当事者達はそんな歴史を知らず、国家の威信と世界平和を背負って、ぎりぎりの決断を行っていた事がドラマティックに描かれていて、歴史の裏側を見るような気分にさせてくれた。
オープニングはいい。タイトルと共にミサイル発射や原爆実験の映像が映し出され緊張感を醸し出す。
そして大統領特別補佐官オドネル家の朝食風景で始まるのだが、そこには子供の通知表を見せられ成績の悪さに文句を言いながら出かける主人公がいる。
ごく普通の家庭人であることの象徴的シーンで、その普通人が世界を震撼させ米国及び世界の命運を決定する瞬間に立ち会うことになるという宿命を上手く表していた。
大統領の権限があるように、それぞれの担当者にも権限があって、思惑によってその個人の権限を行使しようとする所などに偶然がもたらすことへの恐怖を感じる。
えてして歴史はそんなところから動くのかもしれないからだ。
軍部は悪人で、シビリアンは善人と言うのはいささか単純な区分けだとは思うが、それでも軍部のワナの様なものが描かれていて、職業軍人の思考は怖いものがある。
米国人にはチェコスロバキアの領土問題でドイツに譲歩し、ヒトラーの思い通りにされてしまったというミュンヘン協定のことが何回か語られる。
彼等にはその時の外交の失敗がトラウマになっているのだろうけど、その根深さは日本人の僕は実感として感じられない。
同様にピッグス湾事件でのキューバ侵攻失敗もトラウマになっているようで、どちらもこれからの決定に心理的影響を与えていそうなことがサラリと描かれていて興味深かった。
でもホワイトハウスの連中の家族だけが身分証と共にヘリポートから安全地帯に逃れる手はずが整えられていたとなれば、米国の一般国民は不満に思わないのだろうか?変な所に気をもんだ。
ジョン・F・ケネディ45歳、ロバート・ケネディ36歳、ケネス・オドネル38歳、この若い男達がアメリカのリーダーとして、世界的危機を回避したことにあらためて関心する次第だ。
ケネディ大統領のもとで、弟のロバートがあんなに重要な役割を果たしていたことに驚いた(僕の無知が招いた驚きなのだが)。
彼等のリーダーとしての指導力に、軍部が押さえ込まれていく所は、昨今のわが国の政治的指導力の無さを見るにつけ、まことにうらやましい限りと感ぜずにはおれない。
その大統領の権限とその権威に対する自負や、若きケネディが年配の幹部達を叱責するシーンを見ていると、自分達や子供の命を託すに足る人物を大統領選で選んでいる事が理解できる。
やはり日本も首相公選制をとるべきだろうと思ってしまうし、シビリアンコントロールは何があっても効かせなければならないなと感じてしまう内容だ。
時折モノクロ画面に変わるシーンがあるが、ドキュメンタリー効果を狙ったものだったのだろうか。
最高幹部の招集シーンやソ連外相グロムイコの登場シーンなど、重要人物の登場シーンだけかと思っていたが、そうでもなさそうでイマイチ意図が読み取れなかった。
しかしこのキューバ危機のことが、翌年の暗殺事件につながったのではないかとの疑念は残ったままで、同じくケビン・コスナーで以前作られた「JFK」がつながってくる。
ケネディの暗殺事件はやはりミステリーだ。
最後のナレーションは心打つし、全くもってその通りだと思わされる。