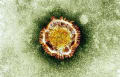猛烈な台風2号、4月としては観測史上最強 なぜ発達?

台風2号が、4月としては過去に類を見ない勢力に達しています。18日(日)の中心気圧は、気象庁の解析では895hPa、アメリカ軍による解析では888hPaとなりました。4月の時点で800hPa台の台風が発生したことは、これまで一度もありません。

台風2号の強さ
先週熱帯低気圧が日本の遥か南の海上で発生、その後パラオ周辺でゆっくりと発達し、16日(金)に「台風2号(国際名:スリゲ)」となりました。その後急激に勢力を増し、17日(土)には「非常に強い勢力」に、同日夜には「猛烈な」勢力となりました。
気象局と米軍による、18日時点の解析値は下記の通りです。その数値は目を見張るものがあります。
<気象庁>
・中心気圧 895hPa
・最大風速(10分平均) 60m/s
・カテゴリー「猛烈」(最強ランク)
<米軍合同台風警報センター>
・中心気圧 888hPa
・最大風速(1分平均) 85m/s
・カテゴリー「スーパータイフーン」(最強ランク)
※一般に中心気圧が低ければ低いほど、風は強くなります。
この時期としては初の800hPa台
一般に台風の活動がもっとも活発になる時期は、海水温が十分に温まる夏から秋の頃です。4月30日までに発達した台風の中で、これまで最強とされてきた台風は、910hPaまで中心気圧が下がった2015年の4号台風(メイサック)でした。
つまり今回の2号は、1月から4月に発達した台風としては観測史上最強、かつ初めて800hPa台に突入した台風となります。
なお1971年の5号(Amy)は、5月2日に中心気圧が890hPaまで下がりました。
フィリピンに上陸回避
18日15時発表の予想進路図 (出典: 気象庁)800hPa台の規模の台風は、一年を通してみても、そう発生するものではありません。その発生数は1951年以降で40個未満です。
それほど珍しい強さの台風が、物理的にも精神的にも台風への準備ができていない時期に襲ってきてはひとたまりもありません。
幸い2号はフィリピンへ上陸する恐れはなく、東の海上を北進する見込みです。ただ問題なのはその動きで、非常にゆっくりとしたペースで21日(水)頃までフィリピン近海にとどまります。同国では強風や大雨に加え、最大12メートルの高波も予想されています。
サイクロン「セロジャ」も記録的
2号が猛威を振るう北太平洋ですが、赤道を隔てた南太平洋では今月はじめに記録的なサイクロンが発生していました。サイクロン「セロジャ」です。インドネシアや東ティモールでは、月間降水量の6倍もの雨が降り、洪水や土砂災害などで200人以上が亡くなりました。
セロジャはその後11日(日)にオーストラリア西部を直撃しています。上陸時の勢力は「カテゴリー3」で、過去にオーストラリア南西部を直撃したサイクロンの中でも、最強の勢力での上陸となりました。カルバリでは、町の7割の住宅が損傷を受けたほどでした。
高い海水温とMJO
でも一体なぜ、太平洋では次々と恐ろしい嵐が発生しているのでしょうか。
一つ目の理由が高い海水温です。台風2号もセロジャも、30度近い温かい海の上で発達をしました。さらに表面だけではなく、海の比較的深い層でも温度が高くなっています。
二つ目の理由は、「マッデン・ジュリアン振動(MJO)」と呼ばれる現象です。これは移動する活発な雲のエリアで、インド洋をスタートして赤道に沿って東進し、30日から60日かけて地球を一周します。今月はこのMJOの影響で、西部太平洋で次々と雲が渦を巻きやすくなっていると考えられています。
まだ4月の時点で記録破りの台風が発生してしまいました。早いうちから台風の備えをしておくのも一考かと思います。