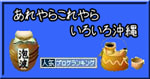きょうは2月14日火曜日。朝方は冷え込んだが、日が昇るに連れて青空が広がった。
朝刊を取りに外に出ると北寄りの西風が冷たかった。
余程興味のある出来事がない限り詳細に記事など読みはしない。見出しだけ目を通す。
8時半、予約をしている病院へ向う。肺炎予防注射である。
予防注射の所為で病気をする羽目になっては敵わないと、市から送ってきた受診票は机の引き出しに入れていた。
先月、NHKテレビで肺炎についての番組を観て気が変わった。
市から送られてきた受診票を探すが見当たらない。
あきらめかけていた時、引き出しの隅っこに隠れている奴をみつけた。
掛かりつけの病院に予約を入れた。それがきょうである。
風は冷たいが、風のない道になると防寒具は要らない。この数日、このような天気が続いている。
9時の予約だ。歩いても10分前には着くだろうと、散歩気分で2kmほどを路地から路地へと気分よく歩いた。
予防注射を終え、4000円を払って病院を出たのは10時半過ぎ。
ジャンバーを脱いで、帰路も歩く。途中で、モスバーガーのある十字路に出た。
一時期、運動公園を歩いて、その帰りにこの店でよくコーヒーを飲んだ事を思い出した。
一旦は通り過ぎたが、妙に懐かしくなって引き返した。
カウンターでトーストセットとあの時よく注文したスープを探したがメニューにない。
ストロガノフ・・・今(18日)、思い出したが、そのときは思い出せなかった。
40歳を超えた店長らしき男は「いや そんなスープは置いてません」という。
あれから10年以上も前のことだったのだ・・・と気付く。
店の佇まいもインテリアも変わっていない。きのうのことのように振舞っていた自分に愕然とした。
1時間余り、その店で寛いで帰宅した。
2時間余りかけて、毎日の楽しみにしている幾つかのブログを観る。
時だけは徒に過ぎて行く。
今日は18日。14日に手がけたブログに取り掛かる。
2月3日、新聞報道により金武町伊芸のコスモス畑に行った。
西原インターから沖縄自動車道に入り、屋嘉インターで降りた。
東海岸を北上すること10分余りで目的地に着いた。
農家の人が農閑期に植え始めたのが切っ掛けだとあったが、コスモス畑は、結構広かった。
沖縄ではコスモスは年中見ることができるといっていい。
しかし、本土で咲く秋のコスモスのように2m近くは伸びない。1m位である。
丁度この頃、北中城(
*城はグスクと読む)ではひまわり畑が満開であった。
ひまわりも大人の背丈ほどには生長しない。
それでも、1月、2月いえば、本土では真冬。最初に訪れたときには満開のひまわりに驚いたものだ。
先日、面白い木の実を見つけた。カニステルとトックリキワタ。
カニステルを最初にみたのは4月だったような気がする。
数年前、本島南部の南城市の一帯で開催されていたオープンガーデンを見に行った時のことだ。
住宅地の畑地に数本の黄色の実をつけた木を見つけた。
「あちこちに柿があるね。何という種類かな」と尋ねたら、
「ああ、カニステルだ。食用にできるが美味くない。蟹でも食べないで捨てるからカニステルと云うんだ」
歩きながらの会話を耳にしたのだろう。垣根越しに、品のいいお爺が、
「持っていくか。たくさん落ちている」と話しかけてきた。
指さす方をみると大きな木に黄色の実が鈴なりなっている。
十数個の実が根元に落ちている。お爺はその内の2,3個を拾い上げて
「皆、持って行ってもいいよ。多分、食べられないな。食うために植えているものは誰もおらん」
そういいながら、人の良い笑みを浮かべて差し出した。
暫くの間、お爺と案内役の友人は愉快に会話していた。方言丸出しだから、私にはわからない。
会話が一段落して、別れ際、「要らないか?」と差し出された。
「ううん、要らん」まるで付き合いのある者同士のようにそっけなく友人は断った。
寧ろ、聞いていた私の方が恐縮して、
「ありがとうございました」と頭を下げた。
これが沖縄である。素っ気ないが、それで相手には伝わっているのだ。
この呼吸が何とか理解できるまで、十数年はかかった。
しかし、ほんとうに素っ気なく応じたのか、そうでないのか、今でも区別がつかない。
カニステルについては、
ここで詳しく見ることが出来る。
カニステル

トックリキワタは花も散り、実だけがぶら下がっていた。
何とか実を手に入れて割ってみたいと思うが、割ってみたことはない。
中味は綿のようなものだという。
その内、落下するだろうと注意して見てはいるが・・・・・・。
トックリキワタ

*トミグスク「城」を沖縄では「グスク」と読む。「大城」(おおしろ)姓は沖縄では最も多い姓である。
過っては、「ウフグスク」と呼んでいたらしい。「ウフ」は方言で「大きい」という意味だ。
「豊見城」も、今では「とみしろ」と読む。しかし、本来は「トミグスク」。
何でも、沖縄から甲子園に豊見城高校が出場したとき、「トミグスクコウコウ」をNHKのアナウンサーが「トミシロコウコウ」と云ったことから「トミシロ」になったらしい。
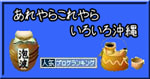 よろしければクリックお願いします。
よろしければクリックお願いします。
 上の絵をクリックよろしくお願いします。
上の絵をクリックよろしくお願いします。 上の絵をクリックよろしくお願いします。
上の絵をクリックよろしくお願いします。