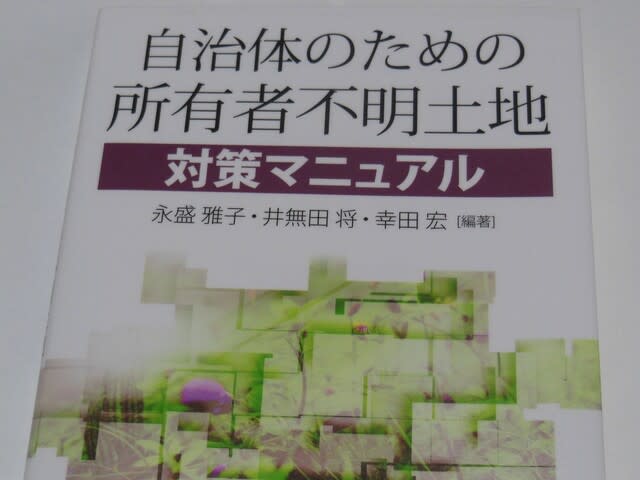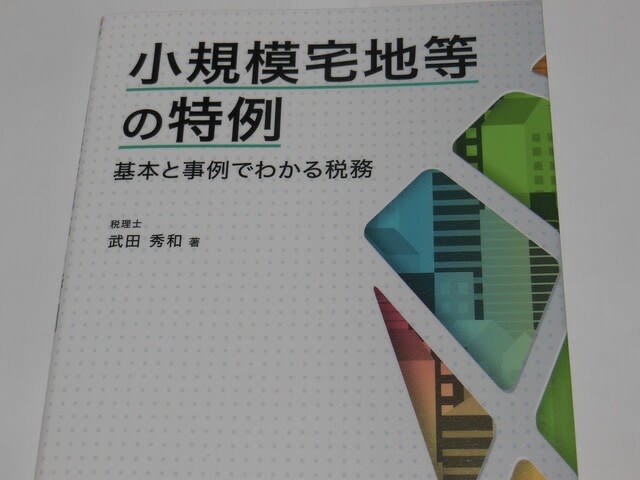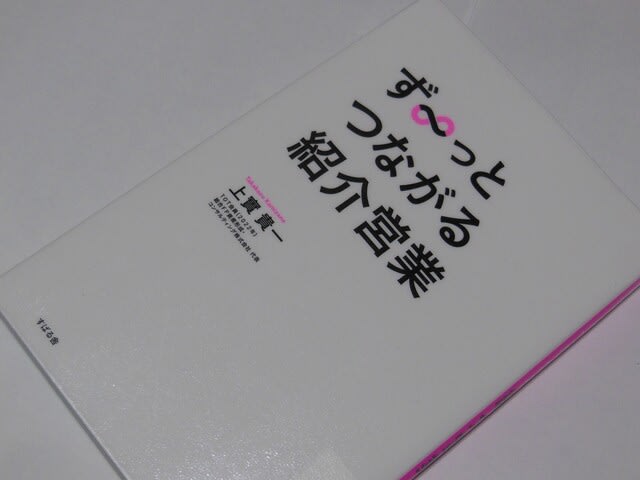1年のうち300日以上和牛を食べる生活を続けているという著者が、牛肉のブランド、流通、冷凍・熟成、調理・焼き方等について解説した本。
著者の紹介が「ふつうの会社員」というのが好感します。詳しくなるとコンサルタントとか何やらカタカナのもっともらしい肩書きを名乗る人が多い中で、どこか潔さを感じます。しかも、魚屋の長男って…
さまざまな蘊蓄の中で、おいしい牛肉を食べるという観点からは、かつてはA5の牛は本当においしかったが今では黒毛和牛の半分以上はA5でA5であればおいしいとは限らなくなっている(38~41ページ)、牛肉の旬は11月から2月くらいで12月がピーク(60~62ページ)、焼肉は火の入れ方で大きく味が変わる(169~178ページ)とかが、読みどころというか、勉強になりました。

小池克臣 クロスメディア・パブリッシング 2024年3月1日発行

著者の紹介が「ふつうの会社員」というのが好感します。詳しくなるとコンサルタントとか何やらカタカナのもっともらしい肩書きを名乗る人が多い中で、どこか潔さを感じます。しかも、魚屋の長男って…
さまざまな蘊蓄の中で、おいしい牛肉を食べるという観点からは、かつてはA5の牛は本当においしかったが今では黒毛和牛の半分以上はA5でA5であればおいしいとは限らなくなっている(38~41ページ)、牛肉の旬は11月から2月くらいで12月がピーク(60~62ページ)、焼肉は火の入れ方で大きく味が変わる(169~178ページ)とかが、読みどころというか、勉強になりました。

小池克臣 クロスメディア・パブリッシング 2024年3月1日発行