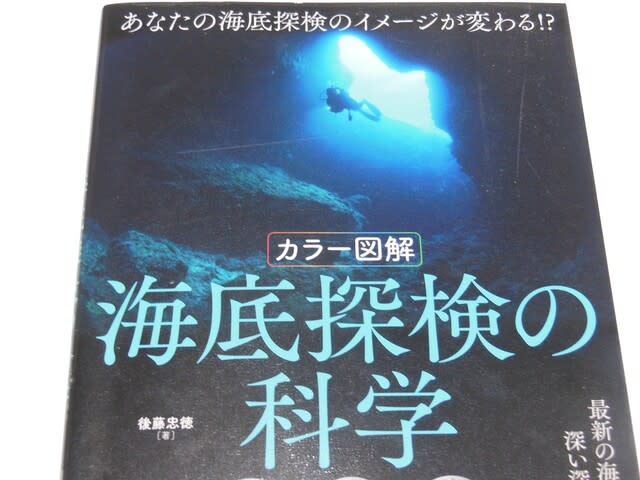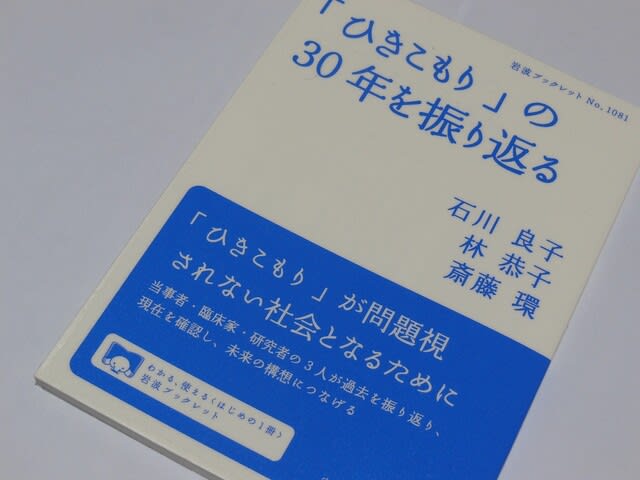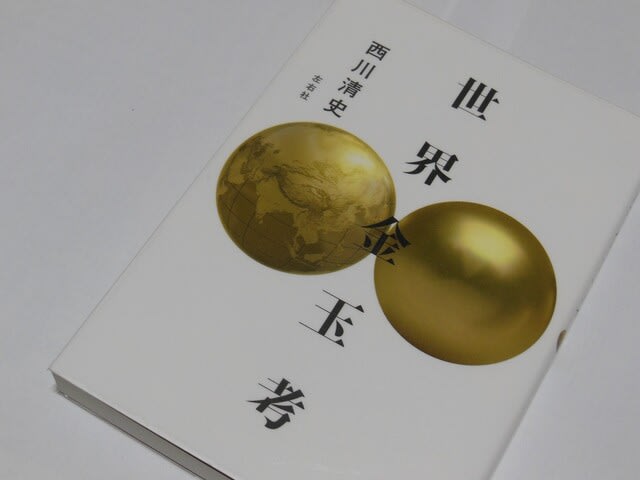海底資源(海底熱水鉱床、レアアース泥、コバルトリッチクラスト、メタンハイドレート等)探査を中心とする海底探査の技術と探査の実情の説明及び海底探査や海洋調査でどんなことがわかるかなどを解説した本。
電磁波が速やかに減衰するために届かない水中で、光も届かず高圧の環境となる深海底での探査をするために技術的にどのような問題があり、それをどう乗り越えてきたかの説明は、知的好奇心に訴えるものがあり、勉強になりました。
深海底のことは未解明のことが多く、海底探査・海洋調査によってさまざまなことがわかる期待があることは理解しますが、どうも全体としては、JAMSTEC(海洋研究開発機構)の研究活動の必要性をPRする本という色彩が強く感じられました(著者は現職は大学教授ですが、元JAMSTEC技術研究主任)。

後藤忠徳 技術評論社 2023年7月11日発行
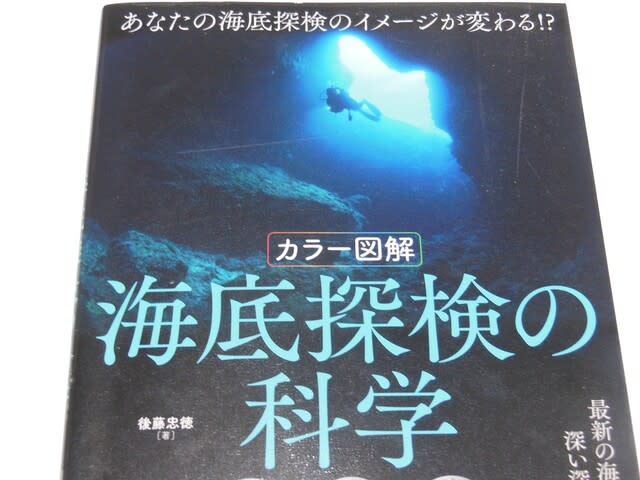
電磁波が速やかに減衰するために届かない水中で、光も届かず高圧の環境となる深海底での探査をするために技術的にどのような問題があり、それをどう乗り越えてきたかの説明は、知的好奇心に訴えるものがあり、勉強になりました。
深海底のことは未解明のことが多く、海底探査・海洋調査によってさまざまなことがわかる期待があることは理解しますが、どうも全体としては、JAMSTEC(海洋研究開発機構)の研究活動の必要性をPRする本という色彩が強く感じられました(著者は現職は大学教授ですが、元JAMSTEC技術研究主任)。

後藤忠徳 技術評論社 2023年7月11日発行