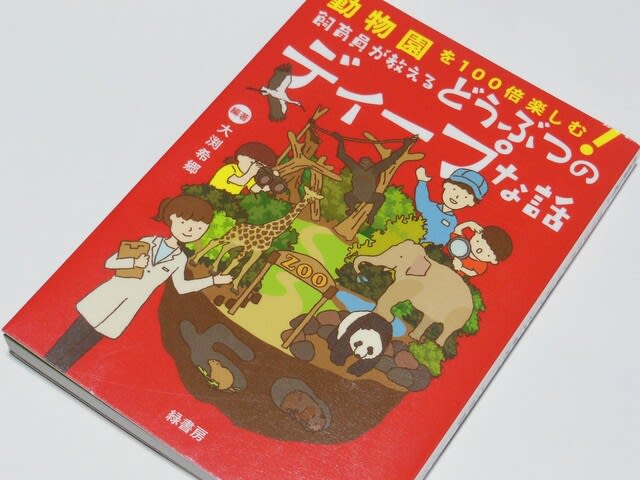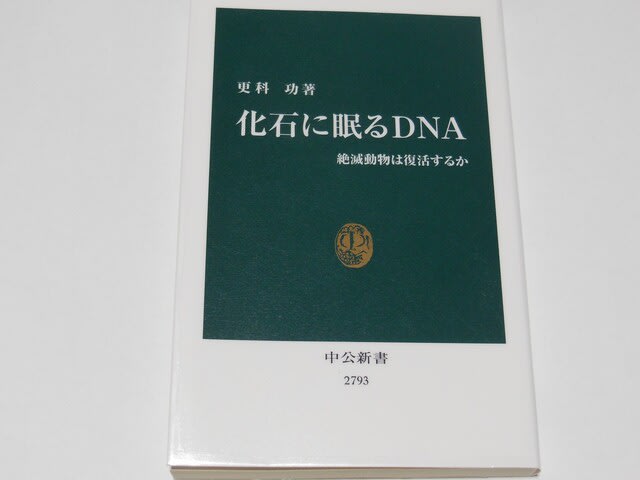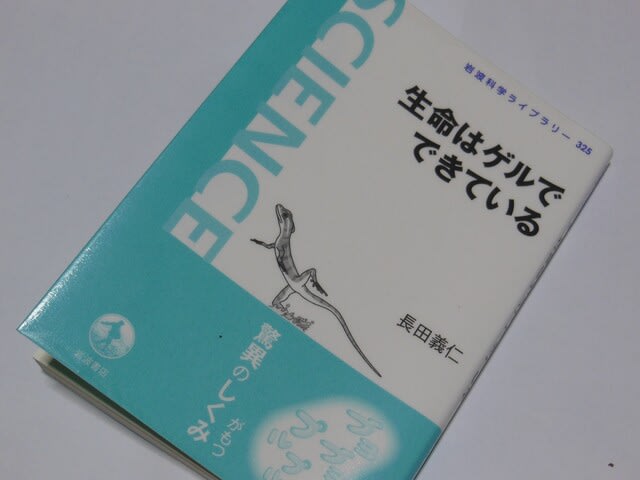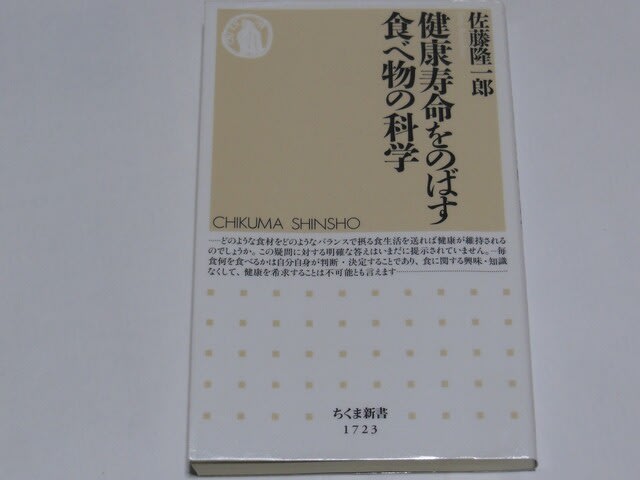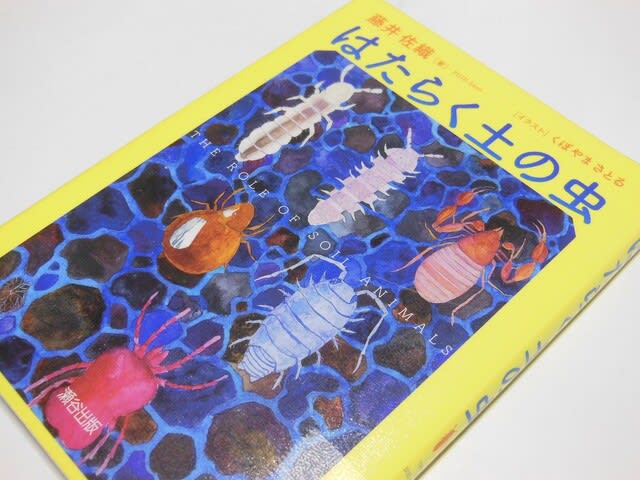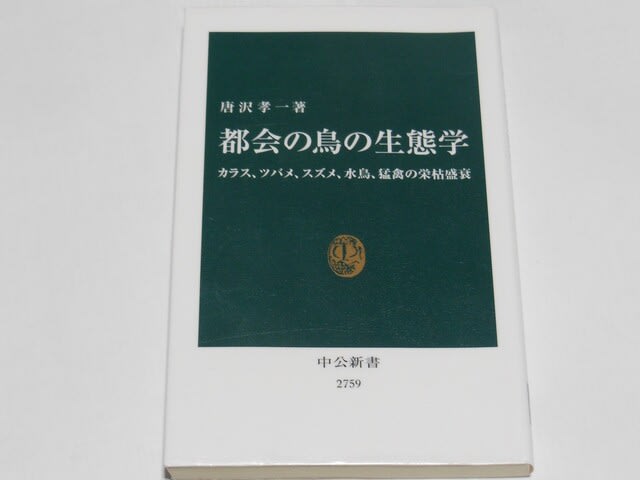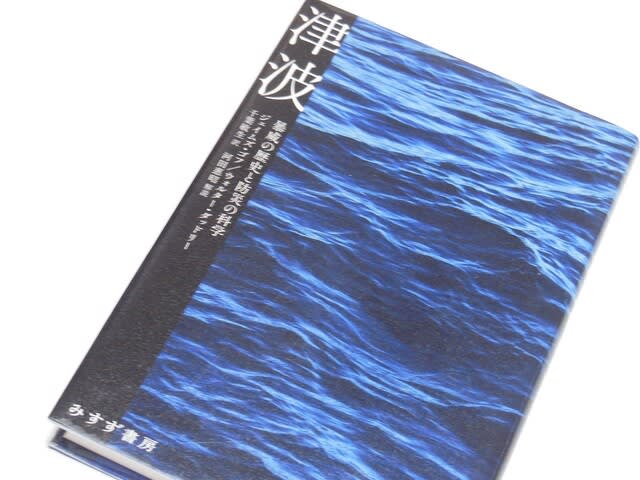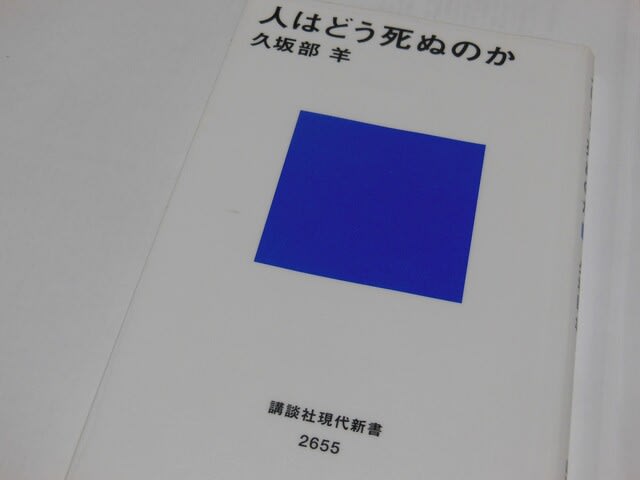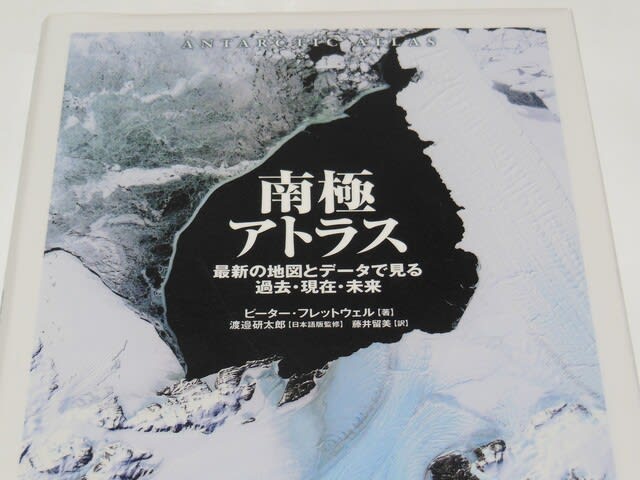動物園などで見られる動物51種について、概ね3ページで、その生態や希少性(絶滅危惧の程度)等を解説した本。
動物園の飼育員の話が中心ということからか編著者の関心からか、繁殖(発情期や交尾の方法、妊娠期間、1度の出産での出生数や出産の頻度、その後の子育て)と寿命の話題と餌・食事、飼育での注意点の話題が中心となっています。
アルマジロの陰茎が全長の2/3に及ぶ(13ページ。そう書いていながら、「交尾では体長の約半分ほどにまで膨らんできます」って、謎)とか、アルマジロ類の多くは1日に16~18時間眠ります(12ページ)とか、トリビアが満載です。
トナカイは硬い餌を与え続けると歯が著しく摩耗したり欠損する(41ページ)、ゴリラに野生でない人が食べる甘い果実をやるのは虫歯の元(51ページ)など、餌についての苦労話もいろいろとあり、興味深く読めました。

大渕希郷編著 緑書房 2023年7月10日発行
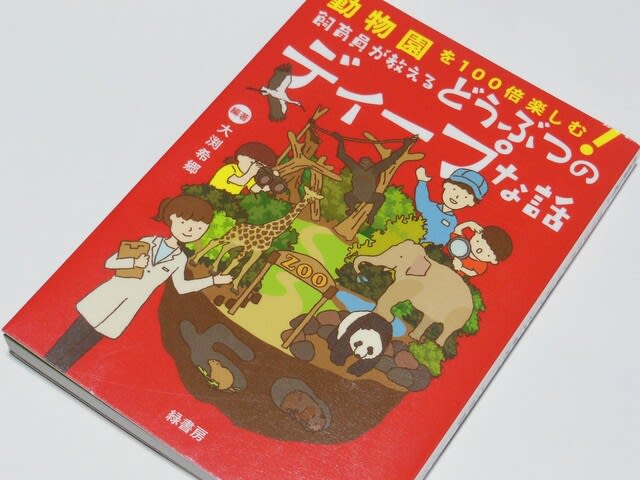
動物園の飼育員の話が中心ということからか編著者の関心からか、繁殖(発情期や交尾の方法、妊娠期間、1度の出産での出生数や出産の頻度、その後の子育て)と寿命の話題と餌・食事、飼育での注意点の話題が中心となっています。
アルマジロの陰茎が全長の2/3に及ぶ(13ページ。そう書いていながら、「交尾では体長の約半分ほどにまで膨らんできます」って、謎)とか、アルマジロ類の多くは1日に16~18時間眠ります(12ページ)とか、トリビアが満載です。
トナカイは硬い餌を与え続けると歯が著しく摩耗したり欠損する(41ページ)、ゴリラに野生でない人が食べる甘い果実をやるのは虫歯の元(51ページ)など、餌についての苦労話もいろいろとあり、興味深く読めました。

大渕希郷編著 緑書房 2023年7月10日発行