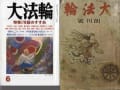19世紀ドイツの哲学者ニーチェの「アンチクリスト」の現代語訳です。これまで哲学書と言えば難しい哲学用語のオンパレードで、なかなか最後まで読破するのに骨が折れたものですが、この本はとっても分かりやすく、ほんの3時間もあればじっくりと読めてしまう作品。
「名著、現代に復活、世界を滅ぼす一神教の恐怖」と帯にある。アメリカ大統領の演説などにさりげなく神という言葉が使われるように、他を認めない唯一の神への信仰が国際間の紛争に利用されていることを意識した復刻なのであろう。
題名も目を引くが、帯の背表紙には「仏教のすばらしさを発見」とある。読んでみるとニーチェは仏教を絶賛している。仏教ほど理知的で現実に正面から向き合っている宗教はない。真に幸福のための具体的な道しるべを示し、実行しているという。
ニーチェはこの著作の中で、仏教の素晴らしいところをこう記している。『仏教はキリスト教に比べれば、100倍くらい現実的です。仏教のよいところは「問題は何か」と客観的に冷静に考える伝統を持っているところです。・・・そういう意味では仏教は、歴史的に見て、ただ一つのきちんと論理的にものを考える宗教と言っていいでしょう。』
そして仏教が注意していることを二つあげています。『一つは感受性をあまりに敏感にすること』『もう一つは、何でもかんでも精神的なものと考えたり、難しい概念を使ったり、論理的な考え方ばかりしている世界の中にずっといること』
仏教は様々なことに気づくことを教えてはいるが、そこで終わり、その先にあれこれ考えない、つまりそこから怨み、ねたみ、おごり、怒りを高じさせないことを大事にしている。また、あまりに頭だけで考えることも推奨していない。修行実践が大切だと教えられている。この辺りのことをニーチェは指摘しているのだと思われる。
また『重要なのは、仏教が上流階級や知識階級から生まれたことです。仏教では、心の晴れやかさ、静けさ、無欲といったものが最高の目標になりました。そして大切なことは、そういった目標は達成されるためにあり、そして実際に達成されるということです。そもそも仏教は、完全なものを目指して猛烈に突き進んでいくタイプの宗教ではありません。普段の状態が、宗教的にも完全なのです』
『ところがキリスト教の場合は、負けた者やおさえつけられてきた者たちの不満がその土台となっています。つまり、キリスト教は最下層民の宗教なのです。・・・キリスト教では最高の目標に達することは絶対に出来ない仕組みになっているのです』
『仏教は良い意味で歳をとった、善良で温和な、きわめて精神化された種族の宗教です。ヨーロッパはまだまだ仏教を受け入れるまでに成熟していません。仏教は人々を平和でほがらかな世界へ連れていき、精神的にも肉体的にも健康にさせます。
キリスト教は野蛮人を支配しようとしますが、その方法は彼らを病弱にすることによってです。相手を弱くすることが、敵を飼い慣らしたり、文明化させるための、キリスト教的処方箋なのです』
まだまだ引用したい部分が沢山あるがこの辺りに留めておきたい。あまりに的確な指摘をされているのではないかと思う。世界にもたらされている現代の様々な紛争の原因がどのあたりに隠されているのかもこの著作から伺われる。実に示唆に富んだ名著である。ぜひ読んでみられることをお勧めする。
ところで、私は何もキリスト教をここで断罪する気は毛頭無い。それよりも実は、現実には私たちの仏教がキリスト教化してはいないかと懸念しているのだ。信仰ばかりを語ってはいまいか。読経、写経もよいがニーチェの唱える仏教の本来あるべき姿勢、論理的に冷静にものを考える伝統をおろそかにしてはいないか。
教えの何たるかも知らせずに、ただ手を合わすことばかりを強要してはいないかと問いたい。ニーチェは、ものを信じ込む人は価値を判断することが出来ず、外のことも自分のことも分からず牢屋に入っているのと同じだとも指摘する。
ニーチェの時代にはヨーロッパに仏教は浸透していなかったであろう。しかし現代のヨーロッパには、沢山の仏教信奉者がいて僧団を供養し真剣に学び修養に励む人々か少なからず居る。私たち日本人は仏教徒という意識も希薄で、この本の訳者(適菜収氏)も指摘しているが、誰もが知らず知らずのうちにキリスト教的考え方、行動パターンの中に巻き込まれているのではないかとも危惧する。
自己の価値観を他に押しつけて、恩をきせ利益を貪るということの愚かな行為を、ただ称賛したり羨望するのではなく、「やはりそれはおかしいだろ、そんなことしてたら地獄行きだよ」という昔の日本人が普通に持っていた素直な感情、正論を取り戻したい。ニーチェも指摘するように仏教は万民の肉体的精神的健康を目指す教えなのだから。
「名著、現代に復活、世界を滅ぼす一神教の恐怖」と帯にある。アメリカ大統領の演説などにさりげなく神という言葉が使われるように、他を認めない唯一の神への信仰が国際間の紛争に利用されていることを意識した復刻なのであろう。
題名も目を引くが、帯の背表紙には「仏教のすばらしさを発見」とある。読んでみるとニーチェは仏教を絶賛している。仏教ほど理知的で現実に正面から向き合っている宗教はない。真に幸福のための具体的な道しるべを示し、実行しているという。
ニーチェはこの著作の中で、仏教の素晴らしいところをこう記している。『仏教はキリスト教に比べれば、100倍くらい現実的です。仏教のよいところは「問題は何か」と客観的に冷静に考える伝統を持っているところです。・・・そういう意味では仏教は、歴史的に見て、ただ一つのきちんと論理的にものを考える宗教と言っていいでしょう。』
そして仏教が注意していることを二つあげています。『一つは感受性をあまりに敏感にすること』『もう一つは、何でもかんでも精神的なものと考えたり、難しい概念を使ったり、論理的な考え方ばかりしている世界の中にずっといること』
仏教は様々なことに気づくことを教えてはいるが、そこで終わり、その先にあれこれ考えない、つまりそこから怨み、ねたみ、おごり、怒りを高じさせないことを大事にしている。また、あまりに頭だけで考えることも推奨していない。修行実践が大切だと教えられている。この辺りのことをニーチェは指摘しているのだと思われる。
また『重要なのは、仏教が上流階級や知識階級から生まれたことです。仏教では、心の晴れやかさ、静けさ、無欲といったものが最高の目標になりました。そして大切なことは、そういった目標は達成されるためにあり、そして実際に達成されるということです。そもそも仏教は、完全なものを目指して猛烈に突き進んでいくタイプの宗教ではありません。普段の状態が、宗教的にも完全なのです』
『ところがキリスト教の場合は、負けた者やおさえつけられてきた者たちの不満がその土台となっています。つまり、キリスト教は最下層民の宗教なのです。・・・キリスト教では最高の目標に達することは絶対に出来ない仕組みになっているのです』
『仏教は良い意味で歳をとった、善良で温和な、きわめて精神化された種族の宗教です。ヨーロッパはまだまだ仏教を受け入れるまでに成熟していません。仏教は人々を平和でほがらかな世界へ連れていき、精神的にも肉体的にも健康にさせます。
キリスト教は野蛮人を支配しようとしますが、その方法は彼らを病弱にすることによってです。相手を弱くすることが、敵を飼い慣らしたり、文明化させるための、キリスト教的処方箋なのです』
まだまだ引用したい部分が沢山あるがこの辺りに留めておきたい。あまりに的確な指摘をされているのではないかと思う。世界にもたらされている現代の様々な紛争の原因がどのあたりに隠されているのかもこの著作から伺われる。実に示唆に富んだ名著である。ぜひ読んでみられることをお勧めする。
ところで、私は何もキリスト教をここで断罪する気は毛頭無い。それよりも実は、現実には私たちの仏教がキリスト教化してはいないかと懸念しているのだ。信仰ばかりを語ってはいまいか。読経、写経もよいがニーチェの唱える仏教の本来あるべき姿勢、論理的に冷静にものを考える伝統をおろそかにしてはいないか。
教えの何たるかも知らせずに、ただ手を合わすことばかりを強要してはいないかと問いたい。ニーチェは、ものを信じ込む人は価値を判断することが出来ず、外のことも自分のことも分からず牢屋に入っているのと同じだとも指摘する。
ニーチェの時代にはヨーロッパに仏教は浸透していなかったであろう。しかし現代のヨーロッパには、沢山の仏教信奉者がいて僧団を供養し真剣に学び修養に励む人々か少なからず居る。私たち日本人は仏教徒という意識も希薄で、この本の訳者(適菜収氏)も指摘しているが、誰もが知らず知らずのうちにキリスト教的考え方、行動パターンの中に巻き込まれているのではないかとも危惧する。
自己の価値観を他に押しつけて、恩をきせ利益を貪るということの愚かな行為を、ただ称賛したり羨望するのではなく、「やはりそれはおかしいだろ、そんなことしてたら地獄行きだよ」という昔の日本人が普通に持っていた素直な感情、正論を取り戻したい。ニーチェも指摘するように仏教は万民の肉体的精神的健康を目指す教えなのだから。