小さな子どもが英語を学ぶ意義はどこにあるのだろうか。
町の図書館では、月に一度国際交流員の人が幼稚園児~小学生を対象とした英語の本の読み聞かせをしている。保育園・幼稚園の年長クラスでも行っている。
私は5歳の娘を連れて3回ほど参加したことがあるのだが、どの子も英語の単語をよく知っている。絵を見せるとちゃんと、「エレファント」「マンキー」「ラビット」などと答えるのである。(この程度は日本語の延長なのか?)
だが、少しでもフレーズになると、全く反応しないのである。ポカーンと口を開けた状態から退屈なのでモソモソ動き出すまで時間はかからない。交流員は日本語が話せるが十分ではない。周りの母親たちは子どもを静かにさせようとはするが、交流員を手助けするまでには至らない。
国際交流員の任期は1年である。
どこの自治体もそうなんだろうか?1年てあまりにも短い気がする。交流員は「日本で働いたことがある」という経験にはなるだろうが、1年でできることは少ないし、交流員への援助も手薄だと思う。いくらもらってるのか知らないが、予算の無駄遣いのように思える…
どこの自治体もやっているから、予算がついているから、以外に理由があるのだろうか。
小学生の英語必修化に関しても賛否両論あったが、結局3年生からですか?始まってますが、これだって、予算の無駄遣い、国語の授業を増やした方が子どものためになる…なんてことになってるんじゃないですか?
図書館の子ども向けのコーナーに、「世界のともだち」というシリーズがあります。パレスチナとインドのを読んでみると、パレスチナの10歳の女の子は、キリスト教系の学校で、国語(アラビア語)の他に英語とフランス語も習っています。(他の学科は算数、科学、社会、地理となってます)インドの男の子は新興富裕層で、有名な私立校に通っており、英語とヒンディー語を習っています。ユニークなのは暗算の学科があることです。他にも環境・地球科学という学科があって週5時間も費やしています。この男の子はパンジャブ地方の出身なのでパンジャブ語も話しますが、一番得意なのは英語だそうです。
なんか彼我の感強し…
グローバル人材育成のためとか、英語できちんと自己主張したりコミュニケーションを取ったりできるようにするため、とかが英語早期教育化の理由だったような気がしますが。日本語が先だろうとか、主張するだけの考えがないんじゃ英語を話せたって意味ないだろうとか、という反論もありましたね。そう言いたくなる気持ちもわかります。
英語がペラペラという表現があるとおり、日本人にとって外国語というのは、ペラペラっとしゃべるのがかっこいいという軽薄さがどうしてもあるようです。発音の悪い人やカタカナ英語っぽい人は中身以前に英ぺとは認められていなかったりします。
小学校でどのような授業を行っているのか知りませんが、英語を話す人はどこに住んでいる人なのか、どんな人種・民族の人なのか、その人たちはどんな肌の色をしているのか、どうして英語ではそのように表現するのか、そういったことを教えることこそが英語教育の意義だと思います。小さいうちからネイティブイングリッシュに接してればたしかにカッコ悪いジャパニーズイングリッシュじゃなくてカッコイイほんものっぽい英語を話すようになるかもしれませんが、日本人が目指しているのはそういうことなのでしょうか?
わがやの5歳の娘は、ユニセフのカレンダーに写っているアフリカの男の子を見て「この子、黒いお顔やね。どうして肌色じゃないが?」と聞いてきます。自分の肌の色が肌色だと思ってるんですね。間違いではありませんが…そのとき疑問に思いました。絵の具の「肌色」って、外国ではどのように表現されているんだろうって。娘に肌の色について説明はしてみましたが、わからないかんじでした。
せっかくの英語教育ですから、教える先生もその意義を考えて、自分なりに工夫して楽しんでやってもらいたいです。
子どもの中に流暢に英語を話す子がいたからってひるまないでほしいです。英ぺを目指すのが目的ではないのですから。負けるな先生。
町の図書館では、月に一度国際交流員の人が幼稚園児~小学生を対象とした英語の本の読み聞かせをしている。保育園・幼稚園の年長クラスでも行っている。
私は5歳の娘を連れて3回ほど参加したことがあるのだが、どの子も英語の単語をよく知っている。絵を見せるとちゃんと、「エレファント」「マンキー」「ラビット」などと答えるのである。(この程度は日本語の延長なのか?)
だが、少しでもフレーズになると、全く反応しないのである。ポカーンと口を開けた状態から退屈なのでモソモソ動き出すまで時間はかからない。交流員は日本語が話せるが十分ではない。周りの母親たちは子どもを静かにさせようとはするが、交流員を手助けするまでには至らない。
国際交流員の任期は1年である。
どこの自治体もそうなんだろうか?1年てあまりにも短い気がする。交流員は「日本で働いたことがある」という経験にはなるだろうが、1年でできることは少ないし、交流員への援助も手薄だと思う。いくらもらってるのか知らないが、予算の無駄遣いのように思える…
どこの自治体もやっているから、予算がついているから、以外に理由があるのだろうか。
小学生の英語必修化に関しても賛否両論あったが、結局3年生からですか?始まってますが、これだって、予算の無駄遣い、国語の授業を増やした方が子どものためになる…なんてことになってるんじゃないですか?
図書館の子ども向けのコーナーに、「世界のともだち」というシリーズがあります。パレスチナとインドのを読んでみると、パレスチナの10歳の女の子は、キリスト教系の学校で、国語(アラビア語)の他に英語とフランス語も習っています。(他の学科は算数、科学、社会、地理となってます)インドの男の子は新興富裕層で、有名な私立校に通っており、英語とヒンディー語を習っています。ユニークなのは暗算の学科があることです。他にも環境・地球科学という学科があって週5時間も費やしています。この男の子はパンジャブ地方の出身なのでパンジャブ語も話しますが、一番得意なのは英語だそうです。
なんか彼我の感強し…
グローバル人材育成のためとか、英語できちんと自己主張したりコミュニケーションを取ったりできるようにするため、とかが英語早期教育化の理由だったような気がしますが。日本語が先だろうとか、主張するだけの考えがないんじゃ英語を話せたって意味ないだろうとか、という反論もありましたね。そう言いたくなる気持ちもわかります。
英語がペラペラという表現があるとおり、日本人にとって外国語というのは、ペラペラっとしゃべるのがかっこいいという軽薄さがどうしてもあるようです。発音の悪い人やカタカナ英語っぽい人は中身以前に英ぺとは認められていなかったりします。
小学校でどのような授業を行っているのか知りませんが、英語を話す人はどこに住んでいる人なのか、どんな人種・民族の人なのか、その人たちはどんな肌の色をしているのか、どうして英語ではそのように表現するのか、そういったことを教えることこそが英語教育の意義だと思います。小さいうちからネイティブイングリッシュに接してればたしかにカッコ悪いジャパニーズイングリッシュじゃなくてカッコイイほんものっぽい英語を話すようになるかもしれませんが、日本人が目指しているのはそういうことなのでしょうか?
わがやの5歳の娘は、ユニセフのカレンダーに写っているアフリカの男の子を見て「この子、黒いお顔やね。どうして肌色じゃないが?」と聞いてきます。自分の肌の色が肌色だと思ってるんですね。間違いではありませんが…そのとき疑問に思いました。絵の具の「肌色」って、外国ではどのように表現されているんだろうって。娘に肌の色について説明はしてみましたが、わからないかんじでした。
せっかくの英語教育ですから、教える先生もその意義を考えて、自分なりに工夫して楽しんでやってもらいたいです。
子どもの中に流暢に英語を話す子がいたからってひるまないでほしいです。英ぺを目指すのが目的ではないのですから。負けるな先生。












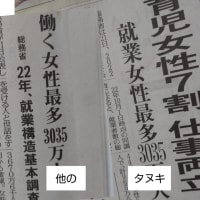
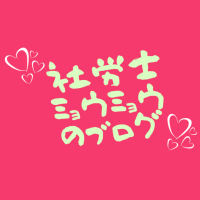
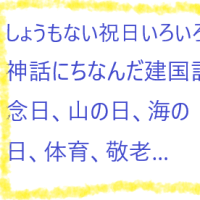




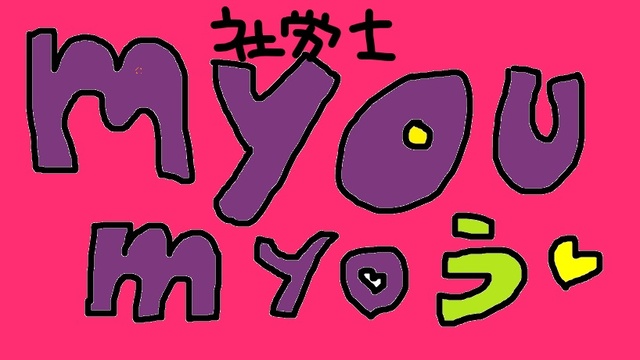

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます