会報表紙集(1-7号までは冊子体ではないので、表紙はありません)
2008年
8号 はじめての海指導員養成講習会の様子。
はじめての海指導員養成講習会の様子。
9号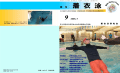 ある意味着衣泳講習会の目玉であった背面からの転落の練習。平成26年度からはテキストからこのメニューがなくなる。
ある意味着衣泳講習会の目玉であった背面からの転落の練習。平成26年度からはテキストからこのメニューがなくなる。
10号 高知県消防防災航空隊と地元の住民との合同水難救助訓練の様子で、このころから航空機救助との連携を重点的に研究し始めた。
高知県消防防災航空隊と地元の住民との合同水難救助訓練の様子で、このころから航空機救助との連携を重点的に研究し始めた。
11号 会長表彰に喜びの様子を送っていただいたので表紙に掲載。
会長表彰に喜びの様子を送っていただいたので表紙に掲載。
2009年
12号 幼児着衣泳が手探りで始まった頃。
幼児着衣泳が手探りで始まった頃。
13号 養護学校でも試験的に実施するところがでてきて、その効果に驚きの声が寄せられた。
養護学校でも試験的に実施するところがでてきて、その効果に驚きの声が寄せられた。
14号 さまざまな消防の装備品で浮いてみた様子
さまざまな消防の装備品で浮いてみた様子
15号 横浜消防と共同で研究を実施した。遭難した漁師を救助する想定。
横浜消防と共同で研究を実施した。遭難した漁師を救助する想定。
2010年
16号 高知県にて漁船から転落して背浮きで救助を待つ想定の研究のひとコマ。
高知県にて漁船から転落して背浮きで救助を待つ想定の研究のひとコマ。
17号 東松島市の月浜海水浴場で、漁師が水難に遭ったことを想定した海上保安庁との合同研究の様子。まさか1年もしないうちにここを津波が襲うとは。
東松島市の月浜海水浴場で、漁師が水難に遭ったことを想定した海上保安庁との合同研究の様子。まさか1年もしないうちにここを津波が襲うとは。
18号 冷水に着衣状態で背浮きを実施するときの負荷について研究をしている様子。水温は10℃であり、この状況が東日本大震災で再現されることに。
冷水に着衣状態で背浮きを実施するときの負荷について研究をしている様子。水温は10℃であり、この状況が東日本大震災で再現されることに。
19号 着衣泳もいよいよ国際的に展開が始まった。
着衣泳もいよいよ国際的に展開が始まった。
2011年
20号 津波想定で高知県消防防災航空隊と共同で研究をしている様子。ある決められた時間で何人の人を水面から救助できるのか、調査した。この回転翼が数ヵ月後に震災でこの研究結果をもとに活躍することになる。
津波想定で高知県消防防災航空隊と共同で研究をしている様子。ある決められた時間で何人の人を水面から救助できるのか、調査した。この回転翼が数ヵ月後に震災でこの研究結果をもとに活躍することになる。
21号 津波で流された安倍志摩子指導員が流されながら送信したメール。
津波で流された安倍志摩子指導員が流されながら送信したメール。
22号 国際会議で日本の着衣泳を世界に広めた。
国際会議で日本の着衣泳を世界に広めた。
23号 浮世絵に描かれた着衣泳。命を守るというよりは。。。
浮世絵に描かれた着衣泳。命を守るというよりは。。。
2012年
24号 がっちりした受講生が並んでプール洗濯機。
がっちりした受講生が並んでプール洗濯機。
25号 着衣泳ビデオの収録風景。すでに14年前。
着衣泳ビデオの収録風景。すでに14年前。
26号 津波で流された安倍志摩子指導員が学術講演会で報告。
津波で流された安倍志摩子指導員が学術講演会で報告。
27号 水難学会主催の始めての国際指導員養成講習会の様子
水難学会主催の始めての国際指導員養成講習会の様子
2013年
28号 水難学会主催の初めての国外・スリランカにおける指導員養成講習会の様子
水難学会主催の初めての国外・スリランカにおける指導員養成講習会の様子
29号 震災をうけて、水面からの這い上がりを実技の重点項目とした。
震災をうけて、水面からの這い上がりを実技の重点項目とした。
30号 がっちりした受講生が並んで点呼。
がっちりした受講生が並んで点呼。
31号 海指導員養成講習会の様子。8号に比べて内容が格段に充実してきている。
海指導員養成講習会の様子。8号に比べて内容が格段に充実してきている。
2014年
32号 タイで行われた国際ワークショップと指導員養成講習会の様子。英語とタイ語を交えて実技が進行した。
タイで行われた国際ワークショップと指導員養成講習会の様子。英語とタイ語を交えて実技が進行した。
2008年
8号
 はじめての海指導員養成講習会の様子。
はじめての海指導員養成講習会の様子。9号
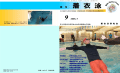 ある意味着衣泳講習会の目玉であった背面からの転落の練習。平成26年度からはテキストからこのメニューがなくなる。
ある意味着衣泳講習会の目玉であった背面からの転落の練習。平成26年度からはテキストからこのメニューがなくなる。10号
 高知県消防防災航空隊と地元の住民との合同水難救助訓練の様子で、このころから航空機救助との連携を重点的に研究し始めた。
高知県消防防災航空隊と地元の住民との合同水難救助訓練の様子で、このころから航空機救助との連携を重点的に研究し始めた。11号
 会長表彰に喜びの様子を送っていただいたので表紙に掲載。
会長表彰に喜びの様子を送っていただいたので表紙に掲載。2009年
12号
 幼児着衣泳が手探りで始まった頃。
幼児着衣泳が手探りで始まった頃。13号
 養護学校でも試験的に実施するところがでてきて、その効果に驚きの声が寄せられた。
養護学校でも試験的に実施するところがでてきて、その効果に驚きの声が寄せられた。14号
 さまざまな消防の装備品で浮いてみた様子
さまざまな消防の装備品で浮いてみた様子15号
 横浜消防と共同で研究を実施した。遭難した漁師を救助する想定。
横浜消防と共同で研究を実施した。遭難した漁師を救助する想定。2010年
16号
 高知県にて漁船から転落して背浮きで救助を待つ想定の研究のひとコマ。
高知県にて漁船から転落して背浮きで救助を待つ想定の研究のひとコマ。17号
 東松島市の月浜海水浴場で、漁師が水難に遭ったことを想定した海上保安庁との合同研究の様子。まさか1年もしないうちにここを津波が襲うとは。
東松島市の月浜海水浴場で、漁師が水難に遭ったことを想定した海上保安庁との合同研究の様子。まさか1年もしないうちにここを津波が襲うとは。18号
 冷水に着衣状態で背浮きを実施するときの負荷について研究をしている様子。水温は10℃であり、この状況が東日本大震災で再現されることに。
冷水に着衣状態で背浮きを実施するときの負荷について研究をしている様子。水温は10℃であり、この状況が東日本大震災で再現されることに。19号
 着衣泳もいよいよ国際的に展開が始まった。
着衣泳もいよいよ国際的に展開が始まった。2011年
20号
 津波想定で高知県消防防災航空隊と共同で研究をしている様子。ある決められた時間で何人の人を水面から救助できるのか、調査した。この回転翼が数ヵ月後に震災でこの研究結果をもとに活躍することになる。
津波想定で高知県消防防災航空隊と共同で研究をしている様子。ある決められた時間で何人の人を水面から救助できるのか、調査した。この回転翼が数ヵ月後に震災でこの研究結果をもとに活躍することになる。21号
 津波で流された安倍志摩子指導員が流されながら送信したメール。
津波で流された安倍志摩子指導員が流されながら送信したメール。22号
 国際会議で日本の着衣泳を世界に広めた。
国際会議で日本の着衣泳を世界に広めた。23号
 浮世絵に描かれた着衣泳。命を守るというよりは。。。
浮世絵に描かれた着衣泳。命を守るというよりは。。。2012年
24号
 がっちりした受講生が並んでプール洗濯機。
がっちりした受講生が並んでプール洗濯機。25号
 着衣泳ビデオの収録風景。すでに14年前。
着衣泳ビデオの収録風景。すでに14年前。26号
 津波で流された安倍志摩子指導員が学術講演会で報告。
津波で流された安倍志摩子指導員が学術講演会で報告。27号
 水難学会主催の始めての国際指導員養成講習会の様子
水難学会主催の始めての国際指導員養成講習会の様子2013年
28号
 水難学会主催の初めての国外・スリランカにおける指導員養成講習会の様子
水難学会主催の初めての国外・スリランカにおける指導員養成講習会の様子29号
 震災をうけて、水面からの這い上がりを実技の重点項目とした。
震災をうけて、水面からの這い上がりを実技の重点項目とした。30号
 がっちりした受講生が並んで点呼。
がっちりした受講生が並んで点呼。31号
 海指導員養成講習会の様子。8号に比べて内容が格段に充実してきている。
海指導員養成講習会の様子。8号に比べて内容が格段に充実してきている。2014年
32号
 タイで行われた国際ワークショップと指導員養成講習会の様子。英語とタイ語を交えて実技が進行した。
タイで行われた国際ワークショップと指導員養成講習会の様子。英語とタイ語を交えて実技が進行した。

















