上鴨社(高鴨神社)、中鴨社(葛城御歳神社)、下鴨社(鴨都波神社)3社を参拝した翌朝は、快晴。

念願叶い生まれて初めて大神神社参拝と三輪山登拝をすることとなりました。


古代イズモ族は、ヤマトに神奈備山信仰も持ってきます。「なび」 は隠るという意味で、 祖霊はきれいな三角錐形の山に隠っていると考えていました。
また、イズモ族はインドから太陽信仰を持ってきていましたから、特に朝に昇る太陽をよく拝んだようです。
形の円い山は、妊娠した女性の腹を連想するので、女神山と考えられており、ヤマト地方では、円く秀麗な形の三輪山が女神山と考えられていました。
そして、ヤマト地方では、陽は三輪山から昇ってくるため、その山が女神山であったので、朝の太陽神も女神であると考えられていたようです。
ここまで


カツラギからは、東方に三輪山を望み、鴨族の人々は、三輪山の良く見える場所に集まって、そこから昇る朝日も拝むようになったようです。
当時は母系家族制であったので、家の祖先神の祭りは女性がつとめ、地域の祭りの神主も女性がつとめたと著書では紹介していました。
そのため三輪山の初代祭主に、コトシロヌシの姫君タタラ五十鈴姫が就任し、出雲王国と同じく、年に2回、春分と秋分の日に、タタラ五十鈴姫が司祭となって山の神に祈 る大祭をおこなったようですね。
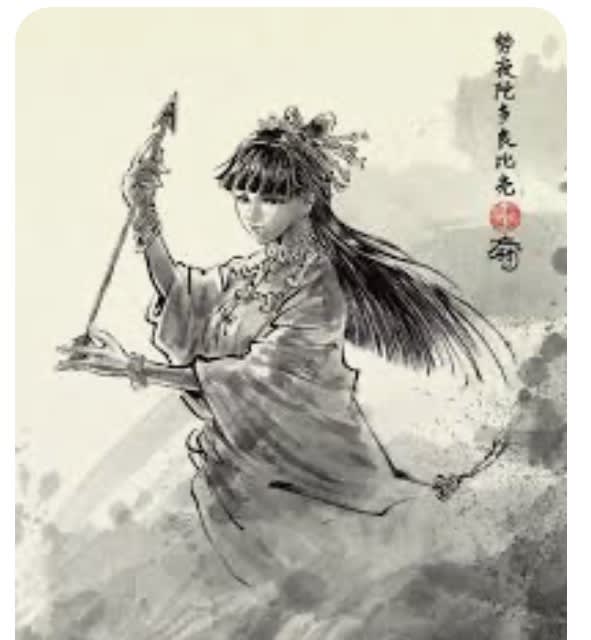
それで、三輪山の西麓の地に宮を建て、姉妹が一緒に住むことになった地はのちに「出雲屋敷」と呼ばれます。太陽の女神を拝む儀式が行われ、三輪山にはサイノカミの幸姫命が祀られたので、山から流れ出る小川は「狭井川」(幸川) と名づけられますが、もとの意味は幸川だそうです。
狭井川と山の辺の道が交わる場所付近には、出雲屋敷と呼ばれたことを示す案内板が建てられているようで、その近くに鎮座する狭井神社ではコトシロヌシやタタラ五十鈴姫が祭られている、とありました。


タタラ五十鈴姫の兄君クシヒカタは、「天日方奇日方」と呼ばれ、その名の意味は「天の奇しきカを持つ日(太陽)を祀る人」のようです。
三輪山を祈る、三輪山から昇る太陽🟰天の奇しきカを持つ日(太陽☀️)に祈る、代表して祈りを捧げたタタラ五十鈴姫を後に祀る。
また、タタラ五十鈴姫の父君・コトシロヌシの神霊も祀る。
コトシロヌシ神の名は、のちに大物主と変えられたと出雲王国の著書では紹介されていました。
神奈備山である三輪山は御霊が還り、安まる、母なる大地の象徴のひとつなのかもしれません。
つづく










