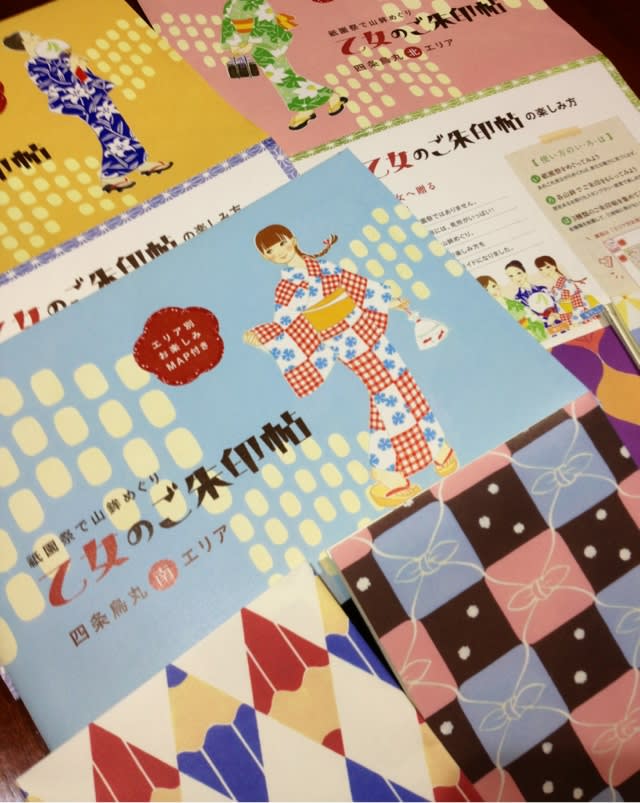お盆が終わり、週末が終わり、またいつもの生活がはじまった。
振り返ると、今年の夏ほど故人の存在を強く感じた年はなかったように思う。
主人はコンペ提出のチェックや映像撮影の立ち会い等で忙しいようで、今年ははじめて娘のNとふたりっきりでの帰省となった。
13日は特急こうのとりに乗って八鹿駅で降り、バスを乗り継いで高柳へ 。
高照寺へ挨拶を済ませた後で、
父方の先祖代々のお墓参り。
途中で母と合流し、親戚のおじさんおばさんとも合流。
行く時とは違う、地方特有の遅い時間の流れの波を不思議な感じで受けとめながら、
83歳のおじさんが運転する(急発進・急停車の荒い運転にドキドキしながら)車に乗せてもらって、実家にたどりついた。
一級河川の円山川に寄り添って、
夏の緑の山々がどこまでも、続いていく。
この川は、豊岡、城崎を越えると日本海へと注がれるのである。
川面は当然のように深い碧色をたたえていて、
とろんとした碧の川面をきれいだなーーと感心して眺めつつ、
おじさんのジョークに受け答えなどして、
車に乗っていた。
車のフロントガラスを、赤とんぼとオニヤンマが次々と線を描きながら流れていく。
田舎の夏を訪れると、
なぜだか、蝉時雨よりも、トンボの大きさに目をみはる。
ほんの2日前には、今年2月に亡くなった103歳の祖母の初盆で御仏壇に手をあわせ、
母方のお墓参りを済ませたばかり。
私の夏は、これらの大仕事を終わらせないと、自分の夏は始まらないように思う。
2日目は、またまた親戚の集いがあった。母は長女なので手伝いやら、何やらのために朝9時から祖母の家へ。
私たちは、朝起きると早々に地元のローカル電車に揺られて「城崎温泉」へと向かった。
暑い日で、太陽はジリジリと肌を焼き、いちだんと湿気も高く、山陰地方の盆地の夏を久々に味わう。
それでも昔ながらの湾曲した石橋や青柳が懐かしくて、
ゆらり、ゆらりと観光客らと一緒にそぞろ歩く。

地蔵湯を抜けて、柳湯を過ぎ、一の湯をゆっくりと眺めながら朝の城崎を歩く。
「お土産物屋さんも、やっぱり昔とは随分と変わったね」
「みなとや、さんは、あらどこ?名前を変えはったんかな」などと、
独り言のようにつぶやいて、
珍しい店をのぞきながら歩く。
朝の城崎はすがすがしい。外国人の観光客も増えたものだ。
ふと。むこうから父がいつもの笑顔のままでこちらへ向かって歩いている姿がまぶたに映った。
自分の宿の料理人用の白い割烹着を腰だけちょこんと巻いていた。
その横からチラリと見えるワニ革(クロコダイル)の茶緑のベルト。
そしてV字のベスト。
うわーーー、幸せな錯覚だ。それを見た瞬間、涙がほろりとにじんだほど私は嬉しかったのである。
そして
父のふわっとした匂いが私の横を通り過ぎた。
本当にありがたい錯覚だった。
それから、「御所の湯」で朝風呂。


お盆で人が多いのではという心配をよそに、
朝風呂は見事に空いていて3組ほどだった。
山からどうどうと流れる滝のしぶきを目前に見ながら
露天温泉へ入る至福。
夏の温泉も、朝はこんなに清々しく、気持ちいい。
温泉という名の熱い海で、ゆうゆうと体を泳がせているようである。
ここの湯は、一の湯のように塩泉ではないと思うが、
やさしくて、透明感にあふれた、いい湯だった。
前に訪れたのは8年前。やはり祖母の慰安のために城崎へ一泊した時のことを、再び、ゆるゆる思い出す。
城崎は7つの外湯めぐりが、素晴らしい。このままどうぞいつまでも鄙びた温泉場であってほしい。
温泉をあがると、ソフトクリームなんぞは食べず、
フルーツ牛乳もこの日は飲まずに、
すぐ目の前の「をり鶴」という老舗の寿司屋へ。

人気店なので40分ほど待ったが、
カウンターの一番端を陣取れた。
身内だけで接客しているのだろう、物腰のあったかい応対ぶりだ。

お昼なので、まずは「にぎり寿司」を注文し、それからコハダ、サユリ、玉子、サザエなどを別注文。
あわせたのは、香住鶴の純米酒しぼりたて。


大将と息子さんの包丁さばきをみながら、
湯浴みのあとでの、旨い寿司。
最高の気分であった。
酢はきつすぎず、にぎるしゃりも柔らかい。
父は前の小さい店だった時に、よくこの大将のにぎる寿司(魚のにぎりや巻き寿司)をごちそうしてくれたもの。
私が大阪へ帰る時には、自分の作った松花堂膳ではなく
「をり鶴」の寿司を車中で食べるようにと、
持たせたくれたものである。
この日はロープウエイまでは行かなかったが、こうの湯あたりでUターン。
城崎は山裾の裏通りや、こうの湯あたりの桜並木の川沿いを、コロンコロンと下駄をならして歩くのが情緒があって良いように思う。
初めての人は、ぜひ射撃場などで遊んでほしい。
昭和なおばちゃんが、ふっくら、やんわりとした面もちでいくらでも打たしてくれるし、スマートボールなどで遊ばせてくれる。
あるいは儲かっていなさそうな、バーで日本酒を飲んだり、ウエハース添えのアイスクリームを食べるのもいい。
私たちはそんな城崎の夜に想いをはせながら、まだ昼間なので帰りに小松菜と柑橘類の野菜ジュースをスタンドで飲み、城崎を歩く。
きょうは盆踊りが近くの神社で行われるようである。