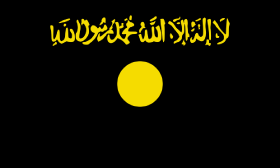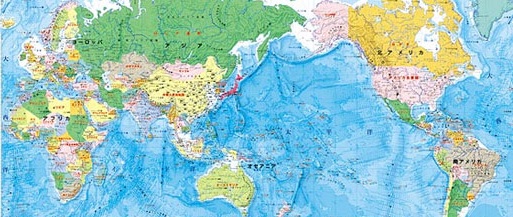
中国敵視は日本を孤立させる 1/24 田中宇
1月24日、国連が、尖閣諸島が中国外縁の大陸棚の一部であるとする中国の主張について、今年7-8月に検討会合を開くことを決めた。
国連は海洋法条約で、陸地に引き続く傾斜が穏やかな海底を大陸棚と呼び、陸地が属する国の領海(陸地から12海里)の外にあるが、漁業や資源開発などその国の経済利権が認められる排他的排他水域にできるとしている。
中国は国連に、尖閣諸島が中国の大陸棚の一部と認めさせることで、地理的な観点からみて尖閣諸島が中国の領土であるべきだという話にしようとしている。 (U.N. to consider validity of China's claim over disputed islands)
かりに今夏、国連が尖閣諸島を中国の大陸棚の一部だと認めたとしても、それで国連が尖閣を中国領と認めたことにはならない。
だが、尖閣が地理的な本来性として中国の一部だと国際的に認められると、中国の「尖閣諸島は本来中国の領土なのに、日本は、中国が弱体化していた日清戦争中に、どさくさ紛れに尖閣を自国領だと閣議で勝手に決定し、それ以来不法占領している」という主張が補強される。 (尖閣で中国と対立するのは愚策)
「尖閣は本来、中国領であるべきなのに、日本が帝国主義時代に奪ったまま占領している」という中国側の見方が国際的に定着しかねない。
日本側の見方は「中国は1980年代に海底ガス田が見つかるまで、尖閣の領土権をほとんど主張していなかったくせに、今になってとんでもない詭弁を発している」というものだが、その見方は国際的に少数派に転じていきかねない。(※北風:欧米の外交では発言介入しないが、既に少数派と思われる。)
「尖閣は、今でこそ無人島だが、以前は日本人が住んでいた」という日本側の主張も、中国側からすると「日本は、中国から奪った島に入植を試みていただけだ」となってしまう。 (中国は日本と戦争する気かも)
ここ数年、国連ではBRICSや発展途上諸国の発言力が増加し、米英から主導権を奪いつつある。
安保理常任理事国でもある中国は以前から、国連で途上諸国の利益を代弁する国を自認している。
911以来、米国の覇権戦略が自滅的に失敗しているのに反比例して、中国が国連で発言力を増している。
中国は、尖閣に関する中国の大陸棚の主張を検討する国連の委員会に大きな圧力をかけるはずだ。 (国連を乗っ取る反米諸国)
米国は911以来、単独覇権の姿勢で、国連を軽視して隠微な政治工作を怠り、力任せに動かそうとする姿勢で、その結果、国連を中国など途上諸国に乗っ取られた。日本は米国に頼りにくくなっている。
尖閣問題が、日中対立の激化によって安保理に出てくるような大問題に発展したら、米国は日本に味方して、中国主導の案に拒否権を発動してくれるだろう。
だが、パレスチナ問題のイスラエル非難決議を米国が拒否権発動で潰し続ける姿に象徴されるように、米国の拒否権発動で守ってもらう国は邪悪だと見られるようになっている。 (悪者にされるイスラエル)
日本人は、尖閣を奪おうとする中国こそ侵略国だと思うが、世界はそのように見ず、むしろ尖閣は「日本が帝国主義的に奪った領土」と見られそうだ。
日本は、中国の巧妙な外交策によって、孤立させられる方向にある。
日本が突っ張っていると、南京大虐殺や従軍慰安婦など「戦争犯罪」問題と連動させられ、国際的に悪者にされる傾向が強まる。
日本はこれまで経済力があったのでアジア諸国から尊重されたが、日本の経済力が落ちて中国の経済力が増す今後は、その点も変わりそうだ。 (◆日中韓協調策に乗れない日本)
日中は話し合おうとする姿勢を見せるが、それはたぶん日中双方の政府の本心でない。
中国は習近平政権になって「いつでも戦争できる態勢」をめざし、軍の幹部を大幅に入れ替えている。 (Inside China: War hysteria blamed on U.S.)
日本では安倍政権が、伝統的に親中国である連立与党の公明党の要人を中国に派遣し、習近平は安倍と会ってもよいと言ったという。
だが日本側では、安倍の特使が訪中するのと同時期に、安倍の外交顧問役である米国筋と親しい外務省の元高官が香港で中国人を集めたシンポジウムで中国批判の講演を発し、日中の敵対を扇動した。
日中とも、和解姿勢は表向きだけだ。 (Abe's adviser blasts China in barbed Hong Kong speech) (China's Xi Agrees to Consider Summit, Japan Envoy Says)
力任せの外交が目立っても、米国が本気で中国包囲網策を続けてくれるなら、まだ日本にとって安心だ。
だが、米オバマ政権がいつまで中国包囲網策を続けるのか、口だけで実体が薄くなるのでないか、懸念が増している。
中道派(国際協調派)のジョン・ケリーが米国無長官になり、同じ傾向のチャック・ヘーゲルが国防長官になりそうだが、2人は、米国が効率的に世界の諸問題を解決できるよう、途上諸国を率いる大国となった中国の協力を得るのが良いと考えている。 (The Asian Pivot Under New Management) (◆2期目のオバマは中国に接近しそう)
米国は、外交軍事面で中国と敵対的だが、経済面では密接につながっている。
米国企業にとって中国は巨大な生産拠点・投資先であり、米国が中国を経済制裁すると米国も大打撃を受けるので、制裁できない。
米国の中国包囲網は持続困難な、中途半端な戦略だ。 (America's Pivot: One Big Contradiction)
米政府は、尖閣を日米安保条約の範囲内だと言っているが、その根拠は尖閣が日本の実効支配下にあるからであり、尖閣が中国側に奪われた状態が続くと、尖閣は中国の実効支配下に移り、日米安保から外れてしまう。
安倍首相は就任してすぐ訪米したかったが、米国側から延期を要請された。
その理由は、日中の対立が激化し、安倍の訪米を許すと、オバマが日本の肩を持った感じが強くなり、米国が中立を保てなくなるからだと米国で報じられた。 (As Dispute Over Islands Escalates, Japan and China Send Fighter Jets to the Scene)
日本政府は、尖閣の土地を国有化して中国との対立をあえて煽ったが、その本意は、日中対立を米国の中国包囲網策の一環として機能させ、日米同盟が中国と敵対する態勢を作ることで、日本の対米従属を強化することだ。
実際のところ米国は、経済面で中国とつながっており、本格的に中国と敵対し続けられない。
米国の中国包囲網はあやふやな戦略なのに、日本はそれに頼って中国との敵対を強め、国際的に孤立しそうになっている。
経済的にも、米国が中国との密接な関係を維持しているのに、日本だけ経済界が中国に投資できない敵対関係を作ってしまい、自滅的に国民生活の窮乏を加速している。 (USA considers scenario of war with China)
米国の単独覇権戦略の失敗と反比例して、中国の国際影響力が拡大している。
先日は、トルコのエルドアン首相が「EUが入れてくれないなら、トルコは上海協力機構に入れてもらう」とテレビ番組で発言し、物議を醸している。
上海機構は中国が主導し、ロシア、中央アジア諸国などが加盟する、ユーラシア西部の安全保障や経済協力の国際機関だ。
上海機構には、インドとパキスタン、アフガニスタン、イランなどが正式加盟の手前のオブザーバーで参加し、トルコはそれらの国々の外側にいる友人的な「戦略パートナー」になっている。 (Erdogan's Shanghai Organization Remarks Lead To Confusion, Concern)
エルドアンは昨年7月ロシアのプーチン大統領と会った時に「上海機構に入れてくれたらEUのことは忘れる」と語ったが、トルコ政府は事後に、あれは冗談だったと釈明した。
EUがトルコを加盟させるとは思えないので、トルコが上海機構に入る話は、今後さらに真剣味を増し、いずれ実現しそうだ。 (Erdogan: Shanghai Cooperation Organisation an alternative to EU)
トルコは、米英主導のNATOに加盟している。
NATOは反ロシア的な国際安保組織で、911後のアフガニスタン駐留によってユーラシア西部への影響力行使をめざした。
米英主導のNATOと、中露主導の上海機構は、ユーラシア西部の覇権を争う関係にある。
トルコが上海機構に入ることは、NATOを捨てることになり、トルコが米英(米EU)の側から中露(アジア)の側に鞍替えするという、地政学的な転換を表している。
実際のところ、トルコが上海機構に入ることは、NATOを捨てることにならない。
NATOは来年のアフガン撤退後、実質的な影響力を大幅が減少するだろう。最悪の場合、NATOの組織は残るが、事実上の解散状態になる。
EUはユーロ危機対策の口実で政治統合を進め、その一環として軍事統合を加速している。
EUの軍事統合が具現化すると、米国が西欧を守るのが基本構造だったNATOは不必要、もしくはEUの自主的な外交安保策にとって邪魔になる。
EUは、NATOがアフガン撤退後に機能低下することや、財政難の米国が欧州を含む世界から軍事撤退していくことを視野に入れて軍事統合を進めている感じだ。 (ユーロ危機からEU統合強化へ)
EUにとってNATOが不必要・邪魔になるのなら、NATOの機能低下は不可避であり、トルコが加盟し続ける意味もなくなる。
NATOが有名無実化するなら、トルコは別の安保策を考えねばならない。
トルコはもともと中央アジアから民族大移動してきた伝説的歴史(歴史的伝説)があり、中央アジアに地政学的な関心がある。
NATOが無力化するなら、上海機構に早めに入った方が良いと、トルコ政府が考えるのは当然だ。 (China could prove ultimate winner in Afghanistan)
上海機構は、もともと中国が中央アジアを経済支援しつつ、中央アジアのイスラム主義運動が中国の新疆ウイグル地区に波及するのを防ぐことを、ロシアの了解をとりつつ進めるための組織だった。
だがその後、911でNATOがアフガンに侵略し、その占領が失敗に向かうとともに、上海機構は、NATO撤退後のアフガンを中露主導で国際共同管理することが目的の一つになっている。
NATOのアフガン撤退後、インド、パキスタン、イランというアフガンに関心を持つ諸国が上海機構に正式加盟を許されるだろう。
そこにトルコも入る可能性が増している。インドが上海機構に入ったら、中国包囲網から事実上離脱することになる。 (India and the SCO: Can they tango?)
西アジアの全体で、米英の影響力が低下し、中露主導の上海機構の力が増すだろう。
イランは中露との結束を強めて国家存続の可能性が増す。
米オバマ政権は、イスラエル右派の妨害を振り切ってイランと和解したいようだが、その裏には、イランを制裁しても効果が薄れるばかりか、中露の利権を拡大して米国の不利が増すだけの現状がある。
シリアもアサド政権が存続しそうで、これまた中露の傘下にある。
米国やサウジが支援した反政府派(アルカイダ)はシリアの政権を取れそうもない。
キッシンジャーは、シリア安定化のためロシアと協調せよと米政府に提案している。 (US needs to work with Russia to end Syria fighting - Kissinger)
オバマ顧問の米シンクタンクは最近、オバマの任期の4年間に、サウジアラビアの王政が、反政府運動の激化による国内混乱の末に転覆される可能性が高いとする報告書を出した。
サウジ王政は昨年から、スンニ派の王政がシーア派の多数派国民を弾圧するバーレーンの混乱が飛び火して、表向き安泰に見えて実は危機の状態になっている。 (Brookings' Bruce Riedel urges intensified US support for Saudi despots)
世界最大の産油国であるサウジが混乱すると、石油価格の高騰など世界経済を混乱させるだけでなく、中東における米国の影響力が低下し、イランやエジプト系の反米イスラム主義が強くなり、これまた地政学的な大転換になる。
中東北部のトルコやイランの転換、南部(アフリカ)のマリやリビアでのイスラム主義の台頭(内戦激化)と合わせて考えると興味深い。 (◆きたるべき「新世界秩序」と日本)
話が広域化しすぎたが、ユーラシア全域で、米国の影響力が低下し、中国の影響力が増しているのが見てとれる。
EUも、ドイツが米国から金塊を引き出す決定をしてドルを揺さぶる半面、中国との戦略関係を強化しており、中露などBRICSと途上諸国が台頭する多極型の新時代への軟着陸をめざしている感じだ。
米英覇権の中枢にいた英国ですら、儲けを失いたくないロンドン金融界が中国に働きかけ、オフショア市場最大の人民元取引市場をめざしている。 (ドイツの金塊引き揚げがドル崩壊を誘発する?) (Bank of England ready to set up first G7 yuan swap)
東南アジアでは、中国の台頭と米国の撤退によって自国周辺の政治バランスが変わることを恐れているフィリピンやベトナム、インドネシアなどが、日本の中国敵視策を歓迎し、日本が中国に対抗して東アジアの新たな政治均衡を作ってほしいと考えている。
しかしその裏で、今後米国が財政破綻などによって東アジアでの軍事的影響を減じたとしても、日本が中国包囲網を維持するつもりなのか、各国とも懸念があるはずだ。
東南アジアの後ろのオーストラリアでは、日本の中国包囲網提案に乗るべきでないとする提案が学者から出されている。 (Right now, we don't need an alliance with Japan)
すでに書いたように、最近の日本の中国敵視策は、対米従属維持策の一環であり、米国を軍事面で日本や東アジアに引き留めておくことが主目的だ。
米国が軍事的に東アジアから撤退する場合、その後も日本が果敢に中国敵視を続けるかどうか、非常に怪しい。
米国が出て行った場合に中国との関係をどうするかというシナリオ自体、日本政府は検討していないかもしれない。
日本が、米国が軍事撤退するかもしれないという前提で対中国政策を考えるなら、そもそも尖閣紛争で中国と敵対するやり方をとらず、中国を批判しつつ協調するような、もっと微妙な策をとったはずだ。
中国と敵対するなら、ロシアや韓国、北朝鮮に協調を働きかけることも必要だが、現実は逆方向だ。 (中国と対立するなら露朝韓と組め)
米国が撤退し、日本が事実上の対中無条件降伏をするような、みっともない結果にならないだろうか。
かつて、欧米からの自立をうたった「大東亜共栄圏」に期待して参加したのに、日本の豹変的な敗戦で裏切られた経験を持つ東南アジアの人々は、それを懸念しているはずだ。
最近の日本の、脇が甘い中国敵視策を見ていると、日本がいずれ窮して再びみっともない豹変をしそうだと感じられる。
日本人自身の間に豹変の懸念が全くないことも、おのれを知る努力をしない戦略的脆弱さを感じる。 (◆一線を越えて危うくなる日本)
ーーーーーーーーーーーーーー