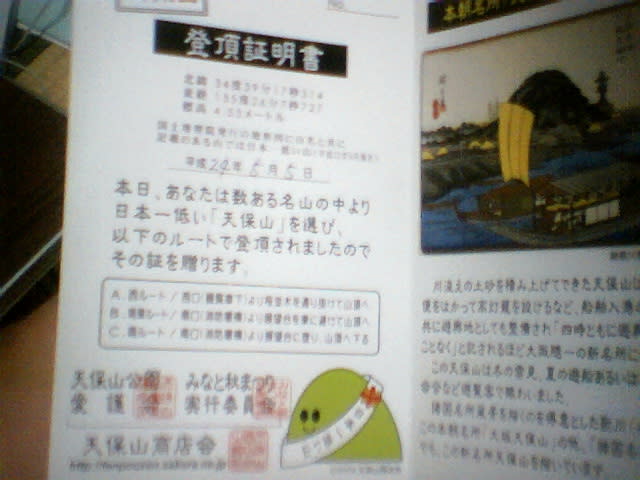時間の流れるのは早いもので、もう2020年も残すところあと一か月足らずとなってしまいました。
COVID-19のせいでほとんど遠出できないのもあって、なんとなく今年一年虚無のままに過ごしてきてしまったような錯覚に陥りますね。
え、錯覚じゃない? またまたそんなぁ。
さて、先ほど「ほとんど遠出できない」と言いましたが、言い換えると全く一切遠出できない、というわけでもありません。ちゃんと感染対策をすれば大丈夫…というのが建前であれ真実であれ言われているところでありまして、実際そんな感じで行われているのがいわゆるGoToキャンペーンですね(まあ第三波やらで今後どうなるかわかりませんが)。
そんな訳で私も9月の連休、いわゆるシルバーウィークにCOVID-19に負けず熊本~博多~下関と勝手にGoToキャンペーンをしてきたのですが(特にキャンペーンの恩恵に与ってはいないような気がします。あと9月の話をいまさら記事にするのは単に私がだらけてただけです)、そこで従来全く認識していなかった九州の文化的特徴に気づきました。
九州の石碑類、文字をめっちゃ金ぴかにしますね?
私がこの九州金ぴか文化(仮称)に気付いたのは、熊本城のすぐそばに位置する熊本県護国神社に参拝した時のことです。このブログを見てらっしゃる方はよくご存じだと思うんですが、護国神社の境内にはたいてい戦友会による記念碑とか慰霊碑とかの石碑、石造物が少なからず建立されています。こういう石造物をチェックするのも護国神社参拝の醍醐味の一つですね(不謹慎)



で、熊本県護国神社にある石碑(一部)の写真がこちら。
はい、めっちゃ金ぴかです。
流石に建立されているものすべてが金ぴかなわけではないのですが、それでも結構な数の石碑の文字が金ぴかに彩られています。他の地域でここまで金ぴかな石碑群というのは見たことがなかったので非常に印象深かったですね。
なんでこんなに金ぴかなのか? と護国神社の方にお伺いしたのですが、境内地の石碑については場所を提供しているだけで建立についてはノータッチだとのこと。
ただ、どうやら昭和50年代くらいから一気に金ぴか文字が増えてきたらしいことはお話の中で分かりました。
で、同様の石碑金ぴか文化は熊本のみにとどまりません。
今回の旅行だけでも直方、大宰府、志賀島などで金ぴか文字の石碑が確認できました。内容も史跡を示すもの(「五卿遺跡」碑)や歌の発祥地を示すもの(「炭坑節発祥の地」碑)といったプラス方面のものから、元寇の際に死んだ元軍将兵の慰霊碑(蒙古塚)といったマイナス方面(?)のものまで多岐に渡ります。
面白いことに、関門海峡を渡った下関では金ぴか石碑は一見したところ確認できませんでした。

大宰府の「五卿遺跡」碑

直方の「炭坑節発祥の地」碑

志賀島の「蒙古塚」碑
ネットで「九州 石碑 金色」などと検索すると結構な数のサイトがヒットするのですが、その内容の多くは「九州ではお墓の文字を金色にする」といったもの。ただ、熊本における学校・史跡関係の石碑の金文字を紹介しているサイトもありました(リンク先)。
お墓を金文字にする理由については現状でもよくわかっていないようですが(実態としては「周りが金色だからうちも金色に」という感じが多いようです)、一説には金ぴか文字が多くみられる長崎については中国の風習に由来するものではないかとも考えられるとのこと(リンク先)。
ただ、これだと長崎以外の九州における石碑金ぴか文字の理由がいまひとつよくわからないんですよね。
蒙古塚なんか、昭和2年に建碑された旧碑の方は彩色痕はぱっと見では確認できないのに、平成17年の地震による被害の後に再建された碑の方は金ぴか文字になってますし。なんなんだろいったい。
いずれにしても、九州にはほかの地方では及びもつかないような謎の「石碑金ぴか文化圏」が存在しています。旅行などで訪問される際にはぜひ石碑の金ぴか文字にも注目してみてください(強引に終わる
COVID-19のせいでほとんど遠出できないのもあって、なんとなく今年一年虚無のままに過ごしてきてしまったような錯覚に陥りますね。
え、錯覚じゃない? またまたそんなぁ。
さて、先ほど「ほとんど遠出できない」と言いましたが、言い換えると全く一切遠出できない、というわけでもありません。ちゃんと感染対策をすれば大丈夫…というのが建前であれ真実であれ言われているところでありまして、実際そんな感じで行われているのがいわゆるGoToキャンペーンですね(まあ第三波やらで今後どうなるかわかりませんが)。
そんな訳で私も9月の連休、いわゆるシルバーウィークにCOVID-19に負けず熊本~博多~下関と勝手にGoToキャンペーンをしてきたのですが(特にキャンペーンの恩恵に与ってはいないような気がします。あと9月の話をいまさら記事にするのは単に私がだらけてただけです)、そこで従来全く認識していなかった九州の文化的特徴に気づきました。
九州の石碑類、文字をめっちゃ金ぴかにしますね?
私がこの九州金ぴか文化(仮称)に気付いたのは、熊本城のすぐそばに位置する熊本県護国神社に参拝した時のことです。このブログを見てらっしゃる方はよくご存じだと思うんですが、護国神社の境内にはたいてい戦友会による記念碑とか慰霊碑とかの石碑、石造物が少なからず建立されています。こういう石造物をチェックするのも護国神社参拝の醍醐味の一つですね(不謹慎)



で、熊本県護国神社にある石碑(一部)の写真がこちら。
はい、めっちゃ金ぴかです。
流石に建立されているものすべてが金ぴかなわけではないのですが、それでも結構な数の石碑の文字が金ぴかに彩られています。他の地域でここまで金ぴかな石碑群というのは見たことがなかったので非常に印象深かったですね。
なんでこんなに金ぴかなのか? と護国神社の方にお伺いしたのですが、境内地の石碑については場所を提供しているだけで建立についてはノータッチだとのこと。
ただ、どうやら昭和50年代くらいから一気に金ぴか文字が増えてきたらしいことはお話の中で分かりました。
で、同様の石碑金ぴか文化は熊本のみにとどまりません。
今回の旅行だけでも直方、大宰府、志賀島などで金ぴか文字の石碑が確認できました。内容も史跡を示すもの(「五卿遺跡」碑)や歌の発祥地を示すもの(「炭坑節発祥の地」碑)といったプラス方面のものから、元寇の際に死んだ元軍将兵の慰霊碑(蒙古塚)といったマイナス方面(?)のものまで多岐に渡ります。
面白いことに、関門海峡を渡った下関では金ぴか石碑は一見したところ確認できませんでした。

大宰府の「五卿遺跡」碑

直方の「炭坑節発祥の地」碑

志賀島の「蒙古塚」碑
ネットで「九州 石碑 金色」などと検索すると結構な数のサイトがヒットするのですが、その内容の多くは「九州ではお墓の文字を金色にする」といったもの。ただ、熊本における学校・史跡関係の石碑の金文字を紹介しているサイトもありました(リンク先)。
お墓を金文字にする理由については現状でもよくわかっていないようですが(実態としては「周りが金色だからうちも金色に」という感じが多いようです)、一説には金ぴか文字が多くみられる長崎については中国の風習に由来するものではないかとも考えられるとのこと(リンク先)。
ただ、これだと長崎以外の九州における石碑金ぴか文字の理由がいまひとつよくわからないんですよね。
蒙古塚なんか、昭和2年に建碑された旧碑の方は彩色痕はぱっと見では確認できないのに、平成17年の地震による被害の後に再建された碑の方は金ぴか文字になってますし。なんなんだろいったい。
いずれにしても、九州にはほかの地方では及びもつかないような謎の「石碑金ぴか文化圏」が存在しています。旅行などで訪問される際にはぜひ石碑の金ぴか文字にも注目してみてください(強引に終わる