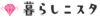「寝室別」の夫婦が急増中⁉ そのメリット&デメリットを大検証
その一方で、寝室を別にして快適にすごしている夫婦も増えているとか。
「寝室を別にしたら夫婦関係に亀裂が入りそう」「離婚につながるんじゃないか」などと心配になる人もいるかと思いますが、どうやらデメリットだけではなさそうですよ。
そこで今回は、寝室を別にすることのメリットとデメリットをご紹介していきます。
夫婦が寝室を別にするきっかけとは?
夫婦が寝室を別にする理由は人それぞれですが、主に考えられる理由は以下の3つ。
▼妻が子どもと寝るから
出産をきっかけに夫婦の寝室を別にするケースは多く見られます。赤ちゃんの夜泣きでパパが熟睡できないというのが主な理由。子どもが1人で寝られるようになっても、その延長で夫婦の寝室は別々のままになる傾向があるようです。
▼いびきや歯ぎしりの騒音で眠れないから
夫婦どちらかのいびき、歯ぎしり、寝言などが激しく、まったく熟睡することができないために寝室を別にする夫婦は少なくありません。いびきだけでも寝られませんが、歯ぎしりや寝言がダブル、トリプルとくれば別室は決まったようなものですね。
なかには、パートナーがトイレに起きたときに気配で目が冷めてしまい、しばらく眠れなくなってしまう方も…。
そのほかにも、寝ている横で読書をされてしまい光や音が気になったり、寝返りなどの振動で目が冷めてしまったり、なかなか眠れなくなってしまう場合もあるでしょう。こういった、音や光、あるいは動きによるストレスが、寝室を別々にするきっかけとなることもあるようです。
▼お互いのライフスタイルを保ちたいから
夫婦一緒に寝るのがイヤなわけではなく、“1人の時間や空間を持ちたい”という願望から別々に寝ることを選ぶ場合もあります。結婚後は、なかなか1人の時間は持てないもの。だから、寝るときくらいは他人を気にすることなく、自分の好きなことや趣味に没頭してリラックスしたいということなのでしょう。
愛情があるからこそ寝室を別々にできる
夫婦が別々の寝室で寝ることは、決して愛情が冷えたということではありません。離婚する確率が上がるというような話もありますが、離婚する夫婦は同室で寝ていても、別室で寝ていても離婚をするのではないでしょうか?
お互いによく話し合って寝室を別々にしたのであれば、快適な時間が持てるぶん心にも余裕が生まれ、相手に対する感謝の気持ちも芽生えるはず。
相手との信頼関係はもちろん、お互いを尊重しあう気持ちや愛情があるからこそできることと言えるかもしれません。
「寝室別」のメリットとは?
これまでにも述べてきたように、最大のメリットは「パートナーを気にせず、1人でゆっくり眠れること」ではないでしょうか。また、趣味や読書を思う存分楽しんで、快適な時間が持てることもメリットです。さらに、快適な睡眠や時間が確保できると、精神的にも満たされ、揉めごとなども少なくなることでしょう。
それに、ケンカの後なども自然に距離が置けるので、気持ちを落ち着かせることもできますよね。とくに1人の時間や空間を持ちたいと願う方には、その時間や空間こそが魅力となるかもしれません。
「寝室別」のデメリットとは?
夫婦の寝室を別々にしてそれぞれの時間を持つということは、必然的に夫婦のコミュニケーションやスキンシップが減るということ。とくに、お互いに仕事で忙しかったり育児に追われたりしていれば、ますます夫婦で過ごす時間は減ってしまうかも可能性があります。
そして、寝室を別々にすると、睡眠時無呼吸症候群などの病気を発見するのが遅れるというデメリットも気になるところ。脳梗塞や心筋梗塞などの発作では、発見の遅れは致命傷になりかねません。
また、夫婦で過ごす時間が減ることで安心感や幸福感を得られず、うつ病などを引き起こすこともあるようです。
寝室を別々にすることにはこのようにメリットもデメリットがありますが、ライフスタイルや性格による向き不向きが大きく影響するものかもしれません。大切なのは、お互いが快適でいられること。夫婦でよく話し合って、自分たちにあった快適な空間を見つけてくださいね!
<プロフィール>
ナツキレイ
フリーライター/日本語家庭教師
タイ在住を経てオーストラリアへ。現在はオーストラリアの田舎で日本語を教える傍ら、ライターとしても活動。政治・経済・教育などの分野から、子育て・旅行・セレブ情報など生活や趣味の分野まで幅広いジャンルで執筆中。定期的に英語のニュース・雑誌サイトの記事を翻訳してリライトも行う。日本生まれ海外育ちの2児の母。
写真© naka - Fotolia.com