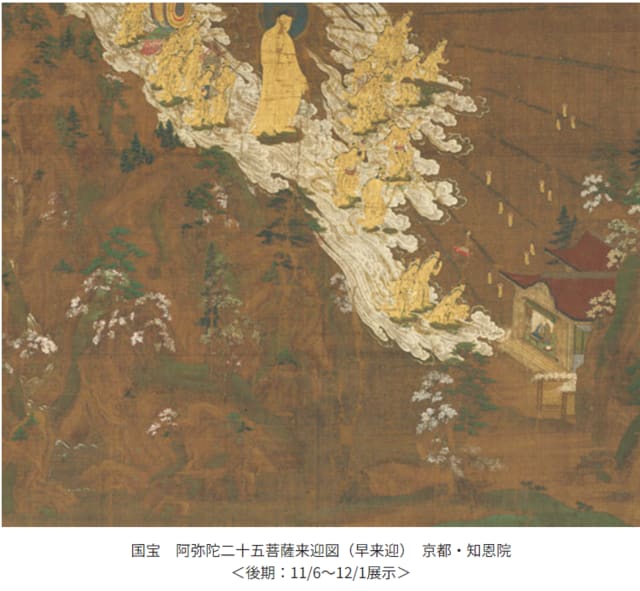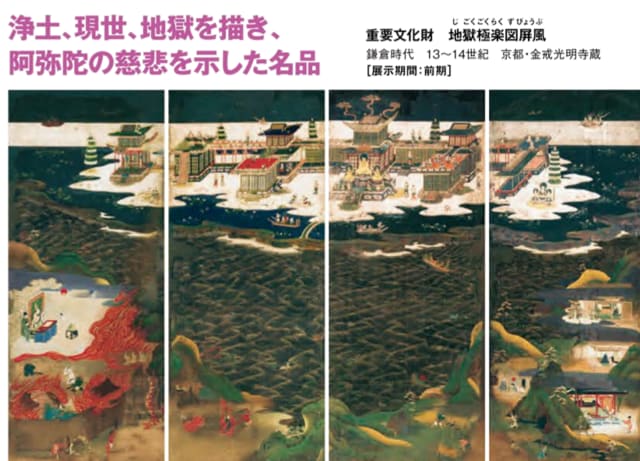石破政権の与野党「部分連合」が招く財政赤字拡大、総花的政策は“インフレ被害者”の政治不満強める
Yahoo news 2024/11/9(土) ダイヤモンド・オンライン 一橋大学名誉教授 野口悠紀雄
政権維持でも政治は不安定化 財政赤字が拡大しインフレに
これまで2年間、世界的なインフレと円安で、日本はインフレに見舞われた。
この問題が完全に終わったとはいえないうちに、日本国内で新たな懸念が生まれた。それは、財政赤字の拡大によるインフレの危険だ。
総選挙の結果、自民・公明の与党勢力が激減し、石破茂首相は、国会での首班指名を得るために野党の国民民主党と経済対策作りや来年度の予算編成、税制改正での連携に踏み出した。
今後、他の野党も含めて、一部の政策で協力する部分連合によってさまざまな意見を取り入れ、総花的・八方美人的な政策が行われる可能性が強い。
このため、負担の引き上げが難しくなる半面で、歳出増の圧力が強まり、財政赤字が拡大するだろう。
財政赤字が拡大すれば、金利が上昇しインフレ率が高まるというのが伝統的な経済学の見方だ。
インフレは、低所得層や年金生活者などの弱者ほど打撃が大きい。「部分連合」で政権は維持できるかもしれないが、政治や社会の不安定化が強まる。
「MMT」が言うようにはいかない 歳出バラマキの影響は金利や物価に影響
少数与党など政権基盤が弱い政府は往々にしてバラマキ的な政策を行う。他方で、増税や社会保険引き上げなどの負担増は後回しにされるだろう。これが経済にいかなる結果をもたらすだろうか?
特に大きな問題は生じないという考えもある。
その代表が現代貨幣理論(MMT)だ。これは、自国通貨を発行する国では国債が内国債である限り、財政支出をいくらでも国債で賄うことができるという考えだ。
この考えは一見したところ、もっともらしい。
なぜなら第一に、国債が内国債である限り、自分自身に対する負債なので、格別の負担は発生しないように思われるからだ。
第二に、完全雇用経済では、財政赤字が拡大して需要が増加した場合に経済全体の需要が供給を超過してしまうので物価が上昇するが、不完全雇用経済であれば、遊休資源の活用によってGDPが増大するから、金利や物価には影響が及ばないように思われるからだ。
MMTをそのまま信奉し主張している政党は少ないが、先の総選挙の公約などを見ると、多くの党が減税などを言う一方でさまざまな歳出拡大策を唱えている。
例えば、国民民主党も「未来志向の積極財政」を掲げて、所得税基礎控除の引き上げやガソリン代値下げ(トリガー条項発動による揮発油税上乗せの停止)、事業主への社会保険料負担助成、教育国債の発行による教育や子育て政策の無償化――など打ち出している。
「賃金上昇率が物価(上昇率)プラス2%に達するまで」という前提だが、こうした政策が実施されれば、財政赤字は大幅に拡大するだろう。そして金利や物価にも影響が出てくる。
財政赤字が増加すると金利は上昇 人為的に抑えると債券市場は混乱
マクロ経済学は、財政赤字が拡大すれば、金利が上昇しインフレ率が高まると予測する。その理由を標準的なマクロ経済学の道具である「IS・LM分析」と「総需要・総供給モデル」で説明すると、次の通りだ。

IS・LM分析は、物価水準を一定にしてGDPと金利の関係を示すものだ(図表1参照)。財市場での均衡を表わす金利とGDPの関係がIS曲線で表わされ、貨幣市場における均衡をもたらす金利とGDPの関係がLM曲線で表わされる。
I:投資 (Investment)、S:貯蓄 (Saving)、L:流動性選好 (Liquidity Preference)、M:貨幣供給 (Money Supply)
縦軸に金利、横軸にGDPを取った図においてIS曲線は右下がりだ。なぜなら、金利が低ければ投資支出が増えてGDPが増大するからだ。
一方でLM曲線は右上がりだ。なぜなら、GDPが増えると取引需要の貨幣(取引の決済などに用いられるマネー)に対する需要が増える。貨幣の供給が一定であれば、資産保有目的のマネーの需要を減らす必要があり、そのためには金利が上昇する必要があるからだ。
財政赤字が拡大すると、追加需要(財政支出、または減税で増加した消費支出)が発生するので、IS曲線が右にシフトし遊休資源が活用され、このためGDPが増加する。
ところがLM曲線は右上がりなので、IS曲線の右方シフトによって均衡点が右上方に移動する。つまり金利が上がる。
なお、ここでいう金利は実質金利だから、物価が上昇すれば名目金利はさらに上がる。
だが日本の現状では、金利上昇を抑えるような動きが起きる可能性がある。日本銀行が利上げを躊躇するかもしれない。あるいは政府が日銀に圧力をかけて金利の引き上げを認めないかもしれない。
石破首相は、つい先ごろまでアベノミクスに対して批判的な意見を述べていた。しかし、自民党総裁に選出されると180度転換し、日銀総裁に利上げを牽制するような発言をするようになった。
こうした“圧力”のために日銀が利上げできなくなると、資金調達市場が混乱する可能性があり、債券市場で円滑な資金調達ができなくなる。ちょうど2022年の秋に生じた状況の再現だ。この時には、金利上昇圧力が強まったにもかかわらず、日銀はイールドカーブ・コントロール政策に固執し、長期金利(10年国債金利)の上昇を指し値オペなどで強引に抑えたため、スプレッド(国債との金利差)が取れない地方債や社債による資金調達に障害が出た。
また、日銀がイールドカーブ・コントロールの撤廃に追い込まれることを見越した海外ヘッジファンドからの激しい投機に見舞われた。
財政赤字拡大で物価も上昇 需要曲線がシフト、均衡点が移動
以上で述べたのは、物価水準が一定に保たれる経済の分析だ。しかし、物価の変動を考えると、財政赤字拡大の影響はそれだけにとどまらない。

これを分析するために、総需要・総供給のモデルを用いる(図表2参照)。これは物価が変動する場合に、経済全体の均衡における物価とGDPの関係を示す分析だ(この場合にも金利は動いているのだが、表には表れない)。
この分析では、縦軸に価格を、横軸にGDPを取る。
価格を所与とした場合にIS・LM分析から得られる均衡のGDPを、さまざまな価格についてプロットした直線を総需要曲線(AD曲線)という。
IS・LM分析からすぐに分かるように、総需要曲線は右下がりだ。
他方で、供給面を考えると、価格が高いほど供給が増えると考えられるので、総供給曲線(AS曲線)は右上がりになる。これはフィリップスカーブと呼ばれる経験則から導き出された考えだ。
財政赤字が増加すると、総需要曲線が右に動く。ところが、総供給曲線は右上がりなので、物価が上昇する。つまりインフレがもたらされる。
以上をまとめると、財政赤字の拡大によってGDPの増加と金利の上昇、そして物価の上昇がもたらされることになる。
「インフレ被害者」の 政治的な不満が強まる
多くの人の所得は、賃金という形で名目値で決められている。インフレが起こると、その実質価値が低下する。したがって、インフレに対しては名目賃金を増やし、実質賃金を一定にしなければならない。
しかし、それができる企業とできない企業がある。大企業の場合には可能だが、中小企業では難しい場合が多い。フリーランサーの場合にはもっと難しい。
一般に、取引の力関係で弱い立場にいる人は、インフレになったからといって、販売価格の引き上げを取引先に要求することは難しい。
インフレの被害者は制度的に賃上げから外されている人々だ。
年金受給者もそうだ。年金も名目値で決められているが、日本の年金制度ではインフレスライドがあるので、実質価値を維持できるように思われる。しかし実際には、現役世代の人口減少を勘案するマクロ経済スライドによって年金額が実質的に減額される。
これまではインフレ率が低かったので発動されないことが多かったが、インフレ率が高くなれば発動される。そうなると、年金の増額は物価の伸びよりも抑制されるため給付水準は目減りし、インフレによって年金の実質価値が下落する可能性がある。
インフレによって利益を得る人は高所得である場合が多いのに対して、インフレによって被害を受ける人は低所得である場合が多い。つまり、インフレは逆進的な税率の税のようなものだ。インフレが最も過酷な税であると言われるのは、もっともなことだ。
したがって、貧富の差がますます拡大し政治に対する不信と不満が強まるだろう。