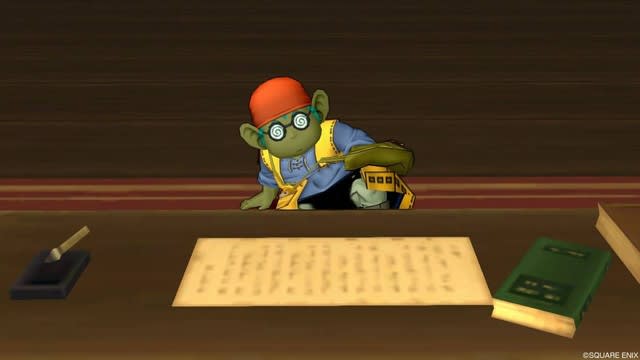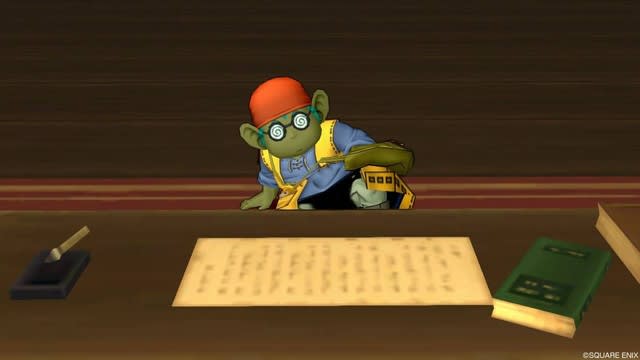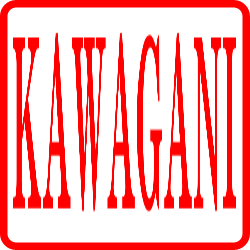初回
前回
<わな>

彼女は石のベンチに腰をおろして、悲しげに頭をたれて、もの思いにふけった。わたしは彼女のそばによって言葉をかけた。彼女はびっくりしてふるえた。

「ボクは、あなたのしあわせを願って暮らしてきました。彼はよいご主人を持たれたようですね」
「新しい奴隷を持ったのじゃないわ。主人をよ。女には主人がいるわ。女は主人を尊敬するものよ」
「あなたは彼を尊敬しているのですか、あんな野蛮な奴を・・・・」

「尊敬しているわ。愛しているわ。ほかのだれよりも」
「ヴァンダ!」
わたしは両手を握りしめてくやしがった。

「あなたはまだ、わたしの奴隷でいたいの。おもしろいわ。でもあの人が許されないと思うわ」
「彼が・・・・?」

「そうよ。あの人はあなたを即刻解雇しろって、わたしに命じたわ。だからあなたが、だれであるか話したら・・・・」
「彼に話した?」
「そうよ。なにもかもみんな話したわ」

「それでだっち彼が怒ったというわけだっちですね」

彼女は下をむいて黙り込んでしまった。しかしわたしはなおも彼を嫉妬し、彼女をなじって議論をつづけ、しまいには、

「もしあいつと結婚するなら、君を殺すぞ」
とおどかした。すると彼女は急に態度をかえて、
「わたし、そういうふうなあなたが好きよ」
といって娼態を示し、
「あなたと結婚するわ。わたしの好きな、好きなあなたと!」
といって、わたしの接吻に応じた。

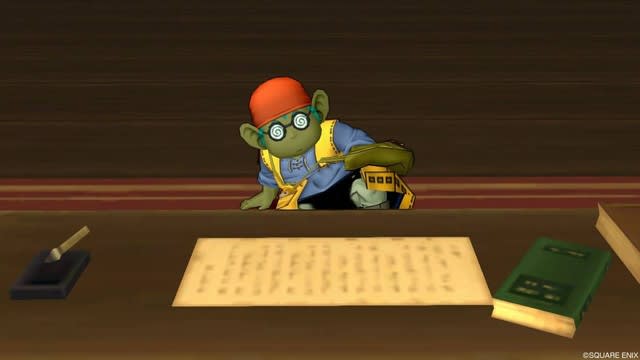




翌日、彼女はどこかほかへ移転したいといって、準備を始めた。夕方、彼女が一通の手紙を出してきて欲しいといったので、わたしは馬車を駆って行ってきた。帰ると早々、待ちかねたように黒人女がきて、
「ご主人様がお呼びでございます」
といった。
「だれか来ているのだっちか?」
「いいえ、だれも」

わたしはゆっくりと階段をのぼって、応接間を通り抜けた。彼女の寝室のドアの前に立った。

ドアはすぐに開いた。彼女は長椅子のうえに横たわっていたが、わたしには気づかないふうであった。銀灰色の服を肌にぴったりにきて、ふくよかな胸と腕をあらわにあらわしていた。髪は編み合わせて青のビロードのリボンを付けていた。釣りランプからはなたれる赤い光が、部屋の調度品をも彼女のからだをも、血汐の色で染めていた。


「ヴァンダ」
わたしは彼女のベッドのそばによって、低い太い声で叫んだ。

「お、ゼフェリン」
彼女は目をあけて、わたしを見るなり嬉しげに叫んだ____
「わたし、待ちくたびれたのよ。今日は、とってもとっても、あなたが恋しくて・・・・・おかわりでしょう?」

そして彼女はわたしの額のおくれ毛をかきあげて、わたしの目に接吻した。
「わたし、この目をいつも愛してきたの。なんて美しいんでしょう!・・・・」

「それなのに、あなたは冷たいわ。わたしを抱いてくれても、まるで丸太棒みたいだったんですもの。あ、待っていらっしゃい。いまわたしが愛の光でたきつけてあげるから」

彼女は媚びるような目つきでわたしにとびついて、わたしの唇に接吻した。それから、

「わたしは、わたしは、あなたを愛するしるしに、もう一度残酷になってあげるわね。かわいいおバカさん、ムチで打ってあげる・・・・」

「でもだっち・・・・・」
「打ってあげたいの!」

「ヴァンダ!」
「こっちへいらっしゃい。わたしに縛らせてちょうだいね。あなたが、わたしをすごく愛してくださっているのを、わたし見たいのよ、ね、わかって?ここに網があるわ」

彼女は立ちあがると、すぐにわたしの足を縛り、それから両腕をうしろにまわして、囚人みたいに締めあげて縛った。
「どう?動ける?」
「動けません」
「すてき」

彼女はさらに丈夫なロープでわたしのからだをエビ攻めのように縛り、ロープの一端で柱ひとつにわたしのからだをくくりつけた。
「まるで処刑されるみたいです」
わたしは低い声でうめいた。
「そうよ、徹底的に処刑してあげるの!」
と彼女は悪鬼のように叫んだ。
「毛皮のジャケットを着てください!」
「喜んで着てあげるわよ」

彼女は愛用のロシア・ジャケットを着て、わたしの目の前にぬくっと立った。そして両手を組んで、目を細めて、わたしを見おろしながら、

「処刑よ、拷問よ。このわたしに利己心や高慢や残忍を植えつけたのはあなたですから、その最初の犠牲にあなたをえらんであげる。わたしを愛している男を虐待するのはおもしろいわ。それでもまだ。あなたはわたしを愛している?」

「気が狂うほど愛してます!」
「熱烈なほど、いいわ」

「今夜のあなたの目には、本物の残忍さの光がある。しかも不思議に美しい。完全に毛皮を着たヴィーナスだ!」

彼女はそれには答えないで、いきなりわたしの首に両腕を巻きつけて、熱烈な接吻をした。わたしの情欲は熱狂的に高まった。

「ムチは、どこに?」
「ほんとうに罰をうけたいのね?」

「そうです!」
「承知したわ」

彼女はさっと一歩身をひいてつんと胸をそらし、なかば顔をベッドのとばりのほうにむけて、
「あなた!この男をムチで打ってちょうだい!」
とあでやかな高声で叫んだ。

声に応じて四柱式寝台の垂れ幕のなかからあらわれたのは、あの美青年のギリシャ人だった。わたしは茫然自失した。彼はチェックの赤ジャケットとズボン、乗馬用の長靴といういでたちであった。そしてわたしのほうをじろりと見てから、彼女にむかって、

「君はたしかに残酷だなァ」
「ちょっとどぎつい快楽ね」
と彼女は上機嫌で笑った。
わたしは完全に彼女の快楽と残酷の罠にかかってしまったのだ。怒りがこみあげてきた。

「縄をとけ!」

「いまさら、なにをいっているの。おまえは、わたしの奴隷じゃないの。同意書を見せてあげようか」

「縄をとけ!さもないと・・・・・」
わたしは渾身の力をこめて縄からのがれようとした。

「縄がきれるかしら?」
彼女はちょっと不安げに若いギリシャ人をかえりみた。
「大丈夫、心配はいらない」
「人を呼ぶぞ!」
「だれにも聞こえやしないわよ」

彼女は、すばやく寄ってきたギリシャ人にムチを渡した。
「やる気か!」
わたしは怒りにふるえながら叫んだ。

「ハハハ、ボクが毛皮を着ておらんものだから、気にいらないらしいな」
ギリシャ人は皮肉に笑いながら、ベッドのうえから短い毛皮の上衣をとって、彼女にてつだわせて着込んだ。
「さあ、ほんとうにこの男をムチ打っていいのかい?」
「お好きなように、どうぞ」
と彼女はうながした。

「けだもの!」
わたしは猛烈な嫉妬と反感をおもえて、気が遠くなりそうだった。

ギリシャ人は血に飢えた狼のようなものすごい形相でわたしに追ってきて、恐るべき力でムチをふるってわたしをうちすえた。ひと打ちごとに肉が裂け、骨がくだける思いだった。彼女は冷然と、いや、いかにも愉快そうにゲラゲラ笑って眺めていた。わたしは恥と絶望で狂い死にそうであった。
それからわたしは、ギリシャ神話にあらわれる神々の愛欲の修羅場を夢みた。男は女の裏切りの罠にかかって、奴隷となり不幸な死へ・・・・・

夢から覚めたように気がついたときには、わたしの肌から血が流れていた。そしてうつろなわたしの耳に響いてきたのは、ヴァンダの悪魔的な嬌声と笑い声、トランクに鍵をおろす音、階段を下りていく彼女と彼の足音、馬車が走り出す音・・・・・

あとは静まりかえってしまった。

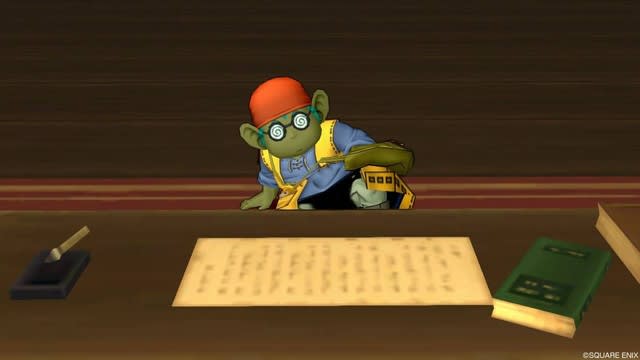

「この話の意味は?」
「わたしがバカ者だったっちということだっちさ。・・・・・せめて一度でもだっち、あの女をひっぱたいてやればよかったんだっちが・・・・」


DQX毛皮を着たヴィーナス 完
原作 ザッヘル・マゾッホ(著)毛皮を着たヴィーナス
脚色 える天まるのブログ