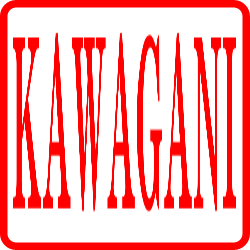初回
DQX毛皮を着たヴィーナス
前回
『毛皮を着たヴィーナス』給仕
<大鏡>

今朝が早くわたしはひとりでメディチのヴィーナス像をたずねた。

美術館のなかの小さな八角形の部屋は、神殿の内部のように燈明が光っていた。わたしは、深く沈黙したヴィーナスの裸像の前に立って崇厳の念をこめて拝んだ。

回廊には人影ひとつなかった。わたしは身をかがめてひざまずき、この女神像の愛らしいすらりとしたからだ、ふくらみかけた胸、処女らしい、だが豊満な顔、小さな角でも隠しているように見える、匂うような巻き髪をじっと見あげた。

深い祈りをこめてから、帰宅して、しばらくすると正午であった。

ヴァンダはまだ両腕を首の下に組んでベッドの中に横たわっていた。わたしを呼ぶベルが鳴った。

「わたし水浴びをしたいわ、おまえそばにいてちょうだい。ドアに鍵をかけて!」

わたしは命じられとおりにして、彼女の寝室へ通じる曲がり階段をおりた。

鉄のてすりにつかまって身を支えながら一段ずつおりていって、途中いくつかのドアに鍵がかかっているかどうかをよくたしかめてもどってくると、彼女はベッドのうえで髪をほぐしていた。緑のビロードのついた毛皮の下は白い素肌であることが、わたしには直感され、悩ましかった。
「ここへ来て、グレゴール。わたしをだいていって!」

わたしは絞首台を見てふるえている死刑囚のようにわなわなしながら、彼女に近づいて毛皮ごと彼女のからだを抱いた。彼女の両腕はわたしの首まわりにからみついた。

一歩一歩、慎重に階段をおりるたびに、彼女の乱れ髪はゆれて、わたしの頬を打った。

浴室は赤いガラスの円天井の室で柔らかに光が射し込んでいた。二本の棕櫚の木がビロードのクッションのあるベッドのうえに、大きな広い葉をさしのべていた。わたしがベッドに彼女のからだをおろすと、
「階段うえの、わたしの化粧台に緑のリボンがあるから持ってきておくれ、それにムチも」と命じた。

わたしは階段をかけあがって、それらを持ってきてから、彼女の水浴の用意にかかったが、彼女のすばらしい玉の肌のあちこちが毛皮の下から見えて光るのに気をとられて、どうにも手足がうまく動かず、ドジばかりふんでいた。

そしてようやくのことで水槽に水が満たされると、彼女はさっと毛皮を脱ぎすてて全課になって、わたしの目の前に立った。
わたしはそのこうごうしさに目がくらむばかりだった。神聖、清純、そして豊艶、わたしは思わずその場の伏して彼女の足に接吻した。

彼女は一瞬のためらいもなく、静かな足どりで水槽に近づくと、水晶のような水のなかへさっと飛び込んだ。美しい小波が彼女の肌のまわりにたわむれているようであった。
水からあがった彼女のつやつやした肌から銀色の水滴がしたたり、バラ色の光が放射された。わたしは言葉もなく歓喜した。そして乾いたリネンの白布で、彼女の輝かしいからだをぐるぐると巻いて水をぬぐい去ってやった。

やがて彼女は大きなビロードの外衣にくるまってクッションのうえにゆったりと横たわって休み、清潔なかわいい無頓着そうにムチでもてあそんでいた。その様子は、黒い貂の毛皮を背景にして白馬がくつろいでいる姿に似ていた。

わたしはその情景をほれぼれと眺めていたが、ふと振り向いて反対側の壁を見ると、思わずあっとおどろいた。そこには金色の額縁の大鏡のなかに、わたしと彼女の姿が豪華な絵のようにうつっていたからである。それがあまりにも美しく、あまりに空想的な絵画に思われ、しかもいつ消えてしまうかもしれないみごとな情景だったので、わたしはにわかに深い悲しみに襲われて顔をしかめた。
「どうしたの?」
「あれだっち、生きた絵だっち」

わたしは鏡のなかを指さした。

「ほんと、美しいわねえ。この瞬間の情景をとらえて、永遠の画面に残すことのできる絵かきさんがいたらいいんだけど、残念だわね」
「できないはずはありませんだっち。もしあなたが画家に思うぞんぶん絵筆をふるわせるようにしたらだっち、あなたの美しい姿は永遠不滅のものとして残りますだっち。あなたの美は死を超えて、永遠に勝ち残りますだっち」
「そうね」
と彼女は微笑して、

「でもいまのイタリアには、ティチアーノとかラファエルとかいうほどの天才画家がいないので、残念よ。天才のいない穴埋めは、恋の心がやってくれる。そうかもしれないわ。あのドイツ人の画家だったら、それができるかしら?」

「あの画家ならば、たしかにだっち、愛の神が絵具をまぜるのをやってくれますだっち」
これがきっかけで若い画家が呼ばれて、彼女の別荘の一隅に画室を設けて、赤い髪と緑の目をしたマドンナ像の製作にとりかかった。

画室のなかでモデルとして横たわった彼女は、横柄な音楽的な笑い声を盛んにたてた。開けっ放しの窓の下に身をよせて、わたしは猛烈に嫉妬しながら、じっと耳をすませて一語一句も聞きもらすまいとした。
彼女は嬌声を(きょうせい)をあげていった____

「絵かきさん、あなた気でも狂ったんじゃないの、わたしを救世主の母マリアのモデルにするなんて!おかしいわよ。ちょっと待ってね、わたしの絵をお見せするわ。わたしが描いたものよ。それを模写していただきたいわ」

彼女は窓から首を出した。太陽の強烈な光にあたって、頭の毛が焔のように輝いた。
「グレゴール!用事よ!」
呼ばれてわたしは、大急ぎで階段をのぼって柱廊を通り抜けて、画室にはいった。
「この絵かきさんを浴室へ案内して」

わたしは命じられたとおりに画家を案内して行く間に、彼女はちょっと姿を消したが、数分後に浴室に現れたときには、玉の素肌に貂の毛皮だけをはおって、ムチをもてあそびながらビロードのクッションのうえに横たわり、片足で床に身を投げ出したわたしのからだを、ぐっとふみつけた。
「あれを見てちょうだい、どう?お気に召して?」
と彼女は大鏡のなかを指さして、画家をかえりみた。

画家は驚きのあまり顔を真っ青にして、唇をわなわなとふるわせて、
「わたしも、あんなふうにあなた様を描きたいと思っていたのですが・・・・」
と答えたが、あとは痛切な呻(うめ)きになってしまった。

次回
『毛皮を着たヴィーナス』画家