広島県内の紅葉は今から益々、赤身を指しながら盛りを迎える。広島市の隣の廿日市市へ友人とドライブへ出掛けた。かつて四年間、勤務した地でもあり、懐かしさが込み上げて来る。宮島サ-ビスから交通安全の速谷神社へ向かう。宮島サ-ビスエリアに着き、公園を見渡すと軽く紅葉していた。
宮島サ-ビスエリア公園に「交通安全」の神様に通じる入口を示す鳥居。

公園も色気付いて来た。

速谷神社鳥居

参道

山陽道の守護神で神格の高い官幣大社

「阿岐国造」

境内には健康長寿や病気平癒の神様「岩木神社」(岩木翁神)を、お祀りしてある。

速谷神社近くに古くから銘水として知られ、商売&安産の神様として祠が祀られているおり、探して山中に分け入ってみた。
つゆ太郎の銘水を遠くから水を汲みに来ておられる。

奥に「つゆ太郎」の源水が絶えない。 ≪飲んでみたが円やかな味がした≫

安産の神様

祠に祈祷する

おおの自然観察公園


ベニマンサク


市内では広島三大祭りの一つである胡子神社の祭礼が始まった。≪えびす講≫
〖 → 町年寄役 銭谷 又兵衛 & 大年寄 松屋 太郎右衛門〗<農家農民 → 大庄屋 & 庄屋格>の、町方役人がこの地に勧請(かんじょう)したとのこと。


平和公園の今


横川散策へ~~、一眼カメラを忘れた。
ドリミネ-ネイションに火が燈った。今日はカメラを忘れたので、観て帰宅することにした。「竹内 まりや」の <家に帰ろう>の曲を聞きながら ♪♬♫~恋する庭を~
宮島サ-ビスエリア公園に「交通安全」の神様に通じる入口を示す鳥居。

公園も色気付いて来た。

速谷神社鳥居

参道

山陽道の守護神で神格の高い官幣大社

「阿岐国造」

境内には健康長寿や病気平癒の神様「岩木神社」(岩木翁神)を、お祀りしてある。

速谷神社近くに古くから銘水として知られ、商売&安産の神様として祠が祀られているおり、探して山中に分け入ってみた。
つゆ太郎の銘水を遠くから水を汲みに来ておられる。

奥に「つゆ太郎」の源水が絶えない。 ≪飲んでみたが円やかな味がした≫

安産の神様

祠に祈祷する

おおの自然観察公園


ベニマンサク


市内では広島三大祭りの一つである胡子神社の祭礼が始まった。≪えびす講≫
〖 → 町年寄役 銭谷 又兵衛 & 大年寄 松屋 太郎右衛門〗<農家農民 → 大庄屋 & 庄屋格>の、町方役人がこの地に勧請(かんじょう)したとのこと。


平和公園の今


横川散策へ~~、一眼カメラを忘れた。
ドリミネ-ネイションに火が燈った。今日はカメラを忘れたので、観て帰宅することにした。「竹内 まりや」の <家に帰ろう>の曲を聞きながら ♪♬♫~恋する庭を~






























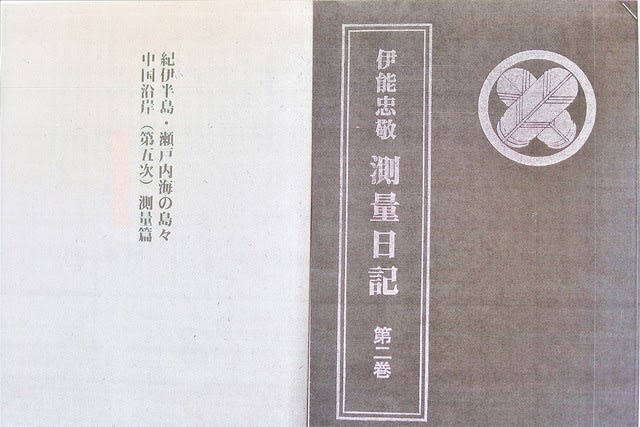









 ≫
≫

