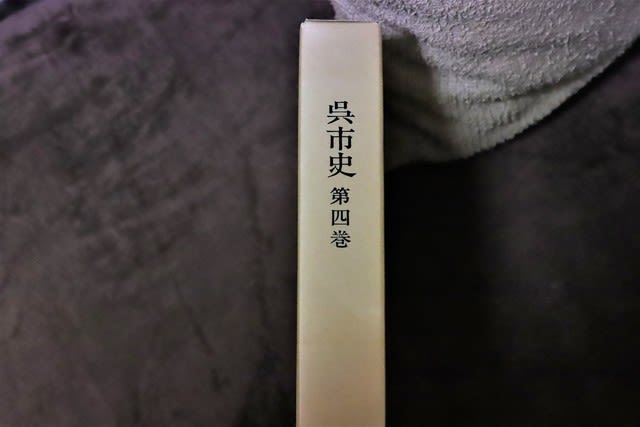マスコミ(特に民放テレビ)新型ウイルス関連(国内外)、従属関係にあるオリンピック関連が連日・連夜に報じられているが報道表記、医学者、医学専門家の言葉に耳慣れない言葉が多く、私のような浅学非才の人間は理解度は低い。が聞く毎に調べて見る毎に勉強にもなった。クリティカル、パンデミック、クラスタ-、フィ-バ-、エンテイバイオティクス等など·······、WHOは中学で習ったが前記した単語はネットで調べ、やけ気味でネイティブ発音まで調べて見た。PANDEMICもストレスはDE、CLUSTERもストレスは弱い、CLITICALも~~、日本語の発音も~~お洒落発音? クラブ、かれし、その他の尻上がり・尻下がりと変わった発音する人がおられる。だだし、地方・地域に寄っては方言もあり、発音も違っており人間味を感じ好印象を与える場合が多い。が就職試験での面接(第二次試験)は個性・人格・表現力を試される場で、方言は方言「職種に寄っては共通語・標準語」で、自分の言葉で話す方が好感を持たれるのではないかと思う。お洒落言葉、お洒落発音は必要はないと思うが·········~~。私も定年を終えた年頃(笑)、若い人には年寄寄りだなあ~、古いなあ~と思われているのだろう(笑)。これも時代の流れ、世は変わって行く。
ウイルス感染でマスク、手洗いは一般化しているが外出控えは自己管理・自己責任から当然だが、今日は休み(シフト勤務)でBSテレビと歴史読書とのスケジュ-ルを決定し、ゆるりとペ-ジをめくった。書は徳川政権の前、豊臣政権時代に遡るが豊臣秀吉が九州平定で京都を発ち、~~広島県の海田に立ち寄った。
福岡黒田藩の支藩である秋月藩の秋月氏は薩摩の嶋津義久氏と同盟を結び、秀吉を迎え手筈をしていたが、先に秋月藩の重臣の一人で「恵利 内蔵助」( 暢堯)が、秀吉と抗戦には徹っしないと判断し和議を薦めたが、結果的に主君である秋月氏に反感を買い、切腹してしまつた。その後、秋月藩も秀吉との戦で岩石城を攻め落とされ降伏した。
その後、戦後処理で高鍋藩三万石に移封されてしまつた。地元では有名な秋月秘話の「原切岩物語」として伝承されている。この小説の中で家臣 恵利 内蔵助は、広島県海田に立ち寄った豊臣秀吉との謁見で、安芸国の浅野弾正(浅野 長吉➜改 長政)氏が取り次いだ。広島浅野藩の初代が、長政の子である浅野 長晟(浅野 幸長の弟)であることを知った。そして、浅野 弾正(長政)は尾張国春井郡 宮後城主である「安井 重継」の子で、信長の家臣である「浅野 長勝」の娘と結婚(婿入り)し、浅野 長政となって時代は流れる。
この小説の主人公である秋月家重臣の一人である「恵利 内蔵助」の出自は、山口県の周防国で柳井~宇部に多い名家でもある「河内山」家、熊毛郡の水木氏(水築家)とも言われている点等、興味深い話である。当時は戦国の世、武士(家臣含む)、姓名が変わりは封建の世の時代での例は、多くあり戸主を家族制度となる『家制度』は最近の戦後改革まで我々庶民(武家以外)の生活まで根付いていた。戦中・戦前の我々の両親・祖父母が生きた時代には養子、取り子取り嫁(第三者家に養子養女となり家を継ぐ)が、多い事は身近に感じるところである。古い家庭に養子が多い事も時代背景からも身近で理解出来る。時間もあることから当県(旧藩)のお殿様である浅野様の家族図を自筆で図式化してみた。
小説ではあるが、巷説と伝承(言い伝え)を交えた歴史小説で巷説は逸話の念が強く、歴史書に近い。また、史実とは歴史上の事実で史実を求めることで歴史学者、歴史家の仕事だと著者は言っている。また、それを知ることが歴史学である。そして解りやすい例として、同じ一つの事件を報道する新聞記事でも、いくつかの新聞に寄って違っているのは珍しい事ではない、発生時点での報道が違っていれば当然だとも言ってる。長い歴史を経て後世から見る史実に曖昧さは月本だとも~·······納得した一日であった。
【秋月秘話】
平成三年九月発刊
史実と巷説と伝承

自筆で書いてみると関連・関係が良く分かる。

当分の間、時間を上手く使いたい。
ウイルス感染でマスク、手洗いは一般化しているが外出控えは自己管理・自己責任から当然だが、今日は休み(シフト勤務)でBSテレビと歴史読書とのスケジュ-ルを決定し、ゆるりとペ-ジをめくった。書は徳川政権の前、豊臣政権時代に遡るが豊臣秀吉が九州平定で京都を発ち、~~広島県の海田に立ち寄った。
福岡黒田藩の支藩である秋月藩の秋月氏は薩摩の嶋津義久氏と同盟を結び、秀吉を迎え手筈をしていたが、先に秋月藩の重臣の一人で「恵利 内蔵助」( 暢堯)が、秀吉と抗戦には徹っしないと判断し和議を薦めたが、結果的に主君である秋月氏に反感を買い、切腹してしまつた。その後、秋月藩も秀吉との戦で岩石城を攻め落とされ降伏した。
その後、戦後処理で高鍋藩三万石に移封されてしまつた。地元では有名な秋月秘話の「原切岩物語」として伝承されている。この小説の中で家臣 恵利 内蔵助は、広島県海田に立ち寄った豊臣秀吉との謁見で、安芸国の浅野弾正(浅野 長吉➜改 長政)氏が取り次いだ。広島浅野藩の初代が、長政の子である浅野 長晟(浅野 幸長の弟)であることを知った。そして、浅野 弾正(長政)は尾張国春井郡 宮後城主である「安井 重継」の子で、信長の家臣である「浅野 長勝」の娘と結婚(婿入り)し、浅野 長政となって時代は流れる。
この小説の主人公である秋月家重臣の一人である「恵利 内蔵助」の出自は、山口県の周防国で柳井~宇部に多い名家でもある「河内山」家、熊毛郡の水木氏(水築家)とも言われている点等、興味深い話である。当時は戦国の世、武士(家臣含む)、姓名が変わりは封建の世の時代での例は、多くあり戸主を家族制度となる『家制度』は最近の戦後改革まで我々庶民(武家以外)の生活まで根付いていた。戦中・戦前の我々の両親・祖父母が生きた時代には養子、取り子取り嫁(第三者家に養子養女となり家を継ぐ)が、多い事は身近に感じるところである。古い家庭に養子が多い事も時代背景からも身近で理解出来る。時間もあることから当県(旧藩)のお殿様である浅野様の家族図を自筆で図式化してみた。
小説ではあるが、巷説と伝承(言い伝え)を交えた歴史小説で巷説は逸話の念が強く、歴史書に近い。また、史実とは歴史上の事実で史実を求めることで歴史学者、歴史家の仕事だと著者は言っている。また、それを知ることが歴史学である。そして解りやすい例として、同じ一つの事件を報道する新聞記事でも、いくつかの新聞に寄って違っているのは珍しい事ではない、発生時点での報道が違っていれば当然だとも言ってる。長い歴史を経て後世から見る史実に曖昧さは月本だとも~·······納得した一日であった。
【秋月秘話】
平成三年九月発刊
史実と巷説と伝承

自筆で書いてみると関連・関係が良く分かる。

当分の間、時間を上手く使いたい。