十年以上前になると思いますが、割箸は、森林伐採を促進するものだから使わないほうが良い、と言う意見が識者等から出るや否や、いや、割箸こそ間伐材の有効利用が出来るエコロジーなものだ、と言う意見がかぶさって、どっちなのー?と結論もよくわからぬままに、マスコミの話題からも消えてしまいました。
何年か前、たまたま行ったネットワーク地球村の高木善之さんの講演会で、割箸の9割以上は中国から輸入したもので、当時、中国で起こった洪水は、日本に輸出する割箸を作るために、行過ぎた伐採をしたことによる森林破壊が原因であったと聞きました。
そのとき、講演会の主催者の方たちにいただいたのが、写真の手作りの箸袋でございます。

一つ一つ、作るのは大変だったと思いますが、この箸袋にお箸を入れて持ち歩けば、割箸を使わなくてもすみますよ、という、主催の奥様たちの心のこもったお箸袋。大切に使わなければ・・・。
和心を大切に、お箸も気取って春慶塗の箸をチョイスしてみました。
この箸袋が優れものなのは、どんな長さのお箸でも入れられるということです。
ふつう箸箱というのは、箸の大きさに合わせてそろえるものですが、箸の長さに合わせて先を折りたたんで、くるっと紐で縛るので、このような男性サイズの箸でも子供用の小さい箸でもカバーできます。すごいっ!
ただし、1つ難点があって、箸が直接袋に当たらないように、不要のチラシなど使って、中にあらかじめ折った紙を入れておかなければなりません。
これが、なんと言うことはないのですが、使い終わった箸は不衛生ですから、使った後はそのつど、この中に紙を折って入れかえるのが、ちょっとひと手間なんですよね。
見栄えはとってもいい感じなんですが。
それでというわけで・・・これだ!

100円ショップは、流通をおかしくさせた元凶とも言われてはいる・・・しかし、これは便利でした。
おそろいの色の箸ケースがついて、この手前の箸と共に100円(税別)。ちょっと短かめだけど慣れてしまえばなんでもなかったし、先端の菜箸仕様のスジがあることで、麺類が食べやすいので、蕎麦屋さんで重宝。しかもケースは、シンプルなかぶせのプラスチックなので、使い終わった後は、箸と共にケースもザーッと洗って、すぐにきれいになります。ふたがパカッとはずれないように、輪ゴムでとめてバックにいれとけば終了です。
見栄えは悪いけど、回転寿司にもぴったりでしょう(笑)
よそゆきには上のお箸、近所には下のお箸。持ち忘れちゃった時は、しょうがない。
なお、成長の早い竹で作られた竹箸や、杉などの間伐材を使っているようなお店では、出てきたお箸を使うようにしています。
私に出来るささやかな、ハチドリのひとしずく
参考サイト ★間伐材だったというのは昔の話?
★地球村通信ニュース「ロシアの森が次のターゲット」
何年か前、たまたま行ったネットワーク地球村の高木善之さんの講演会で、割箸の9割以上は中国から輸入したもので、当時、中国で起こった洪水は、日本に輸出する割箸を作るために、行過ぎた伐採をしたことによる森林破壊が原因であったと聞きました。
そのとき、講演会の主催者の方たちにいただいたのが、写真の手作りの箸袋でございます。

一つ一つ、作るのは大変だったと思いますが、この箸袋にお箸を入れて持ち歩けば、割箸を使わなくてもすみますよ、という、主催の奥様たちの心のこもったお箸袋。大切に使わなければ・・・。
和心を大切に、お箸も気取って春慶塗の箸をチョイスしてみました。
この箸袋が優れものなのは、どんな長さのお箸でも入れられるということです。
ふつう箸箱というのは、箸の大きさに合わせてそろえるものですが、箸の長さに合わせて先を折りたたんで、くるっと紐で縛るので、このような男性サイズの箸でも子供用の小さい箸でもカバーできます。すごいっ!

ただし、1つ難点があって、箸が直接袋に当たらないように、不要のチラシなど使って、中にあらかじめ折った紙を入れておかなければなりません。
これが、なんと言うことはないのですが、使い終わった箸は不衛生ですから、使った後はそのつど、この中に紙を折って入れかえるのが、ちょっとひと手間なんですよね。
見栄えはとってもいい感じなんですが。
それでというわけで・・・これだ!

100円ショップは、流通をおかしくさせた元凶とも言われてはいる・・・しかし、これは便利でした。
おそろいの色の箸ケースがついて、この手前の箸と共に100円(税別)。ちょっと短かめだけど慣れてしまえばなんでもなかったし、先端の菜箸仕様のスジがあることで、麺類が食べやすいので、蕎麦屋さんで重宝。しかもケースは、シンプルなかぶせのプラスチックなので、使い終わった後は、箸と共にケースもザーッと洗って、すぐにきれいになります。ふたがパカッとはずれないように、輪ゴムでとめてバックにいれとけば終了です。
見栄えは悪いけど、回転寿司にもぴったりでしょう(笑)
よそゆきには上のお箸、近所には下のお箸。持ち忘れちゃった時は、しょうがない。

なお、成長の早い竹で作られた竹箸や、杉などの間伐材を使っているようなお店では、出てきたお箸を使うようにしています。
私に出来るささやかな、ハチドリのひとしずく

参考サイト ★間伐材だったというのは昔の話?
★地球村通信ニュース「ロシアの森が次のターゲット」










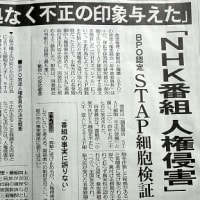




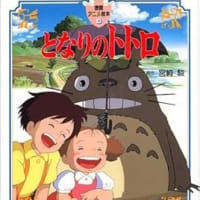
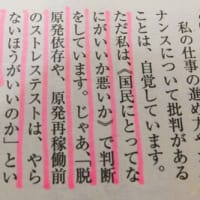
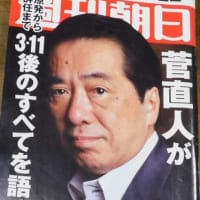








箸袋の事をはじめて知りました
どんなものかはこの写真でよく分かります。
とてもしゃれていますね。
ちょっと使うのには面倒なこともあるようですが、
どんなサイズの箸にも合うというところがいいですね。
風呂敷きの機能を似ているかな?
風呂敷と通じるところがありますね。
おしゃれな風呂敷もいただいたりしましたが、いまいち、使いこなせていません。(小池百合子さんが推奨してたからからか・・・。)
本当は、根が怠け者なので、めんどくさいことが苦手なんですよ。
「割り箸」は確かに間伐材を使っていましたが、
残念ながら、経済原則にそぐわなくなってしまいました。
というのは、山林の間伐作業をすると何がしかの補助金がお上から交付されていたのです。その上その間伐材もそれなりの価値を生んでいたのですが、残念ながらそれ以上の廉価で、その膨大な消費量を補う中国産が出回ったのです。(これは日本商社の仕込みです)
農家では村有林の維持管理には欠かせない間伐作業
だったのですが、若者の農村離脱と高齢者化は逃れられず現在に至っています。
高級品の代名詞である「マッタケ」が台所の焚き付け(若い人にはわからないでしょうが、昔ガスも電気もない時代は、コンロと呼ばずに「おくどさん」といって火を燃やしていました。その火を燃やす導火線のような役割を松葉や杉葉なければ新聞紙などを代用していました)取りに行く事によって松林の掃除に繋がって更に次年度のマッタケを生産したのですが、そうしなくなったのでマッタケが松葉やその他の枯れ葉で押しつぶされて出なくなってしまったのと同様です。
そういう事って世の中結構あるのですよ。生活向上と文化生活向上、効率化、合理化、人間が人間を苦しめている側面を直視する必要がある時代です。
(やま~だのな~かの一本足の案山子が言うのですから、当たらずとも遠からず、実体験です)
そうですね。間伐材の有効利用は、日本の林業を守る上でも、大事なことだったのですが、おっしゃるように経済原則にそぐわなくなってしまったのですね。
安い木材を伐るために中国は森林破壊が起き、日本では林業がだめになる・・・経済の原則は、もはや持続可能な資源保持のためには、害をもたらして何も生み出しません。このままのやり方を続ければ、悲しい末路をたどるしかないのかもしれません。
>そういう事って世の中結構あるのですよ。生活向上と文化生活向上、効率化、合理化、人間が人間を苦しめている側面を直視する必要がある時代です。
そうですね。私もそのように思います。かつては、間伐材を利用した割り箸が、使用後焚きつけなどに燃やされて灰は、また肥料になったとも聞いています。
これは江戸時代の循環システムと同じですよね。いま、江戸の暮らしが見直されています。あの知恵を現代になんとか生かしてゆきたいですね。
おくどさんのお話は、勉強になりました。
マツタケも、松葉の有効利用があるから、松林の環境保全になり、育つことができるのですね。
案山子さん、またいろいろ教えてください。ありがとうございました。