
ずいぶん前に読んだエッセーだけど、小説家であり医師でもある、ある作家の一文が印象に残っている。
そこには、医師として、たくさんの死にも、向き合ってきたから言えることだとして、人間の体は、死んだらただのモノとなってしまうだけ、その存在は永遠に失われてしまうのだ、というようなことが、きっぱり・はっきりと書かれていた。
それは、物理的には、その通りだろう。
多くの死と向き合わねばならないという職業柄、それぞれの人の死に対して、いちいち精神的な何かや霊的な何かを感じていたら身が持たないということもあるだろう。
そう言い切らなければ、死と向き合う仕事など、やっていられないのかもしれない。
医師としての視点は、現状それでいいのかもしれないけれど、しかし、作家としてはどうなのか。
それ以来、その作家の小説は、なぜだか底が浅いような気がして、まったく読む気がしなくなってしまったのも事実。
目には見えなくても、あるものは、ある。
目には見えなくてもあるんだと、そのことは、古今東西、多くの人々が何かの形で、語り継いできたことなのだけど、左脳ばっかり鍛えているとわからなくなっちゃうのかも・・・。
頭で考えれば、どつぼにはまってとっぴんしゃん。ぬけたら、どんどこしょ~、でしょ。(笑)
ダイヤモンド・オンラインに、外科医柴田高氏の書いた、こんな記事があった。
興味深かったので、以下、記事全文掲載します。
■「お坊さまのお仕事」も医療のひとつ(ダイヤモンド・オンライン) - goo ニュース
外科医になって3年目ごろのある日、家へ帰ると遠い親戚に当たるというお坊さまが来ておられて、母と昔話をしていた。私が挨拶をして横に座ると、突然そのお坊さまが
「たかしちゃん、お医者さんだそうですね。患者さんは元気になられる場合もあるけど、亡くなることもあるでしょう」
と、私に話しかけられた。
「はい、今はガン末期の方のお世話が多くて」と私。
「そうですか。最期に立ち会われるんですね」とお坊さま。
「死亡確認が月に2、3回はあります」と私。
「悪いことはいいません。亡くなられた方に向かわれた後は、必ず心の中でかまいませんから手を合わせて、南無阿弥陀仏を唱えてくださいね」とおっしゃって、お坊さまはこう続けた。
「いろいろな思いを抱いて亡くなられる方がいます。どんな方でもご冥福を祈る思いをそれぞれの霊に伝えてください」
私は“霊”については、そのときはあまり理解できなかったが、それ以降必ず、ご冥福を祈る思いを込めて心の中で「南無阿弥陀仏」と手を合わせることを実行した。
その後勤めた病院での出来事。
その病院は戦後まもなく建てられて老朽化が進んでいたため、新病院への移転構想が立てられていた。あるとき、三十代後半の独身女性の患者さんが手術後合併症を起こして退院できないまま、亡くなられるという不幸なことが起こった。
亡くなられる数日前、廊下で歩行器を使って懸命に歩かれていたのを見かけた私は「がんばれてますね」と声をおかけしたが、その髪が急に白くなっているのに驚いたのだった。
そして亡くなられたその日、私は病室の前を通りかかり、名札の名前が変わっているのに気づいた。詰所でたずねると「昨晩、亡くなられました」と担当のY看護師が答えてくれた。胃ガンの根治手術で縫合不全という合併症が起こり何度も手術や処置を行った。半年近い入院で、合併症がよくなったころから免疫が低下し、抗がん剤予防投与ができないこともあり、早期にガンが再発してしまったのだった。
そのとき「ピンポン、ピンポン」と名札の変わったその病室から患者さんのコール。「ハーイ、どうなさいました。すぐ行きますね」と出て行ったY看護師が、しばらくすると悲壮な顔をして戻ってきた。「患者さんが金縛りにあってて…、髪の毛の白い女性が夢に…」と言葉を詰まらせる。
居合わせた詰所の数名は、一瞬で私と同じことを考え、血の気が引く思いにとらわれた。
その夜から、その病棟はただ事ではなかった。少なくとも亡くなられたあの患者さんを知る者にとっては。
日ごろは日常診療で目の前を患者さんがつぎつぎ入退院され、野戦病院のように手術や死亡確認が行われている。そんなふうだから医師や看護師は、亡くなられた患者さんの“霊”を意識する暇など皆無だ。しかし、そのときばかりは特別だった。若くして亡くなられた患者さんを思うと、彼女のつらい思いや苦労が頭をよぎり、その無念さが思われてならないのだ。
怖いとか、恐ろしいという感覚はなかった。ただ、肉体はもうこの世にはない患者さんの“気”が、まだ病室や病棟に余韻として残っていると私は感じた。
数日後、その病棟の当直業務が私に回ってきた。深夜業務に入る看護師さんの申し送りを聞こうと詰所に行くと、看護師さん同士が“その話”をしている。
「まだ、病棟におられますよ。私感じるから」と若い看護師。
「先生、早く成仏するように伝えてくださいよ。今夜は2人ほど危ない患者さんもいらっしゃるのに」と別の看護師。思わず私は「そんなこといわれてもあの世の医者じゃないから」と答えた。
そのとき遠隔モニターの心電計のひとつからピーピーとアラーム音が鳴り響く。
「あ、Mさんだ」
アラームを切り、「316号の個室です。胃がん末期で酸素は5リッター流しています。主治医のN先生からご家族に急変する可能性の説明はされています」と若い看護師が告げる。すぐに腰を上げた私は聴診器とペンライトを持ち316号室へ駆けつけた。
狭い病室へ入ると、何回かお話をしたことのある奥さんと娘さん、息子さんが身を寄せ合っている。患者のMさんは肩を大きく揺らし、枕元の酸素ボンベからはシューシュー音が鳴っている。私は呼吸音を聴診した後、「Mさん、つらいですね、でも心配ないですよ。今夜は私がいますよ」といいながら手を握った。Mさん
は私に気づき「うん、うん」とうなずいてくれた。
深夜回診をして「今夜はまだ大丈夫だな」と多少の安堵感をもって、トイレで用を足そうと立ち止まったとき。一息ついた私は、背筋に“何か”を感じた。
「あ、まだ居られるんですね。大丈夫、大丈夫、よくがんばられましたね。心配ないです、心配ないです。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏」私は心で手を合わせ念じ続けた。
結局Mさんは翌日亡くなられた。10日ほど経ってその病棟を訪ねると、看護師詰所から、“霊”を感じるといっていた若い看護師やY看護師たちの明るい笑い声が聞こえてきた。
「もう、みなさん退院されたんですね」と私がいうと「え? 誰の話ですか」と怪訝な顔をした。
亡くなられた方に対してご冥福を祈ることも、医療現場では大切なことであり、また期待されているのだと思う。
体は死んでも、魂はなくならない。魂の故郷へ、帰るだけ(自殺はそう単純ではなさそうだけど・・)
そんなことを、少しでも理解してくださるこのようなお医者様が増えてくれば、心のケアも含めて、終末医療にも変化が訪れる予感がする。
また、そういうことが、どんどん公けに話されるようになれば、人の恐怖や不安につけこんで、ぼったくりをする偽宗教や偽霊能者の嘘も、わかってくるだろう。

スピリチュアリティ・カウンセリング(飯田史彦・著)
真に人を救うのは、
薬や奇跡やスピリチュアルな力ではなく、
愛情と希望である。
(本書・帯より)
国立大学教授という仕事を辞めてまでも、飯田史彦さんがスピリチュアル・ケア研究所「光の学校」を設立されたのも、このためなんだろうな。
















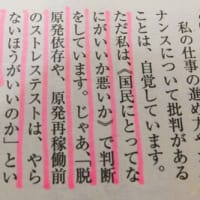









そして、母を看取って・・
心臓が止まり、脳が停止して、人は「死」を迎えるわけですが、
その時、亡くなった。とうい自覚・・
当の本人は、気付いていないのではないかと・・思います。
気付かないまま、留まる。
残された人の役目は、
亡くなった人の
心穏やかな気付きのお手伝いをしてやることだと思います。
>残された人の役目は、
亡くなった人の
心穏やかな気付きのお手伝いをしてやることだと思います
そうかもしれませんね。
また、そうすることで残された者も、安らかな思いになれますから。
>「まだ、病棟におられますよ。私感じるから」と若い看護師。
10年前にある病気で入院していた日のある日の深夜、わたしはスリッパ履きのような、妙に気になる足音を耳にして、巡回に来た看護師さんにそのことを話したら、「あー 大ちゃんさんもとうとう聞いてしまいましたか」と。
聞けば、看護師さんたちの間ではかなり有名な、誰も歩いていない廊下に響く足音なのだそうで、どうも以前入院していてそこで亡くなった方のもののようなのです。
まだそこをさまよっていたんですね、きっと。
あまり書くと背中がぞくぞくしてくるので、このお話はこれにて。(笑)
うちの不思議人間も、病院のエレベーターのすみや、待合室の椅子なんかに、色の薄くなった(透けた感じ)の人物が見えたりするので、病院にはあまり、行きたがらなかったのですよ(汗)。
でも、飯田史彦さんの本で、
○こういうのは幽霊ではなくて、「残存思念」というものであることと、
○生きていた時の思いが強く残っている場所で、敏感な人が反応してしまう
と、いうことが書かれていて、「本物の幽霊ではない」ことが分かって、すごくほっとしたのですよ。
(でも、ごくまれに、そうじゃないこともあるらしいですが・・冷汗)
どうかしたら、私も、南無阿弥陀仏・どうぞ成仏してくださいねと、心の中でつぶやくようにしています。