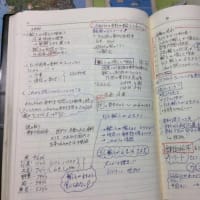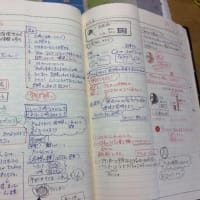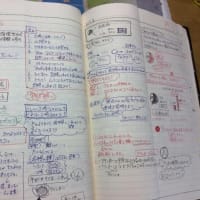30代になると、研究会では
いろいろな質問をするようになりました。
しかし、それは今考えると
「自己満足」的なものが非常に多かったような気がします。
例えば、社会科の授業であれば
=======================
社会科の言語活動である「解釈」という活動を
どう捉えて授業されたのですか?
=======================
指導案に明記されてあった”概念的知識”について
6年の歴史の授業においては
どのように考えられておられますか?
=======================
などのような質問です。
たまたま自分が知っていた、もしくは勉強していた
専門的な領域の用語を、
得意げにしゃべっていたのです。
これは授業者と自分の、一対一の対話になってしまい、
周りは「何を言っているんだ?」
という雰囲気になりました。
こんな個人的な質問は、本来授業が終わった後、
授業者の方に労いの言葉をかけながら、お聞きすれば良い事です。
自己満足に過ぎない質問は控える・・
その過ちに気づいてから、研究会での発言内容が変わってきました。
=========================
周りにも「学び」が広がる
価値のある答えを引き出す質問をしよう
=========================
と心がけるようになりました。
例えば、
=========================
(小中連携で授業をされた先生に対して)
「小中学校で、お互い授業を参観された際、
校種の違いで驚かれた事はなんですか?」
「授業で活用された絵資料の扱いについては、
本日の流し方以外にもいろいろ考えられたと思うのですが、
どのような構想を他にお持ちでしたか?」
「研究主題の”討論”までもっていくために、
単元計画の中でどのような工夫をされたのですか?」
「とても構造的な板書に感動したのですが、
児童の思考をどのようにまとめようと
いつもこころがけていらっしゃるのですか?」
=========================
「授業者の授業力を、向上させてあげよう」
「自分の知識を、見せつけさせよう」
といった不遜な考え方ではなく、
==========================
如何にこの研究会で参会者全体の学びを深めるか?
==========================
ということを意識するようになりました。
そのような意識のもと質問をすると、授業者の方は、笑顔で
自分の考えを話してくださるのでした。
そして参会者の方々がうなずいたり、メモをとったりする姿が
目に入るようになりました。
独りよがりの質問を繰り返していたころには
全く見られない光景でした。
※
ただし、やはり本当に授業の中で気になって、
全体の場で確認した方がいいと思った項目については
当然質問しました。
また、協議の柱に沿って、自分の質疑は妥当かどうかも
毎回確認をしていました。
いろいろな質問をするようになりました。
しかし、それは今考えると
「自己満足」的なものが非常に多かったような気がします。
例えば、社会科の授業であれば
=======================
社会科の言語活動である「解釈」という活動を
どう捉えて授業されたのですか?
=======================
指導案に明記されてあった”概念的知識”について
6年の歴史の授業においては
どのように考えられておられますか?
=======================
などのような質問です。
たまたま自分が知っていた、もしくは勉強していた
専門的な領域の用語を、
得意げにしゃべっていたのです。
これは授業者と自分の、一対一の対話になってしまい、
周りは「何を言っているんだ?」
という雰囲気になりました。
こんな個人的な質問は、本来授業が終わった後、
授業者の方に労いの言葉をかけながら、お聞きすれば良い事です。
自己満足に過ぎない質問は控える・・
その過ちに気づいてから、研究会での発言内容が変わってきました。
=========================
周りにも「学び」が広がる
価値のある答えを引き出す質問をしよう
=========================
と心がけるようになりました。
例えば、
=========================
(小中連携で授業をされた先生に対して)
「小中学校で、お互い授業を参観された際、
校種の違いで驚かれた事はなんですか?」
「授業で活用された絵資料の扱いについては、
本日の流し方以外にもいろいろ考えられたと思うのですが、
どのような構想を他にお持ちでしたか?」
「研究主題の”討論”までもっていくために、
単元計画の中でどのような工夫をされたのですか?」
「とても構造的な板書に感動したのですが、
児童の思考をどのようにまとめようと
いつもこころがけていらっしゃるのですか?」
=========================
「授業者の授業力を、向上させてあげよう」
「自分の知識を、見せつけさせよう」
といった不遜な考え方ではなく、
==========================
如何にこの研究会で参会者全体の学びを深めるか?
==========================
ということを意識するようになりました。
そのような意識のもと質問をすると、授業者の方は、笑顔で
自分の考えを話してくださるのでした。
そして参会者の方々がうなずいたり、メモをとったりする姿が
目に入るようになりました。
独りよがりの質問を繰り返していたころには
全く見られない光景でした。
※
ただし、やはり本当に授業の中で気になって、
全体の場で確認した方がいいと思った項目については
当然質問しました。
また、協議の柱に沿って、自分の質疑は妥当かどうかも
毎回確認をしていました。