図解 自然な姿を楽しむ「庭木」の剪定/平井孝幸/講談社/2012
作庭家が書いた、雑木の剪定のやり方に書いてある本。
第一部の「雑木に適した剪定の基礎」は庭を持っている人にお薦めできる内容である。
幹を太らせず、細くしなやかな枝振りの庭木を維持したい方は、必読である。
20頁には、「しなやかな枝を遺したまま、一定の生長ペースで雑木を維持するには、毎年全体の1/3程度の枝を落としていくのが剪定の大きなポイント」だと書いてある。
また、同頁には、
「現状よりも二回りくらい小さな樹冠にするイメージを持って、下の方から伸びている若くて細い枝を主幹に見立て、新たな主幹に差し替えるつもりで切り戻していきます。主幹は太くて重いので、一度にすべて切り落とそうとすると危険です。2回に分けて切りましょう。」とある。
24頁には、
「上手な手入れほど、剪定後に見てどこを切ったかがわからない。床屋に行ったばかりのような、さっぱりした印象になったら、うまく剪定できなかったということ。シルエットを変えずに樹冠を小さくするのが、雑木の手入れの重要なポイントなのです。」とある。
参考としたいものである。
作庭家が書いた、雑木の剪定のやり方に書いてある本。
第一部の「雑木に適した剪定の基礎」は庭を持っている人にお薦めできる内容である。
幹を太らせず、細くしなやかな枝振りの庭木を維持したい方は、必読である。
20頁には、「しなやかな枝を遺したまま、一定の生長ペースで雑木を維持するには、毎年全体の1/3程度の枝を落としていくのが剪定の大きなポイント」だと書いてある。
また、同頁には、
「現状よりも二回りくらい小さな樹冠にするイメージを持って、下の方から伸びている若くて細い枝を主幹に見立て、新たな主幹に差し替えるつもりで切り戻していきます。主幹は太くて重いので、一度にすべて切り落とそうとすると危険です。2回に分けて切りましょう。」とある。
24頁には、
「上手な手入れほど、剪定後に見てどこを切ったかがわからない。床屋に行ったばかりのような、さっぱりした印象になったら、うまく剪定できなかったということ。シルエットを変えずに樹冠を小さくするのが、雑木の手入れの重要なポイントなのです。」とある。
参考としたいものである。










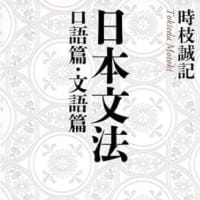




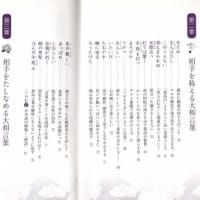
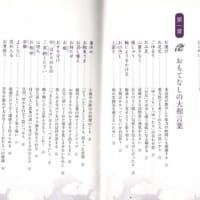
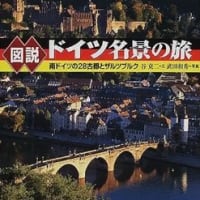
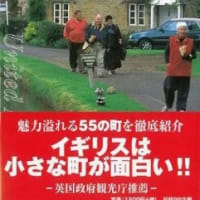
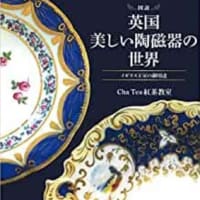






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます