(下島君の報告、続きです。お読みください。)
海は満潮をむかえ、強い風と相まって、高波を引き起こしていた。壊れた防波堤のかわりにと、道の脇には土嚢が積まれていたが、波はそこに当たって砕け、道の片側をしぶきで濡らしていた。ボランティアセンターに戻り、今日のボランティアを終えた旨を伝える。お疲れ様でした、と一声掛けられ報告は終わった。
日は落ちてきたが、まだ沈んではいない。志津川に沿って、廃墟の町を進む。
親の知り合いが、地元の農家を間借りしてチャリティーコンサートを開くというので、それを聴きに行くことになっていた。わずかに残った気仙沼線の盛り土を超え、林に引っかかった車を横目に進むと、小さな赤い橋がみえた。国道から離れ、橋を渡る。海から遠く離れた山間の田畑まで、津波は押し寄せ、瓦礫だけを残していった。しかし、波を被らなかった場所は、今年も田植えがされ、青い稲の葉を風になびかせていた。
地図にない、曲がりくねった道をゆく。森を抜け、坂をのぼると、木製の郵便ポストが立っていた。柵の中をのんびりと歩き回る豚たち。その中に、会場はあった。小さな女の子がシャボン玉を飛ばしていた。テーブルの上にはパンとレタスとハムが並び、大人達はビールやワインを片手に歓談している。
下界が現実だとしたら、この風景は形而上の世界とでも言い表せばよいのか。そう呆然としていると、チョビ髭の家主がお酒を勧めてきた。
「飲みましょう。飲まなければならない。そうでしょう?」
家主さんは豚飼いであり、写真家でもあった。山の上で豚を飼い、生計を立てていた。彼の写真の中には、のどかな志津川の町がたたずんでいた。
「下の光景を見ましたか? ひどいものでしょう。文明に対する警告だと、私は思いますね」
「なぜ、津波が何度も押し寄せている町の防災庁舎を、あんな平地に造ったのか、分かりますか? 効率がいいからですよ。人々が高台に住もうとしないのだってそうだ。こんなひどい被害が出たのは、人災ですよ。我々が効率を追い求め続けた結果。そうじゃありませんか」
その演説の横で笑っている大柄な男性は床屋だったと自己紹介した。私の隣で先ほどから、工具で金属加工をしている若者は、金属パイプを加工して笛を造って売り歩き、その売り上げを被災地に寄付しているという。










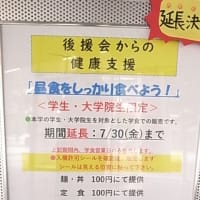





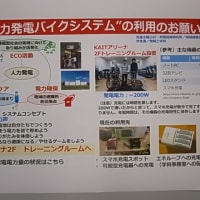








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます