
上州のかかあ天下と空っ風!
これが、群馬県に対する大方の大ざっぱなイメージだろう。
仕事で高崎市を中心に、県下をよく回るが、知るほどに良さが分かってくる。
人情味に溢れ、伝統文化を大事にすると同時に、モノづくりなど近代的な産業が根付いている。
県庁の所在地は前橋市だが、新幹線の要所でもある高崎市の発展が著しい。(昨年、市人口でも県下一に)
下仁田ネギ、深谷ネギ、コンニャクなどの農産物、自然の恵みを生かした漬物は有名。街中、郊外に散在するうどん・ソバの店構えも、趣味の良い和風造りが多く、土地柄が出ているように感じる。
”かかあ天下”の真意は?
単純に女性上位、ダメ亭主の意味ではないという。
逆に、「男らしくいて欲しい」というおんな心から、女性がひたむきにガンバリ、家事・家計全般を切り盛りする。(確かに老いも若きもしっかり者の女性が多い気がする。)
結果、旦那には競輪、競馬、博打などで楽しんでもらう。
こんな極めて日本的な風土が残っている、という説に共感を覚える。
今、思い返してみても、男っ気があり、侠気を感じる男性が多い。
福田、中曽根、小渕、現福田という4人の首相を輩出しているのも、義理人情に支えられた土地柄と関係がありそう。
(対照的に、前小泉首相の横須賀市は、米軍基地などアメリカさま様で、よく言えば先進的、ドライに割り切る土地柄という気がする。)
昨日、仕事帰りの午後、高崎市駅前通りの「全国都市緑化ぐんまフェア」をのぞいてみた。近代的な市役所(21F建?)と高崎城址の周辺に、広場花壇、大通りの植込み、屋内イベントが開かれている。
「上州ぐんま」は江戸中期から、京都・西陣の職人が桐生に移住して「西の西陣、東の桐生」と言われるほどの絹織物の生産地となった。
数年前から、湘南ライン(高崎線・山手線・東海道線乗り入れ)ができ、民営化の恩恵と思っていたが、戦前も東のシルクロードとして、ぐんま→新宿→横浜→輸出という貿易ルートが出来ていたという。もう一つのルート:八王子→今のJR横浜線沿いの街道→横浜という多摩のシルクロードも明治の初めから開かれていた。
この染色(文化)と機織(技術)の伝統が、今桐生・高崎・大田・伊勢崎に広がる多産業に跨るモノづくり拠点のルーツとなっているのだろう。
ギャラリー「絹と染めのアート」で染色に関心を持った。
草木染めの手法の解説、材料とその染色した生地の展示で、身近な草・木からよくもあんなきれいな色が出るもんだ、と感心する。
平安朝の十二単(ジュウニヒトエ)は、自然と草木の変化を衣の色で表現してあり、大和心の奥床しさの極みか。
このフェアは前橋市/太田市でも行われ、無料バス運行(6/8まで開催)されているので、もう1~2回は見て回りたい。
これが、群馬県に対する大方の大ざっぱなイメージだろう。
仕事で高崎市を中心に、県下をよく回るが、知るほどに良さが分かってくる。
人情味に溢れ、伝統文化を大事にすると同時に、モノづくりなど近代的な産業が根付いている。
県庁の所在地は前橋市だが、新幹線の要所でもある高崎市の発展が著しい。(昨年、市人口でも県下一に)
下仁田ネギ、深谷ネギ、コンニャクなどの農産物、自然の恵みを生かした漬物は有名。街中、郊外に散在するうどん・ソバの店構えも、趣味の良い和風造りが多く、土地柄が出ているように感じる。
”かかあ天下”の真意は?
単純に女性上位、ダメ亭主の意味ではないという。
逆に、「男らしくいて欲しい」というおんな心から、女性がひたむきにガンバリ、家事・家計全般を切り盛りする。(確かに老いも若きもしっかり者の女性が多い気がする。)
結果、旦那には競輪、競馬、博打などで楽しんでもらう。
こんな極めて日本的な風土が残っている、という説に共感を覚える。
今、思い返してみても、男っ気があり、侠気を感じる男性が多い。
福田、中曽根、小渕、現福田という4人の首相を輩出しているのも、義理人情に支えられた土地柄と関係がありそう。
(対照的に、前小泉首相の横須賀市は、米軍基地などアメリカさま様で、よく言えば先進的、ドライに割り切る土地柄という気がする。)
昨日、仕事帰りの午後、高崎市駅前通りの「全国都市緑化ぐんまフェア」をのぞいてみた。近代的な市役所(21F建?)と高崎城址の周辺に、広場花壇、大通りの植込み、屋内イベントが開かれている。
「上州ぐんま」は江戸中期から、京都・西陣の職人が桐生に移住して「西の西陣、東の桐生」と言われるほどの絹織物の生産地となった。
数年前から、湘南ライン(高崎線・山手線・東海道線乗り入れ)ができ、民営化の恩恵と思っていたが、戦前も東のシルクロードとして、ぐんま→新宿→横浜→輸出という貿易ルートが出来ていたという。もう一つのルート:八王子→今のJR横浜線沿いの街道→横浜という多摩のシルクロードも明治の初めから開かれていた。
この染色(文化)と機織(技術)の伝統が、今桐生・高崎・大田・伊勢崎に広がる多産業に跨るモノづくり拠点のルーツとなっているのだろう。
ギャラリー「絹と染めのアート」で染色に関心を持った。
草木染めの手法の解説、材料とその染色した生地の展示で、身近な草・木からよくもあんなきれいな色が出るもんだ、と感心する。
平安朝の十二単(ジュウニヒトエ)は、自然と草木の変化を衣の色で表現してあり、大和心の奥床しさの極みか。
このフェアは前橋市/太田市でも行われ、無料バス運行(6/8まで開催)されているので、もう1~2回は見て回りたい。










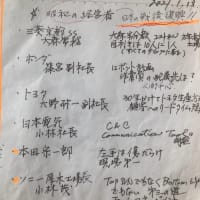
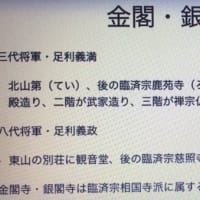
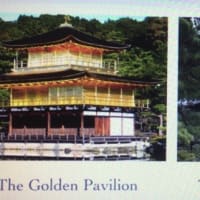
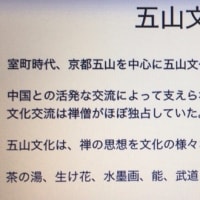
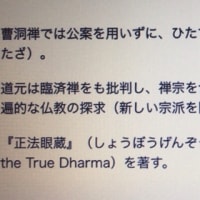
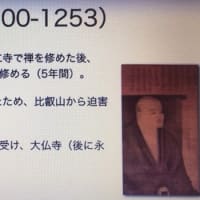
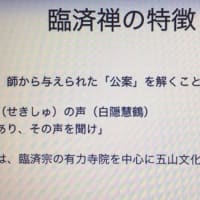
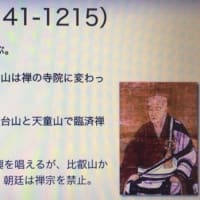
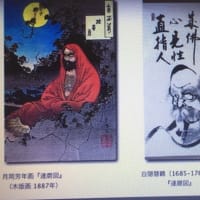
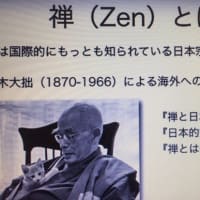
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます