
①ガソリン暫定税率の期限切れ・復活のおかげで、身近な生活で意味のない混乱に巻き込まれている。道路特定財源→一般財源化、廃止→環境税、などの問題を絡んで、与野党の駆け引きによる政治の迷走は収まらない。
(民主党は、道路特定財源の修正案見送り、座して衆院再可決を待つのみ、世論の動向分析に留めるという。空気だけに振り回され、自分がない??)
②後期高齢者医療制度も、年金天引きと低所得者の窮状を強調して、悪法の烙印が押されてしまった。現役保険料の40%も拠出され、膨張を続ける医療費の抑制が主題なのに。(今日5/2の新聞で、参院自民が基礎年金以下の低所得者は全額免除を提言、とある。民主案はないのかな?3年間何を検討していたのだろう)
③年金問題も、社会保険庁の不祥事(消えた記録5000万件/納金着服/不正書換えetc.)を中心に、制度改革そっちのけで役人不信だけを煽るような印象がある。
④再生紙偽装の問題も、役所主導の100%再生を至上命題としたグリーン調達という御旗に屈した感がある。(近日、30%再生を認めその旨表示という修正になりそう。製紙メーカーも最初から言えば良かったのに・・)
グローバリゼーションの急な進行もあり、何とも訳の分からない政治・社会が到来したという実感がある。
衆・参議院の「ねじれ政局」というだけでは説明しきれない何か?があるのではないか。
その何か?を求めて、「”空気”の研究」山本七平著を再読(20年ほど前に一読)した。1977年著だが、今の日本の状態にぴったり当てはまる。
改めて、山本さんの博識と観点、とくにキリスト教を中心とする絶対観からの日本的流儀の弱点の指摘に感服。(目からうろこ)
** 以下、要点と感想 **
”空気”とは、非常に強固でほぼ絶対的な支配力をもつ「判断の基準」であり、それに抵抗する者を社会的に葬るほどの超能力である。
私たち日本人は、常に論理的判断の基準と、空気的判断の基準という、一種のダブルスタンダードのもとに生きている。
山本さんの言う「人工空気醸成法」の基本の背後に、対象への「臨在感的把握」に基づく判断がある。(臨在感=その場の状況では○○せざるを得ないetc.etc.”あなたと私/その場状況判断”という感情中心の相対的世界?)
対象の臨在感的な把握の前提は、感情移入の日常化・無意識化→それにより「生きている」という実感(日本的世界)
感情移入で絶対化されると、自分が対象に支配され「空気」の支配が起こる。
空気支配のもう一つの原則:
対立概念で対象を把握しょうとしないこと。例)一人の人を「善悪という対立概念」ではなく、善玉・悪玉に分けて、それぞれの概念を乗り移らせること。
挿話:
周恩来首相が、田中首相に送った言葉「言必信、行必果:やると言ったら必ずやるサ、やった以上はどこまでもやるサ(玉砕?)」つまり小人(おっちょこちょい)。
「時代先取り」と右へ左へと一目散。
反対に、大人とは、対象を相対的に把握することにより、大局をつかんでこうならない人間のこと。→我々は、「言必信、行必果」なものを純粋な立派な人間、対象を相対化するものを不純な人間と見やすい。
ある時期は「成長」が絶対化され、次の瞬間には「公害」、少し経って「資源」が絶対化される。
「熱しやすく冷めやすい」・・・よく言えば、その場の空気(ムード)に従った「巧みな方向転換」、悪く言えば「お先ばしりのおっちょこちょい」→後で、長い目で見れば、結果的にそれなりに相対化されている。
このやり方は、日本軍の「短期決戦+連続型」だから、「長期持久、長期維持」は期待できない。
持続可能な計画が求められるグローバルな社会では、危険な様相を呈する。(日本の現状の最大の弱点?)
しからば、「空気」に支配されないための問題克服の要点は?
①臨在感を歴史的に把握しなおすこと(日本の流儀:≒アニミズム(物神論?=空気主義)の世界)→いわしの頭も信心から、「もっと大人になれ」、郷に入らば郷に従え。
②対立概念による対象把握(例:旧約聖書の徹底的相対化の世界⇔これに対し、我国では、天皇=偶像的「現人神」、教育勅語=言語による偶像etc.→小泉内閣の何でも規制緩和・民営化が今や諸悪の根源に。)
よくこれだけ、分析的に深く考えるのものだ。
山本さんは、具体的には”水”という疑念に目をむけ、日本の伝統の中に水の効用を説いている。
(民主党は、道路特定財源の修正案見送り、座して衆院再可決を待つのみ、世論の動向分析に留めるという。空気だけに振り回され、自分がない??)
②後期高齢者医療制度も、年金天引きと低所得者の窮状を強調して、悪法の烙印が押されてしまった。現役保険料の40%も拠出され、膨張を続ける医療費の抑制が主題なのに。(今日5/2の新聞で、参院自民が基礎年金以下の低所得者は全額免除を提言、とある。民主案はないのかな?3年間何を検討していたのだろう)
③年金問題も、社会保険庁の不祥事(消えた記録5000万件/納金着服/不正書換えetc.)を中心に、制度改革そっちのけで役人不信だけを煽るような印象がある。
④再生紙偽装の問題も、役所主導の100%再生を至上命題としたグリーン調達という御旗に屈した感がある。(近日、30%再生を認めその旨表示という修正になりそう。製紙メーカーも最初から言えば良かったのに・・)
グローバリゼーションの急な進行もあり、何とも訳の分からない政治・社会が到来したという実感がある。
衆・参議院の「ねじれ政局」というだけでは説明しきれない何か?があるのではないか。
その何か?を求めて、「”空気”の研究」山本七平著を再読(20年ほど前に一読)した。1977年著だが、今の日本の状態にぴったり当てはまる。
改めて、山本さんの博識と観点、とくにキリスト教を中心とする絶対観からの日本的流儀の弱点の指摘に感服。(目からうろこ)
** 以下、要点と感想 **
”空気”とは、非常に強固でほぼ絶対的な支配力をもつ「判断の基準」であり、それに抵抗する者を社会的に葬るほどの超能力である。
私たち日本人は、常に論理的判断の基準と、空気的判断の基準という、一種のダブルスタンダードのもとに生きている。
山本さんの言う「人工空気醸成法」の基本の背後に、対象への「臨在感的把握」に基づく判断がある。(臨在感=その場の状況では○○せざるを得ないetc.etc.”あなたと私/その場状況判断”という感情中心の相対的世界?)
対象の臨在感的な把握の前提は、感情移入の日常化・無意識化→それにより「生きている」という実感(日本的世界)
感情移入で絶対化されると、自分が対象に支配され「空気」の支配が起こる。
空気支配のもう一つの原則:
対立概念で対象を把握しょうとしないこと。例)一人の人を「善悪という対立概念」ではなく、善玉・悪玉に分けて、それぞれの概念を乗り移らせること。
挿話:
周恩来首相が、田中首相に送った言葉「言必信、行必果:やると言ったら必ずやるサ、やった以上はどこまでもやるサ(玉砕?)」つまり小人(おっちょこちょい)。
「時代先取り」と右へ左へと一目散。
反対に、大人とは、対象を相対的に把握することにより、大局をつかんでこうならない人間のこと。→我々は、「言必信、行必果」なものを純粋な立派な人間、対象を相対化するものを不純な人間と見やすい。
ある時期は「成長」が絶対化され、次の瞬間には「公害」、少し経って「資源」が絶対化される。
「熱しやすく冷めやすい」・・・よく言えば、その場の空気(ムード)に従った「巧みな方向転換」、悪く言えば「お先ばしりのおっちょこちょい」→後で、長い目で見れば、結果的にそれなりに相対化されている。
このやり方は、日本軍の「短期決戦+連続型」だから、「長期持久、長期維持」は期待できない。
持続可能な計画が求められるグローバルな社会では、危険な様相を呈する。(日本の現状の最大の弱点?)
しからば、「空気」に支配されないための問題克服の要点は?
①臨在感を歴史的に把握しなおすこと(日本の流儀:≒アニミズム(物神論?=空気主義)の世界)→いわしの頭も信心から、「もっと大人になれ」、郷に入らば郷に従え。
②対立概念による対象把握(例:旧約聖書の徹底的相対化の世界⇔これに対し、我国では、天皇=偶像的「現人神」、教育勅語=言語による偶像etc.→小泉内閣の何でも規制緩和・民営化が今や諸悪の根源に。)
よくこれだけ、分析的に深く考えるのものだ。
山本さんは、具体的には”水”という疑念に目をむけ、日本の伝統の中に水の効用を説いている。










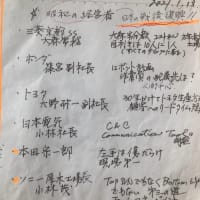
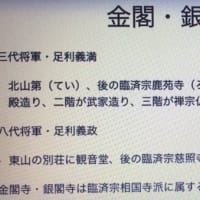
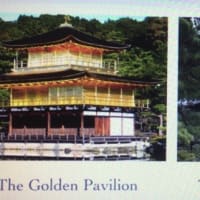
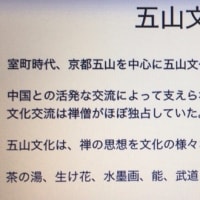
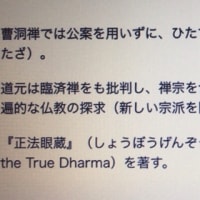
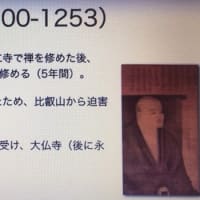
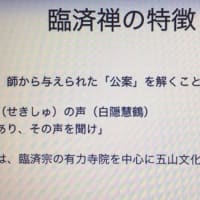
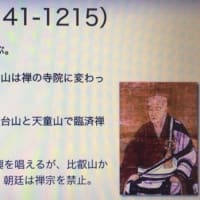
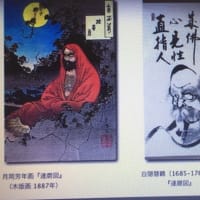
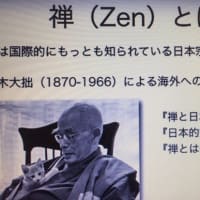
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます