甲州街道を踏破中の友人の誘いで、長寿食で1980年代ころ、マスコミでも話題になった上野原市の民宿に予約して、紅葉を観に行ってきた。
中央線の高尾駅で乗り換え、3連休の中日とあって家族連れやグループで賑わっていた。
ほとんどが、高尾山に向かう人たちのようだ。
相模湖を見下ろす上野原駅は南側に大型商業施設が目立つのみで、人出も少ない。
食事処も2,3件のみで、早めに昼を済ませバスに乗り込み、山懐深く通じているつづら折りの道を進むんで行く。
途中、旧甲州街道から分け入り、相模川の源流という鶴川沿いに刻まれた峡谷が、思ったより深い。
山あいの数軒のが、どこまでも切れないのには驚くほどだ。
目の前にそびえる尾根の向こう側は、多摩の山々となり、都と山梨県の県境だ。
終点から少し手前の西原の学校前でバスを降り、「びりゅう館」に立ち寄る。案内板によると、古くは平安時代の小荘園であったとある。
その頃、日本の人口は5-600万人、すでに大化の改新の律令制度に組み込まれていたのだろう。
飛騨高山でも「飛騨は山また山のため、大上中下4等の”下の下の国”と呼ばれた」とあったように記憶する。
人間が国家の支配を受けないで、生きていける証となる地であって欲しかった!
ここで、坪山から降りてきた3人のシニアハイカーと出合ったが、かなりハードなコースとのことでお疲れのご様子だった。
雑穀のサンプルや唐箕や篩などの農具の他、入り口にはB29が落とした弾頭の破損残骸が展示してあった。

こんな山奥に爆弾を落とすとは!多分、米兵の冷やかしのいたずら心からだろう。
宿まで約5,6km、バス道を外れ、曲がりくねった川沿いの進みながら、両岸の赤や黄色の紅葉を楽しめた。
大半が見ごろを過ぎ、枯れ葉の絨毯だったが、所々に遅めの紅葉が目を引く。
陽当たりの加減で、紅葉する時期がずれる様子が分かる。
川のちょっとした斜面には、区切られた畑が見られる。
予定通り、日没前4:30頃、長寿食の元祖「梅鶯荘バイオウソウ」に到着。

ひと風呂浴びて、広間で夕食を頂く。
さといも、山菜の天ぷら、刺身コンニャク、ジャガイモ(せいだ)、キビの赤飯など、
根菜類がたっぷり並ぶ。むしろ粗食とも言える日本古来の食生活が、この地を長寿村(ユヅハラ村)としてマスコミでも有名にした と言う。
山道の疲れもあり、二人とも身体が快い眠りと一体になったように寝入ってしまった。
翌朝、宿の前の小道を下って沢にかかる橋を渡る。それにしても、濡れ落ち葉で断崖絶壁に足を滑らせそうな坂道が永遠に(笑)記憶に残りそう。
その先にあったわずかな広さの畑に、獣除けの電線とは!宿で聞くと、猿・シカ・イノシシが荒らすらしい。
朝食も、塩シャケの他は、すべて根菜類。
いつもより便通もスッキリ、食生活を見直す良い機会になる気がした。
便利さを求めるだけの生活にも、強烈なインパクトを受けた。
旧い伝統を守る宿の女将姉妹さんに 感謝です。
一句: 晩秋の 長寿の村に 真善美
(駄作、プレバトのおばさんに叱られる?)
帰りも沢沿いの小道を、上野原駅に向けて、約10kmほどテクテクと歩く。
まだ、柚子の実と赤と黄色の紅葉が、目に焼きついている。

中央線の高尾駅で乗り換え、3連休の中日とあって家族連れやグループで賑わっていた。
ほとんどが、高尾山に向かう人たちのようだ。

相模湖を見下ろす上野原駅は南側に大型商業施設が目立つのみで、人出も少ない。
食事処も2,3件のみで、早めに昼を済ませバスに乗り込み、山懐深く通じているつづら折りの道を進むんで行く。
途中、旧甲州街道から分け入り、相模川の源流という鶴川沿いに刻まれた峡谷が、思ったより深い。
山あいの数軒のが、どこまでも切れないのには驚くほどだ。
目の前にそびえる尾根の向こう側は、多摩の山々となり、都と山梨県の県境だ。
終点から少し手前の西原の学校前でバスを降り、「びりゅう館」に立ち寄る。案内板によると、古くは平安時代の小荘園であったとある。
その頃、日本の人口は5-600万人、すでに大化の改新の律令制度に組み込まれていたのだろう。
飛騨高山でも「飛騨は山また山のため、大上中下4等の”下の下の国”と呼ばれた」とあったように記憶する。

人間が国家の支配を受けないで、生きていける証となる地であって欲しかった!
ここで、坪山から降りてきた3人のシニアハイカーと出合ったが、かなりハードなコースとのことでお疲れのご様子だった。
雑穀のサンプルや唐箕や篩などの農具の他、入り口にはB29が落とした弾頭の破損残骸が展示してあった。


こんな山奥に爆弾を落とすとは!多分、米兵の冷やかしのいたずら心からだろう。
宿まで約5,6km、バス道を外れ、曲がりくねった川沿いの進みながら、両岸の赤や黄色の紅葉を楽しめた。

大半が見ごろを過ぎ、枯れ葉の絨毯だったが、所々に遅めの紅葉が目を引く。
陽当たりの加減で、紅葉する時期がずれる様子が分かる。
川のちょっとした斜面には、区切られた畑が見られる。

予定通り、日没前4:30頃、長寿食の元祖「梅鶯荘バイオウソウ」に到着。


ひと風呂浴びて、広間で夕食を頂く。
さといも、山菜の天ぷら、刺身コンニャク、ジャガイモ(せいだ)、キビの赤飯など、
根菜類がたっぷり並ぶ。むしろ粗食とも言える日本古来の食生活が、この地を長寿村(ユヅハラ村)としてマスコミでも有名にした と言う。
山道の疲れもあり、二人とも身体が快い眠りと一体になったように寝入ってしまった。
翌朝、宿の前の小道を下って沢にかかる橋を渡る。それにしても、濡れ落ち葉で断崖絶壁に足を滑らせそうな坂道が永遠に(笑)記憶に残りそう。

その先にあったわずかな広さの畑に、獣除けの電線とは!宿で聞くと、猿・シカ・イノシシが荒らすらしい。

朝食も、塩シャケの他は、すべて根菜類。
いつもより便通もスッキリ、食生活を見直す良い機会になる気がした。
便利さを求めるだけの生活にも、強烈なインパクトを受けた。
旧い伝統を守る宿の女将姉妹さんに 感謝です。
一句: 晩秋の 長寿の村に 真善美
(駄作、プレバトのおばさんに叱られる?)
帰りも沢沿いの小道を、上野原駅に向けて、約10kmほどテクテクと歩く。
まだ、柚子の実と赤と黄色の紅葉が、目に焼きついている。











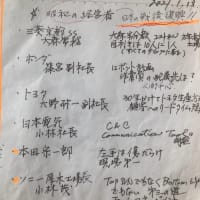
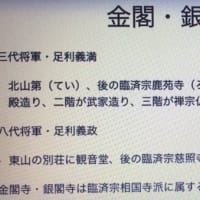
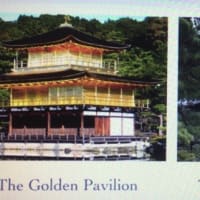
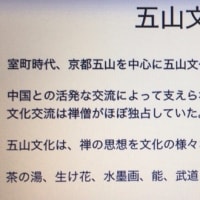
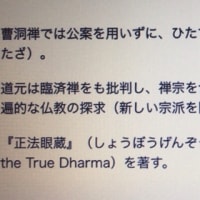
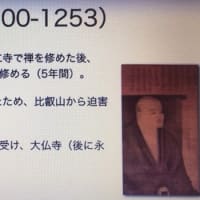
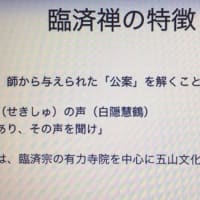
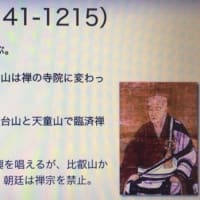
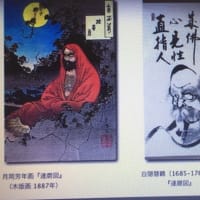
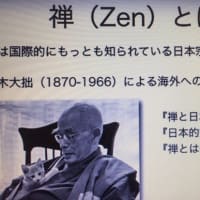
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます