
秋田県:角館のイメージは
”武家屋敷とシダレザクラ”品格と華という感じで、いつか訪ねてみたいと思っていた。
大曲で宿をとり、田沢湖線で角館駅に下車、
ちょうど駅前にレンタサイクルがあり、3時間くらい散策できた。

駅通りを1KMほどで、碁盤目に区画された商人町(外町トマチ)、火除けという防火地区を挟んで北に武家町(内町)が、道路の幅から曲がり角の一つまで、当時のまま残されている。
東西0.8Km、南北1kmくらいだろうか、北に古城山(城址)を仰ぎ、南に3本の大通りを中心に、統一された黒塀の中に、深い木立に囲まれて武家屋敷がみごとに調和して佇んでいる。
見上げるようなモミの大木、苔むした石畳、ところどころには楓の枝が垂れている。
黒塀から道路にふりそそいでいるのが、シダレザクラのようで、春の開花時期はさぞ見栄えがすることだろう。
観光ポスターを思い出した。
樺細工の実演工房や伝承館もあり、みやげ物として有名らしい。
山桜の樹皮を細工して茶筒や硯箱、お盆が多い。
角館町は、芦名氏の時代(1620頃)に、この三方を山に囲まれ、西に桧木内川に沿って、新しく作られた城下町とある。
南に広がる仙北平野:肥沃な農地・農民を治めるには適している。
後に佐竹氏に引き継がれ、京都を模して街づくりが行われた。
”みちのくの小京都”とも言われる。
いくつか残る武家屋敷の中でも、青柳家が有名で、秋田蘭画を確立した小野田直武も姻戚関係にあるとのこと。
平賀源内が久保田藩(のち秋田藩)・佐竹氏に鉱山開発の指導に招かれたこともあり、蘭画の技法を伝えたのが始まりらしい。
杉田玄白の「解体新書」の挿絵で有名、教科書で見たものと同じ記念碑があった。
そういえば、秋田市の千秋公園:県立美術館で、佐竹の殿様が描いた秋田蘭画の展示を見たことがある。

源内が、角館生まれかと思っていたが、それだけの縁らしい。
ちなみに、源内は男色家(衆道シュドウともいう)で、生涯妻帯せず、多少変人だったらしい。
わびさびの俳聖「松尾芭蕉」もそうだったとか。
欧米の同性愛とは似て非なり、男性優位の崇高な精神への憧れからとも言われる。
源内は電気の発明で、教科書で出てきた気がするが、舶来のエレキテル(静電気発生装置)を修復しただけで、
その原理は理解していなかったという。
また、蘭学者として外国文献や文化・技術を紹介した源内が、意外にも語学知識に乏しく、翻訳に頼っていたというのがほんとうであるなら、あり得ることだろうし面白い。
角館の武士は、陪臣(藩主の家臣(佐竹氏)の家臣)とかで、禄高は低かったが、絹、菅傘、樺細工など殖産に取り組んだので、
こういう屋敷を維持できたという。
西の通りは、御徒町だから、下級武士の住まいということで、敷地も狭い。
家の前を丁寧に掃き掃除している年配の女性にも軽く会釈され、旧家のしきたりが感じられた。
武家づくりの稲庭うどんのお店も、樺細工の装飾、清楚な雰囲気で、コシのあるうどんをおいしくいただいた。
商人町にも、旧家と道路が立派に保存されており、広い休憩所があった。
西宮家は、明治ー大正期に地主として栄え、母屋の障子・ガラスや蔵の感じが大正ロマンの趣がある。
管理は、角館町に委託され、着物の似合いそうな女性が由来などについて語ってくれた。
たてつ家では、M33に建てられ、ご先祖の生活用品、稚児・婚礼衣装、陶器などが当時のお蔵を資料館として展示・開放されている。おみやげ店の若い女性二人は、ここの娘さんで、この旧家で住まわれているそうだ。

まっすぐに伸びる広い道路、空き地にも続く黒い塀、屋敷内の手入れされた樹木など、よく維持できている。
重要伝統的建造物群保存地区に指定され、文化庁からの予算が回っているからだろうが、国の財政危機を思うと
いつまで頼れるのだろうか?
全国にこの指定地区が、弘前、萩(2ケ所)、知覧など10ケ所ある。
戻りは、西側の桧木内川の対岸から、湾曲した堤防に沿って2km続く桜並木を全望できる。
朱色の橋と深い桜の緑それに清流、これに春の爛漫と咲き誇る桜が加われば、絶景かな!
シーズンには、大型バスが列を連ねる。
ここ数ケ月、膝・腰を痛めているので、仕事先での散策を控えていたが、レンタサイクルでとても助かった。
”武家屋敷とシダレザクラ”品格と華という感じで、いつか訪ねてみたいと思っていた。
大曲で宿をとり、田沢湖線で角館駅に下車、
ちょうど駅前にレンタサイクルがあり、3時間くらい散策できた。


駅通りを1KMほどで、碁盤目に区画された商人町(外町トマチ)、火除けという防火地区を挟んで北に武家町(内町)が、道路の幅から曲がり角の一つまで、当時のまま残されている。
東西0.8Km、南北1kmくらいだろうか、北に古城山(城址)を仰ぎ、南に3本の大通りを中心に、統一された黒塀の中に、深い木立に囲まれて武家屋敷がみごとに調和して佇んでいる。
見上げるようなモミの大木、苔むした石畳、ところどころには楓の枝が垂れている。
黒塀から道路にふりそそいでいるのが、シダレザクラのようで、春の開花時期はさぞ見栄えがすることだろう。
観光ポスターを思い出した。
樺細工の実演工房や伝承館もあり、みやげ物として有名らしい。
山桜の樹皮を細工して茶筒や硯箱、お盆が多い。
角館町は、芦名氏の時代(1620頃)に、この三方を山に囲まれ、西に桧木内川に沿って、新しく作られた城下町とある。
南に広がる仙北平野:肥沃な農地・農民を治めるには適している。
後に佐竹氏に引き継がれ、京都を模して街づくりが行われた。
”みちのくの小京都”とも言われる。
いくつか残る武家屋敷の中でも、青柳家が有名で、秋田蘭画を確立した小野田直武も姻戚関係にあるとのこと。
平賀源内が久保田藩(のち秋田藩)・佐竹氏に鉱山開発の指導に招かれたこともあり、蘭画の技法を伝えたのが始まりらしい。
杉田玄白の「解体新書」の挿絵で有名、教科書で見たものと同じ記念碑があった。
そういえば、秋田市の千秋公園:県立美術館で、佐竹の殿様が描いた秋田蘭画の展示を見たことがある。


源内が、角館生まれかと思っていたが、それだけの縁らしい。
ちなみに、源内は男色家(衆道シュドウともいう)で、生涯妻帯せず、多少変人だったらしい。
わびさびの俳聖「松尾芭蕉」もそうだったとか。
欧米の同性愛とは似て非なり、男性優位の崇高な精神への憧れからとも言われる。
源内は電気の発明で、教科書で出てきた気がするが、舶来のエレキテル(静電気発生装置)を修復しただけで、
その原理は理解していなかったという。
また、蘭学者として外国文献や文化・技術を紹介した源内が、意外にも語学知識に乏しく、翻訳に頼っていたというのがほんとうであるなら、あり得ることだろうし面白い。
角館の武士は、陪臣(藩主の家臣(佐竹氏)の家臣)とかで、禄高は低かったが、絹、菅傘、樺細工など殖産に取り組んだので、
こういう屋敷を維持できたという。
西の通りは、御徒町だから、下級武士の住まいということで、敷地も狭い。
家の前を丁寧に掃き掃除している年配の女性にも軽く会釈され、旧家のしきたりが感じられた。
武家づくりの稲庭うどんのお店も、樺細工の装飾、清楚な雰囲気で、コシのあるうどんをおいしくいただいた。
商人町にも、旧家と道路が立派に保存されており、広い休憩所があった。
西宮家は、明治ー大正期に地主として栄え、母屋の障子・ガラスや蔵の感じが大正ロマンの趣がある。
管理は、角館町に委託され、着物の似合いそうな女性が由来などについて語ってくれた。
たてつ家では、M33に建てられ、ご先祖の生活用品、稚児・婚礼衣装、陶器などが当時のお蔵を資料館として展示・開放されている。おみやげ店の若い女性二人は、ここの娘さんで、この旧家で住まわれているそうだ。


まっすぐに伸びる広い道路、空き地にも続く黒い塀、屋敷内の手入れされた樹木など、よく維持できている。
重要伝統的建造物群保存地区に指定され、文化庁からの予算が回っているからだろうが、国の財政危機を思うと
いつまで頼れるのだろうか?
全国にこの指定地区が、弘前、萩(2ケ所)、知覧など10ケ所ある。
戻りは、西側の桧木内川の対岸から、湾曲した堤防に沿って2km続く桜並木を全望できる。
朱色の橋と深い桜の緑それに清流、これに春の爛漫と咲き誇る桜が加われば、絶景かな!
シーズンには、大型バスが列を連ねる。

ここ数ケ月、膝・腰を痛めているので、仕事先での散策を控えていたが、レンタサイクルでとても助かった。










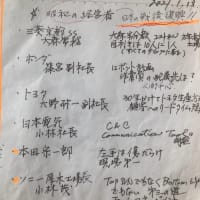
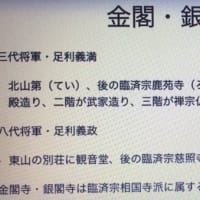
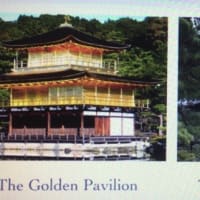
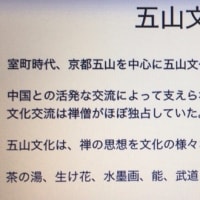
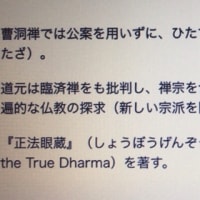
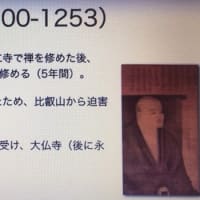
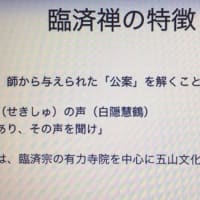
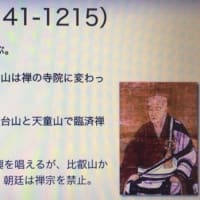
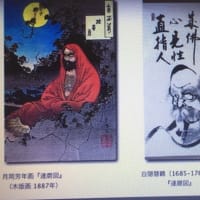
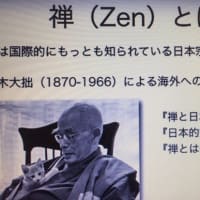
いい佇まいですね。
平賀源内といえば
う・な・ぎ・(*^_^*)
山桜の樹皮、樺細工、そういうの好きです♪
美○子さまへのおみやげに??うふっ
旧家のしきたり、こうした歴史上の重要伝統的建造物、いつまでも遺して欲しいです。
腰・膝、どうぞおだいじになさってください。
高価なおみやげは無し、カリントウと武家煎餅でした。
『償い』さんの相変わらず精神的充実/エイジングブライト(歳とともに輝きを増し続ける=これも”私造ことば”)に敬服します。
私もまだまだブライトを目指します。
我がブログへのお立ち寄りに感謝!